ベトナムの出生率は女性1人当たり1.91人にまで低下し、史上最低水準となった。
同時に、ベトナムは世界で最も急速な高齢化に直面しており、2036年までに60歳以上の人口が人口の20%を占めると予想されています。こうした静かな変化は、将来の人材、社会保障、そして持続可能な開発にとって大きな問題となっています。
心配なのは、数字だけではありません。経済的なプレッシャー、性別による固定観念、仕事と家庭の不均衡などにより、望む通りに子供を持つことができない人が増えているという事実もあります。
世界人口デー(7月11日)を機に、ダン・トリ記者はベトナムの国連人口基金代表マット・ジャクソン氏に独占インタビューを行い、現在の人口動態を検証し、生殖の自律性、すなわち各個人が自身の状況と希望に従って子供を持つかどうかを決定する権利を持つことを保障する、という点に重点を置いた人口政策のアプローチを策定した。
生きる意欲は限られている
ベトナムの現在の人口状況、特に出生率の低下傾向をどのように評価しますか?
-ベトナムは深刻な人口動態の転換期を迎えています。合計特殊出生率(TFR)は、1950年代の女性1人当たり約5人から1989年には3.83に低下し、2024年には1.91となり、史上最低水準となります。
出産する女性の平均年齢も28~29歳程度まで上昇しています。これは、若い世代の家族形態、社会経済状況、そして人生に対する期待の大きな変化を反映した傾向です。
しかし、懸念されるのは数字だけではありません。今こそ、より大きな視点で物事を考え、人々の生殖に関する選択や欲求に影響を与える障壁を取り除く時です。


若者の多くは、依然として子供を持ちたくない、あるいは子供が少ないことで満足していると言っています。これは個人的な意見でしょうか、それとも、若者が望む家庭を築くことを困難にする多くの要因があるという、より深い原因によるものだと思いますか?
- UNFPAはYouGovと協力し、5大陸14か国の14,000人を対象に調査を実施し、ある現実を明らかにしました。人々は自分たちの望む家族を築くことができているのでしょうか?
調査結果によると、生殖の意思を果たせない成人の割合は驚くべきレベルに達している。
50歳未満の5人に1人は、希望する数の子供を産めないと考えています。出産を終えた人の3分の1は、当初希望していたよりも少ない数の子供を産むと答えています。
したがって、本当の問題は出生率が低下していることではなく、生殖欲求が満たされず、選択肢が否定されていることなのです。
世界は急速に変化しています。世界人口は今世紀中にピークを迎え、その後減少すると予測されています。これは、高齢者の増加と労働力の減少という形で、社会が変化し続けることを意味します。
こうした人口動態のジレンマに直面して、世界中の政策立案者や 政治家は終末シナリオをますます懸念しており、個人の再生産願望を国家の人口目標と一致させることを拒否する女性たちに対してますます批判的になっている。
しかし、現在の出生危機の本質は、子どもを持つかどうか、いつ持つか、誰と持つかといった個人の生殖に関する決定がひどく妨げられていることにある。
ベトナムの若者が「出産を恐れる」4つの障壁

現在の出生危機の本質は、個人の生殖に関する決断にあります。
具体的に、多くのベトナムの若者が子供を持つことを負担だと感じている障壁は何でしょうか?
-今日の若者が結婚や出産を躊躇したり遅らせたりする主な理由は 4 つあります。
まず、経済の不安定さがあります。国連人口基金(UNFPA)の「世界人口白書2025」によると、人々が望む数の子どもを持つことができない主な理由は経済的な制約です。
調査対象者の半数以上が、経済的な不安、雇用の不安定さ、住宅費や育児費が最大の障壁であると答えた。
第二に、ジェンダー固定観念の圧力があります。報告書によると、世界的に女性は依然として男性の3~10倍もの無償の介護・家事労働を担っています。
それどころか、男性が育児や家事の分担のために仕事を休むと偏見を持たれ、夫婦が家庭を築く上で不平等な環境が生まれます。


第三に、ワークライフバランスの不均衡です。長時間労働、育児休暇の制限、そして柔軟性の欠如は、子育てを非常に困難にしています。
186カ国が産休を設けている一方、父親の育児休暇を設けているのはわずか122カ国で、平均はわずか9日です。
最後に、文化的規範と性別の役割は、各人の生殖に関する決定に強い影響を及ぼします。
女性は依然として、一定の年齢に達する前に結婚し、結婚後すぐに子供を産み、キャリア開発よりも家族を優先することが求められ、不妊、中絶、家族計画といった問題について話すことも許されていない。
若者が結婚や出産から遠ざかっているのではなく、単に障壁が多すぎて苦しんでいるだけなのだと理解する必要があります。こうした選択が経済的にも精神的にもリスクを伴う社会において。

女性や若者が結婚が遅いとか子供を持たないことを責めるのではなく、次のような問いかけをすることが重要です。夫婦や個人が望む数の子供を持つことを妨げている障壁は何なのか、そしてその障壁を取り除くために私たちは何ができるのか。
高齢者介護の経済
同氏によれば、ベトナムは「第二の日本」になる危険にさらされているのだろうか。つまり、異なる状況下で急速な人口高齢化の過程に突入するということであり、日本は既に先進国であったのに高齢化が始まったのに対し、ベトナムは依然として低中所得国にとどまっているということだ。
国連の定義によると、60歳以上の人口が総人口の20%を超えると、その国は「高齢化」段階に入ります。ベトナムは2036年までに60歳以上の人口が2,000万人を超える「高齢化」国になると予測されています。
このプロセスは非常に急速に進行しており、わずか25年(2011~2036年)で進行します。これは、米国の69年、フランスの115年と比べても大きな差です。ベトナムは世界で最も急速に高齢化が進む国の一つになりつつあります。
しかし、高齢者人口が増加していることは憂慮すべきことではなく、経済、社会、健康の面で大きな前進です。
問題は年齢ではなく、高齢者が価値ある人生を送り続けるための条件を私たちがどのように認識し、作り出すかです。

問題は年齢ではなく、高齢者が価値ある人生を送り続けるための条件を私たちがどのように認識し、作り出すかです。
日本のような多くの先進国では、高齢者であっても条件が整えば自分なりの方法で働き、社会経済生活に参加できるのが現実です。
そのためには、2つの中核となる要素を重視する必要があります。1つ目は、高齢者が常に最新の情報を入手し、役立つ情報にアクセスできるよう、テクノロジーやイノベーションへのアクセスを含む生涯学習の機会を提供することです。
二つ目は、尊厳ある老後を過ごすための包括的なケアシステムです。ベトナムの文化では、高齢者は子供や孫と一緒に暮らすことが多いです。
これは、子供と両親の両方の世話をしなければならない女性にとって大きな負担となります。
したがって、高齢者が家族や社会の負担とならないように、高齢者をケアする経済の構築に注力する必要があります。高齢者のケア、保護、そして高齢者の役割の促進を国の社会経済発展政策システムに統合し、高齢者が自分らしい働き方で社会に貢献し続けることができる条件を整えることが重要です。
女性フリーランス労働者のグループにもっと注目するべきです。
UNFPAは、保健省が政府に提出している人口法案の中で、特に第二子を出産する女性の産休を7か月に延長することや、工業団地で二人の子供を持つ女性への住宅支援に関する政策の方向性をどのように評価していますか。
- UNFPAは、生殖に関する権利と出産に関する決定における各個人の主体性を強調した人口法案の明確な進展を高く評価する。
具体的には、第二子を出産する女性の産休を7か月に延長するという提案は、生殖に関する決定に影響を及ぼす可能性のある経済的圧力と育児負担を軽減する前向きなシグナルです。
しかし、この政策は現時点では、契約と社会保険に加入している正規労働者にのみ有効です。一方、ベトナムの女性労働者の60%以上は、契約や社会保険に加入していないフリーランスを含む非公式セクターで働いており、同様の福利厚生を受けることができません。


したがって、真に公平で包括的な政策を望むのであれば、非公式雇用の女性、少数民族の女性、移民、不安定な雇用に就いている女性など、あらゆる女性グループの権利を保障する仕組みが必要です。
2人の子供を出産する女性に対する住宅支援政策に関しては、これは前向きな動きではあるが、支援エコシステムの全体的な文脈の中で位置づけられる必要がある。

多くの国の教訓から、経済的な出生促進政策は短期的な影響しか及ぼさず、夫婦が出産の時期を調整する可能性はあっても、子どもの総数に大きな変化をもたらすことはないということがわかっています。
ベトナムのように人口転換の岐路に立つ国々に対し、UNFPAはどのような提言を行っているのでしょうか?世界的な潮流に対応しつつ、個人の自己決定権を保障するために、人口政策にはどのように取り組むべきでしょうか?
世界人口が80億人に達する中、世界は二つの大きな懸念に同時に直面しています。一つは人口爆発への懸念、もう一つは出生率の低下です。こうした変化に直面し、国連人口基金(UNFPA)は次のように提言しています。「政府は政策立案において人々を中心とし、人々の真のニーズと要望に耳を傾ける必要があります。」
つまり、政策はパートナーの選択から、いつ子供を産むか、何人産むか、出産間隔に至るまで、個人の自主性を保証する必要があるということだ。

マット・ジャクソン氏は、政策は人間中心である必要があるとコメントした。
私たちは、人口動態指標を懸念するアプローチから、回復力と積極的な対応を構築するアプローチへと変えていく必要があります。
持続可能な人口転換は、理想的な出生率や人口置換水準に到達することではなく、誰もが自らの将来を決定する権利と手段を持つ社会を創ることにあります。
人口法案は、そのビジョンの実現に向けた正しい方向への一歩であり、UNFPAはベトナム政府と共にこの道を歩む用意ができています。
お話させていただきありがとうございました!
出典: https://dantri.com.vn/suc-khoe/truong-dai-dien-unfpa-nguoi-tre-khong-ngai-sinh-ho-mac-ket-boi-rao-can-20250710180935964.htm



























![[写真] ザーライ省の指導者らが中央高地の少数民族とともにホーおじさんの記念碑に花を捧げる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)




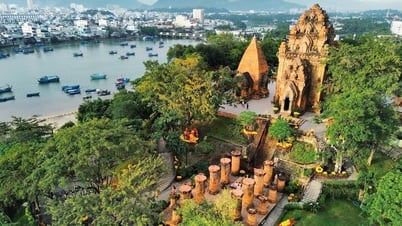







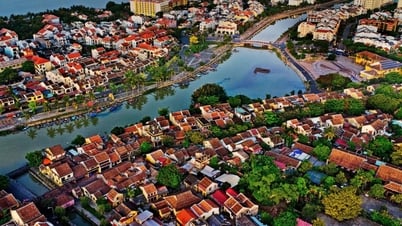



























































コメント (0)