国を再編する
ト・ラム書記長率いる中央工作代表団は6月29日午後、ホーチミン市スアンホア区の党委員会常務委員会と協力した。
事務総長は次のように指摘した。「区レベルの行政単位は、これまでの区レベルとは異なる考え方を持つ必要がある。これまで行政と管理に重点を置いてきたのなら、これからは創造と人々への奉仕へと転換しなければならない。区内で人々が必要としているもの、あるいは困難に直面しているものはすべて、遅滞なく、即座に解決することに注力しなければならない。区の権限を超える問題は、速やかにホーチミン市に報告しなければならない。」
7月1日より、第3区は50年にわたる建設と開発の歴史的旅に正式に終止符を打ち、バンコ、スアンホア、ニエウロックの3つの区に新たな歴史のページを開きました。
スアンホア区は、中央政府や市の主要機関の本部のほとんど、中華人民共和国、ロシア連邦、日本などの大国の総領事館の本部、サイゴン大司教区、ヴィンギエム寺などの宗教施設が集中しており、 政治的な安全、秩序、社会の安全にとって重要な地域です。

ト・ラム書記長率いる中央作業代表団は、6月29日午後、ホーチミン市スアンホア区の党委員会常務委員会と協力した。写真:NLĐ
ト・ラム書記長の現地視察は、7月1日の歴史的瞬間に備えるためのものだ。
ホーチミン市は、ビンズオン省およびバリア・ブンタウ省と合併しますが、名称はホーチミン市のままです。新市は面積6,772平方キロメートル以上、人口1,400万人以上、168の市町村レベルの行政単位を有します。ベトナム国レベルでは、省は63省から34省に縮小され、市町村は10,035から3,321に削減され、郡レベルの行政単位は廃止されます。
この移行を実行するために、国会は憲法、地方自治組織法、政府組織法を改正し、政府も一連の法令を公布した。そのうち 28 件は地方分権と権限委譲に関する法令であり、約 40 件は付随する法令であった。
これは、ト・ラム書記長が述べたように、「国の再編」です。中央、省・市、村・区という三層制の政府構造は、ベトナムが現在世界の約80%の国で採用されているモデルに近づくことに役立ちます。
これは単なる行政組織の変更ではなく、党と国家の深い革新的思考、強い政治的決意、戦略的ビジョンを示す包括的な制度革命です。
この協定により、経済圏が連携し、より広い経済空間が創出され、各地域の強みを活かして成長時代への備えが整います。合併後の省市の多くは、人口200万~300万人規模で、経済規模も大きく、山岳地帯、平野部、沿岸部が混在する地域となっています。これらの要因により、各地域は真の潜在力を持つ強力な経済圏へと発展していくでしょう。
特に、ビンズオン省(工業の中心地)とバリア・ブンタウ省(工業と観光の中心地)が統合された新しいホーチミン市など、この地域と比較できる優れた経済空間がいくつかあります。
経済インフラ開発、科学技術、デジタル変革、高速鉄道、原子力、金融センターなど、経済、成長、経済再編を促進するための多くの解決策があり、また、その装置の配置も行われています。
団結が鍵
ソクチャン省ビジネス協会会長、メコンデルタビジネス協会評議会副会長のトラン・カック・タム博士は、VietNamNetで次のように警告した。「大きな課題は、いかに和解し、統一された組織体、共通の目標のために円滑に機能する組織を構築し、地域間の不健全な競争を回避していくかということです。地域や「あなたの部族」か「私の部族」かに関わらず、真に有能な公務員を昇進させる仕組みが必要です。」
この状況は、ト・ラム書記長も「機構合理化革命における団結の力」という記事の中で指摘している。彼は、機構の整理・再編の過程において団結が欠如すると、多くの課題や分裂のリスクが生じると述べた。まず、職員の間では、統合によって職を失ったり、転職を余儀なくされたりするのではないかという不安が生じている。影響を受ける職員に対して明確かつ合理的な方針がなければ、「意見が合わない」というネガティブな心理状態が生じやすく、内部の不和を招きやすい。
さらに、地域感情も注目すべき課題です。誰もが故郷、かつて愛着を持っていた場所に愛着と誇りを持っています。市町村合併の際には、新市名、本社所在地、人員配置などをめぐる懸念から、メリットとデメリットの比較が起こりやすく、合併のプロセスを阻害する要因となります。
山岳省と平野省、そして「豊かな」省と「貧しい」省の合併には、指導部が公平な立場に立ち、資源のバランスを確保し、開発上の利益を調和させるビジョンを持つことが求められる。配分に公平性が欠ければ、地域間の不平等が容易に生じ、連帯感に亀裂が生じる可能性がある。

山岳省と平野部、そして「豊かな」省と「貧しい」省の統合には、指導部が公平な立場と先見性を持つことが求められる。写真:ホアン・ハ
二重従属モデルは時代遅れです。
ベトナムは1945年以来、旧社会主義国の特徴である二重従属モデルを採用しています。したがって、政府機構は中央、省・市、県・郡、そしてコミューン・区の4つのレベルに分かれています。地方機関は中央政府からの垂直的な指導を受けると同時に、同レベルの地方自治体による行政管理も受けています。
各階層には、党、政府、祖国戦線、そして社会政治組織が十分に存在します。このモデルは指揮統制の統一に役立ちますが、同時に、機構を煩雑にし、階層化し、重複させています。
例えば、投資プロジェクトは、各レベルの部局、人民委員会、人民評議会といった一連の機関を経由し、その後、省庁や政府へと進む必要がある場合があります。こうした重複や絡み合いにより、意思決定プロセスは長期化し、行政コストは高くなり、関係者間の連絡は多くても非効率的になります。
現在、二重従属モデルを維持している国は、ベトナムを含めて世界でも数カ国しかありません。
創造とサービスの装置
ト・ラム書記長は、国際調査によると、約80%の国が三層制政府モデルを採用していると述べた。ベトナムは、中央政府、省・市、町村・区というモデルに基づき、この方向で行政機構の再編を進めている。
彼によると、コミューンレベルは人々に最も近い場所であり、政策や指針を直接実行する場所であるため、「最も重要な政府レベル」となるだろう。コミューンレベルが弱体であれば、政策は実行されない。逆に、コミューンレベルに真の権力が与えられれば、効果的な機構の基盤となるだろう。
人民に近い草の根モデルは、「服従・命令」の状態から「自律・自己管理」、「管理」から「奉仕」へと移行する。これが新しいモデルの核心精神である。
この改革により、中間レベル(地区)が廃止され、100以上の地区レベルの業務が省へ、約600の業務がコミューンへ移管されます。これは、草の根レベルへの権限委譲、給与体系の合理化、予算支出の削減、業務効率の向上を意味します。
ファム・ミン・チン首相が強調したように、これは組織構造と経営思考における「革命」です。政府はもはや人々がドアをノックするのを待つのではなく、積極的に草の根に働きかけ、耳を傾け、人々と企業の課題を根本から解決しなければなりません。そして何よりも重要なのは、物事を成し遂げることです。
これは「行政管理」から「創造的・サービス的管理」への変革であり、国家が管理者ではなく、コミュニティの発展の伴走者であり促進者であるという、国家管理における現代的な概念です。
三層制政府モデルは、画期的かつ包括的で建設的な一歩です。この改革は、単に境界や組織構造を再編するだけでなく、国家と国民、中央と地方、そして国家と市場の関係を再構築するものです。
このモデルの成功には、革新の精神、社会的合意、そして何よりも断固たる行動が必要です。組織が合理化され、効率化され、幹部が国民に密着して初めて、私たちは国民により良い奉仕を提供し、国がより速く、より強く、より持続的に発展していくことに貢献できるのです。
ベトナムネット
出典: https://vietnamnet.vn/trang-moi-cho-viet-nam-2416511.html










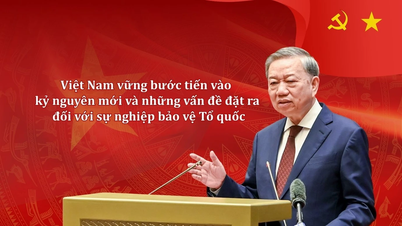











![[写真] ト・ラム事務総長が決議第57-NQ/TW号の実施に役立つ3つのデジタルプラットフォームの立ち上げに出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/2/d7fb7a42b2c74ffbb1da1124c24d41d3)



































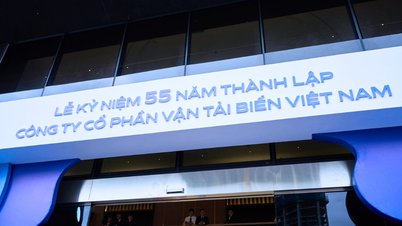





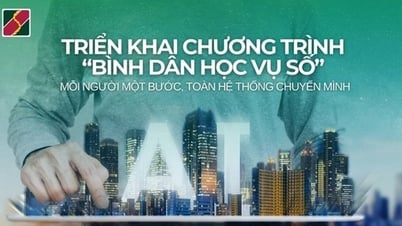














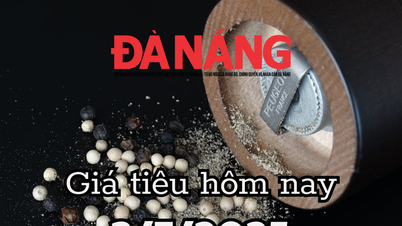


















コメント (0)