家の前に植えようと、森から持ってきた真っ赤な野花。一見、ひまわりや牡丹にも似ているが、実は違う。この植物は奇妙な成長を見せた。この植物にとって、日光は欠かせないエネルギー源であり、生命の源であり、命に潤いを与えるものだった。不思議なことに、中部地方の強い日差しは、他の花が枯れていく中、この花を赤い唇をすぼめ、より一層鮮やかに見せていた。彼女はそれを「陽光に飢えたボン」と名付けた。彼は微笑んで、当然のように同意した。そう、スイレンやセスバニアのように、「陽光に飢えたボン」だ。いかにも南国らしい名前だ。そして、それはいつもそうだった。彼女の押し付けは、彼はいつも無条件に、何の異論もなく受け入れてきた。

イラスト:LE NGOC DUY
テト前の南行き列車はガラガラだった。当然のことながら、ほとんどの労働者は年始に故郷を離れて南へ働きに行き、年末に家族と再会するために帰省する。そのため、南北を結ぶ列車の切符は数ヶ月前から予約する必要があり、南北を結ぶ列車の予約はまばらだった。そこで切符売りの店員は彼女を見て、温かい笑顔で言った。「どの車両でも、どの席でも構いません。疲れたら寝台車で寝てください。列車全体に乗客は少ないですから」
彼女が列車に乗ることを選んだのは偶然ではなく、この土地、あの人との運命の終わりだった。かつて、この同じ駅で彼は彼女を冷淡に迎え、二人は恋人同士になった。太陽と風に満ちたこの土地は、彼女に南部風の騎士道精神あふれる人々が暮らす国を見せてくれた。
そして彼女は恋に落ちた。太陽に恋し、風に恋し、愛は彼女の全身に染み渡り、まるで掴み、愛撫できるかのように感じられた。戦争の悲劇的な名前の一つ一つ、穏やかな川の別れの痛みの一つ一つ、道端の野に咲くヒナギクの一つ一つに恋をした…まるでこれほどまでに心を開くことができなかったかのように、彼女は恋に落ちた。そして今、大地と空が交わる瞬間、人々が集い、船は彼女を南の地へ連れ戻すという奇妙な使命を、まるで人の命の循環のように成し遂げる。彼女はそれを運命と呼ぶ。
汽笛が長く鳴り響き、それからガタガタと音を立てて走り去っていった。見送りの人たちも徐々に離れていったが、もちろん私はその中にいなかった。この駅で君を迎えに行くのは初めてだから、これが最後の見送りになるんだろう?でも、今は子供たちを学校に送っている最中で、彼らは何か言い争っていた。上の子は歴史が好きで、下の子は文学の話が好きだったので、私はよくその会話をまとめなければならなかった。
列車に乗る前夜、彼女は彼の家へ向かった。街からそう遠くない田舎にある。タイル張りの3部屋しかない家は、果樹に囲まれていた。かつて彼と暮らすためにここに引っ越してきた時期もあったが、練習にもっと時間を費やすため、結局は都会の古い家へ移らざるを得なくなった。彼は果樹を集めるのに熱中し、庭のあちこちに植えていた。
本当は、彼女は自分が選んだ道を彼に導きたかったのだが、彼が感傷的で、自分の感情をなかなか手放せないと感じ、諦めてしまった。彼は若い頃、物乞いの女にご飯をあげるために、米の缶詰を担いで1キロ近く走ったことを彼女に話した。ある時、出張中に山間の村で困っていた貧しい母親に、最後の小銭をあげてしまった。帰り道、車がガソリン切れになり、友人たちに助けを呼ばなければならなかった。
その後、彼は日々の悩みに囚われてしまいました。この人にとって、すべてを手放すことは難しく、ましてや自分自身を手放すことなど考えられませんでした。彼女は自ら選んだ道を歩み始め、彼の日々の物思いに沈んだ視線、遠くを見つめる非難めいた言葉を無視することを学びました。そして彼は徐々に結婚生活の軌道から外れ、彼女が望んでいた通り、子供たちの世話だけに集中するようになりました。
彼女は人目につかない隅っこを覗き込んだ。家の中は夕食の真っ最中で、末っ子が父親を呼ぶ声がはっきりと聞こえた。スプーンや椀がぶつかり合う音、扇風機が回る音も聞こえた。兄は晴れの日も寒さの日も、天気に関わらず扇風機を使う癖があった。誰かに食べ物を持ってきてもらうように頼んでいた。兄もそうだった。一緒に暮らしていた頃、机の上で食事をする兄のせいで、彼女はよく文句を言っていた。それが病気の元凶だったのだ。離婚後、兄は末っ子とこの階で暮らしているが、それでも彼女は時々メールで兄に用件を伝えていた。
放せ、言ったでしょ!
先生は、前世は宮廷に仕える侍女だったと話した。なんとも不思議なことに、毎晩夢の中で自分と姫が一団に追われているのを見たという。そして先生は、彼女には定められた運命があり、修行し、手放さなければならない、血縁関係や祖先崇拝の儀式をすべて手放さなければならないと告げた。先生に出会う前は、人生はあまりにも複雑すぎると感じていた。なぜ日々の怒りや憎しみ、愛に囚われ、苦しみに身を委ねるのだろうか?なぜこんな人生を送らなければならないのだろうか?
彼女はかつて、自分は家庭的な女性ではないと告白した。あの名もなき仕事に多くの時間を費やしたくなかったのだ。家庭生活でも同じだった。果てしない世界の前で、自分の存在が小さく感じられるのだ。
「自分を解放しなくてはならない」と彼は彼女に言った。
ある人が彼女に、出版前の詩集の編集を手伝ってほしいと頼んだ。彼の詩はいつも人生や人々への苦しみと負い目に満ちていて、優雅とは程遠いものだった。
「気楽で平穏な気持ちになるには、手放さなきゃいけないのよ、愛しい人」と彼女は作家に言った。彼はそれを分かっていながらも、きっとできないだろうと思いながら、思慮深く言った。ああ、どうしてみんなこんな風に苦しまなきゃいけないのかしら、と彼女はため息をついた。
トンネルに差し掛かると、誰かが「あそこにハイヴァン山がある、なんて美しいんだ」と言った。列車はまるで巨大な風のニシキヘビのように峠をしっかりと包み込む。かつてないほど美しい弧を描きながら、乗客全員が雲の中へと突き進む長い列車の姿を心ゆくまで眺める、かけがえのないひとときを過ごした。
列車は汽笛を鳴らし、暗いトンネルへと突入した。列車の各車両が闇に飲み込まれていく。
車両に着く寸前で、彼女は悲しげにため息をついた。慌てて辺りを見回すと、雲間から太陽の温かい光が山頂で戯れていた。
時間が止まったようだった。彼女は世界の二つの半分の間にいた。数秒後には、闇の世界へと漂い落ちるだろう。その時、彼女は突然、太陽を渇望する花、自分が名付けた花のことを思い出した。
ミン・アン
ソース
















































































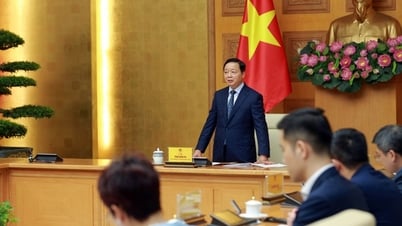
















コメント (0)