開発研究所は、ビンチャン地区が2030年までに地区に転換される可能性は低いため、ホーチミン市管轄下の市になるべきだと提案した。
この提案は、ホーチミン市開発研究所(HIDS)が、ビンチャン地区を地区または市に変えるプロジェクトを完了するための提案草案の中で、9月22日に実施される予定だった。
ビンチャン区はホーチミン市の南西の玄関口に位置する郊外地区で、面積は252平方キロメートルで、カンザー区とクチ区に次ぐ面積を誇ります。人口は71万1千人で、ベトナムで最も人口の多い地区です。近年、この地域の都市化率は急速に高まっています。

ビンチャン地区の一部を上空から撮影。写真:タン・トゥン
HIDSによると、現状と「都市の分類に関する決議」、「行政単位の基準及び行政単位の分類に関する決議」による基準を比較すると、ビンチャン省が現在から2030年まで地区レベルの行政単位に変更される可能性は低いという。
一方、この地域は、2025年までに都市内都市モデルに転換し、都市分類タイプIIIの基準を達成することができます。この目標を達成するために、ビンチャン地区は2030年までに、都市インフラ、交通、環境改善を開発するための多くのプロジェクトに投資する必要があります。総投資資本は、社会化財を含めて約122,695億ドンと推定されています。
国会常務委員会決議第1211号によれば、省都または中央直轄市の基準は、人口15万人以上、面積150平方キロメートル以上、社級行政単位が10以上、社級行政単位の総数に対する区の比率が65%以上…となっている。
中央直轄市の管轄区域となるための基準には、人口密度が1平方キロメートルあたり1万人、非農業労働力が労働力全体の90%、工業、商業、サービス、観光が経済構造に占める割合が90%以上、都市インフラが同期して完備していることなどが含まれます...
HIDSによると、ホーチミン市とメコンデルタ各省を結ぶ交通の要衝であるにもかかわらず、地区内の交通インフラは、特に近隣地域やロンアン省に隣接する地域において依然として限られている。このことが、都市化、経済発展、そして両地域間の連携を大きく阻害している。
さらに、地区内には依然として多くの土地が存在しているものの、有効活用されていません。農村行政単位による管理体制は多くの困難に直面しており、人々の生活の質を向上させるための経済・社会発展の突破口を開くことができていません。
地区レベルから都市行政単位(市内都市モデル)への転換により、ビンチャン市はインフラに投資し、潜在力と強みを活かす条件が整うことが期待されます。
区や市の行政単位を設立するための地区建設への投資計画は、2020~2025年度ホーチミン市党大会第11回決議に盛り込まれた課題です。過去2年間、ホーチミン市の5つの区、すなわちクチ区、ビンチャン区、カンザー区、ニャーベ区、ホックモン区は、いずれも2030年までに市となることを目指してきました。
昨年末、2021年から2030年にかけての地区の地区(または市)への投資と建設プロジェクトの進捗状況に関する会議の後、市人民委員会は郊外の地区に対して、地区または市になるための承認を申請せず、ホーチミン市の基準を満たすまで待って、各地域に適したモデルを決定するよう要請した。
ル・トゥイエ
[広告2]
ソースリンク



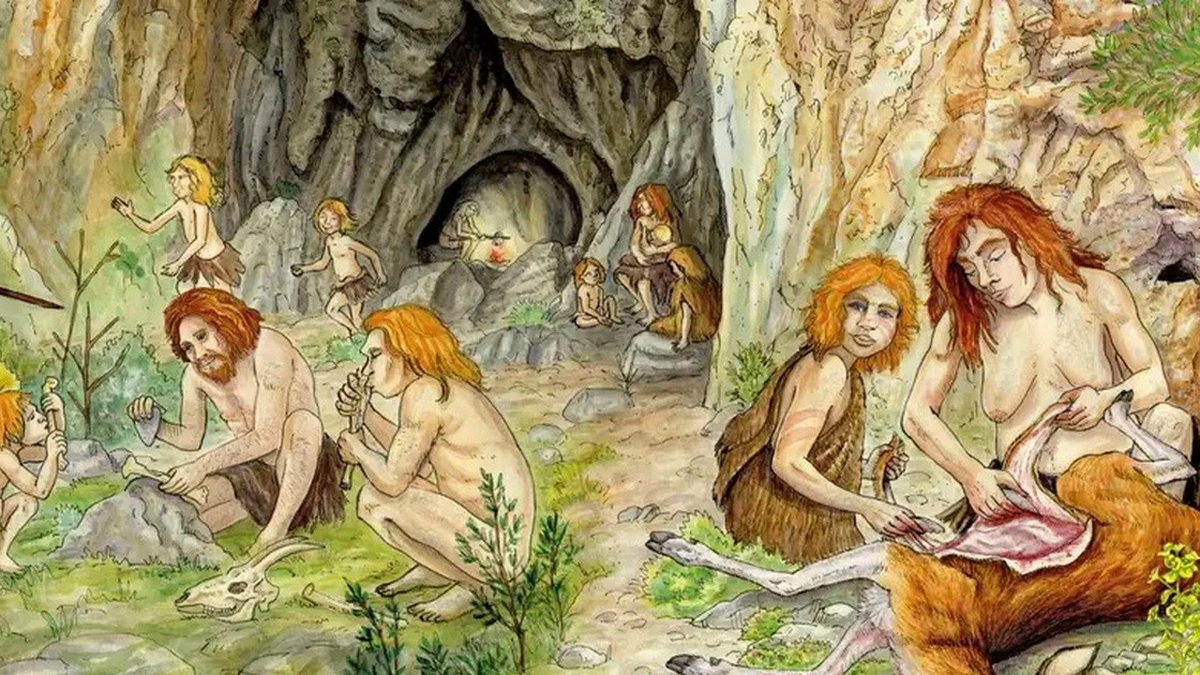
























































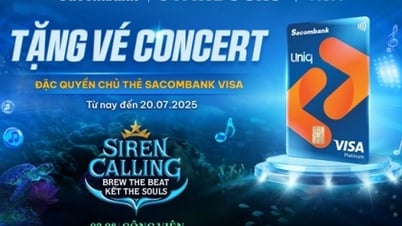











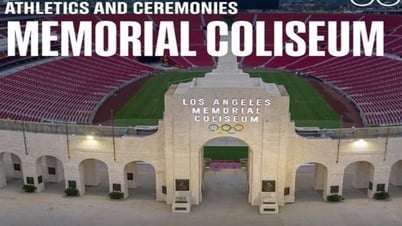


















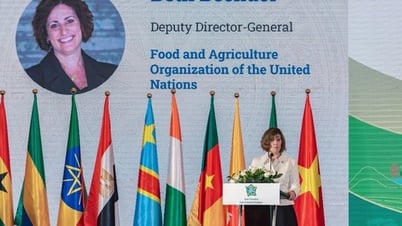










コメント (0)