路地の突き当たりに着くと、ソイはク・ムンの泣き声を聞きました。彼女は額を伝う汗を拭うために立ち止まりました。夕暮れ時、家の中の電球が点いたばかりで、ランプシェードの周りを蟻が飛び回っていました。ポーチのマットの上で、ク・ムンは癇癪を起こすかのように泣きました。台所では、ソイの母親が暖炉のそばに座り、悲しみと疲れに顔をしかめ、ク・ムンが泣き終わるまで見守っていました。「どうして泣いているの?おばさんが帰ってきたのよ!」ソイは息子を慰めるために身をかがめました。ソイの腕の中で、ク・ムンはすぐに泣き止み、手の甲で鼻を拭いて微笑みました。ソイは彼を抱きかかえ、庭を歩きながら優しく撫でました。すると、すぐに彼は眠りに落ちました。手はまだおばさんのシャツをしっかりと握っていました。ソイは息子をベッドに寝かせると、台所へ急いで行き、お盆に食器を並べ、母親の方へ向き直って尋ねました。「お母さん、夕食を作ってあげるわ!」母親は咳き込み、さらに薪を台所に押し込みながら、重々しい声で答えました。「どんなお米も水も、私には飲み込めないわ!」
ソイは静かに台所へ行き、ご飯を温めた。それから庭へ行き、サツマイモの芽を摘み、ナスを魚醤で焼いた。これで食事は十分だった。質素な食事が運ばれ、ゆっくりと咀嚼する母親を見て、ソイは申し訳なく思った。「明日はヌーおばさんのために山に登って薬草を摘むわ。お金ができたら市場に食べ物を買ってこようかしら」。母親は乾燥盆の上の薬草を袋に詰めながら、「家事も孫の世話も全部一人でこなしてたら、夫や子供たちと過ごす時間なんてどこにあるのかしら」と呟いた。ソイはこっそりと微笑み、洗面器を持って井戸へ向かった。一日中働き続けたせいで、灰が髪にこびりついていた。ソイはバケツの水を汲み、すぐに向きを変えて洗面器の洗濯物を洗った。洗い終わると、干し草の山の上に月がかかり、野菜畑に冷たく白い光が広がっていた。家の中では、二人はぐっすりと眠り、整然とした呼吸が空っぽの家の中を響かせていた。小さな男の子は寝返りを打ち、母親の名前を呟いた後、再び眠りに落ちた。トムという母親はソイの妹で、19歳で母親になり、子供を妹に預けて長い間家を空けていた。時折、少しの間だけ立ち寄っては子供を抱きしめるだけだった。
夜は風に吹かれて静まり返っていた。十字路の綿の木が揺れ、赤い葉の束を落としていた。綿の木の下で遊んだばかりの村の子供たちは、もう家に帰ってきた。彼女は壁に映る自分の震える影を見つめていた。夜ごとに少しずつ年を重ねていくのを感じ、唇は季節の最後のしおれた花びらのようにしわくちゃになっていた。
* * *
まだ霧が濃く、ソイはすでにリュックサックを背負って山を登っていた。彼女は花咲くシムの森を通る曲がりくねった赤い土の道をたどり、バイチャイに続く道に曲がった。ソイはリュックサックを放り投げ、五色の花を一束摘み、口に運び、残った甘い蜜を吸った。ソイの手は器用に葉を摘んだ。ソイのように葉を摘み慣れている者だけが、どの茂みに薬草の葉があるかを知っているだろう。村では、ソイが摘んだ薬草だけがヌー夫人を満足させられる。その葉にはまだ露がついていて、強い刺激臭があるのだ。ソイは薬草の葉をひとつかみずつ束ねて籠に入れ、結びながら心の中で計算した。今回はヌー夫人が籠全体を持って行き、十万ルピー以上を手に入れた。それは母親に食べ物を買うのに十分な額で、残りはク・ムンにコンデンスミルクを一缶買うのに十分な額だった。
ムンのことを思いながら、ソイは妹のトムのことを思い浮かべた。トムは今どこにいるのだろう?いつ子供たちの元に戻ってくるのだろう?ある日、村人たちがトムを町の喫茶店で見かけたという話を耳にした。金髪に染め、美しい服を着ていたという。ソイは信じられなかったが、心の底ではトムが田舎の厳しい生活に耐えられないだろうと分かっていた。幼い頃、二人の姉妹は薪集めに丘を登り、白い葦の森を眺めた。ソイは魅了され、枝を一本一本摘んで頭にかぶる花輪を作った。それを見たトムは思わず笑った。「本当に田舎娘だね!僕は、たとえ葦の花をもらっても、欲しくないよ。花もイナゴも、こんなに味気ないものだ!」
ソイが山を下り、ヌーおばさんの家の方へ向かった時、まだ午後の陽は沈んでいませんでした。おばさんはソイを見るとすぐに温かく迎え、財布を取り出してお金を数え、ソイに渡しました。ムンにバナナとビンロウの実をあげるのを忘れていませんでした。ソイが家に着くと、すでにあたりは暗くなっていました。おばさんの姿を見ると、ムンは抱っこしてもらうために両腕を上げました。おばさんの輝く瞳を見て、ソイは幼い頃のトムの姿を思い出しました。痩せていて、髪は首筋で束ねられていましたが、瞳はいつも不思議なほど輝いていました。
夜。家は静まり返っていた。ソイはク・ムンの安定した寝息と、葦を吹き抜ける風の音に耳を澄ませながら横たわっていた。ソイは眠りに落ちた。夢の中で、白い葦の茂みの真ん中に立っている自分の姿を見た。頭には葦の冠が精巧に編まれていて、一見すると王冠のようだった。「見て!お姫様みたいに可愛いわ!」と声がした。ソイは振り返ると、それはトムだった。トムはそこに立っていた。ソイから腕を伸ばした距離ほどしか離れていないのに、なぜか妹からとても遠く離れているように感じた。「トム!ムンのところに戻ってきて!ムンは毎晩、祖母に母親の話を聞かせてほしいと頼んでいた。『私のお母さんはソイおばさんみたいに綺麗?どうして私を置いて行ったの?戻ってきて、トム!』と彼女は尋ねた。彼女が言い終わる前に、トムの姿は白い葦の茂みの中に消えていた。鶏小屋の外では、雄鶏が三番目の夜更けに羽ばたき、鳴いていた。ソイは目を覚まし、外を見ました。まだ夜は深々としていました。反対側のベッドでは、おばあちゃんと孫娘がまだ抱き合ってぐっすり眠っていました。
夜明け、ソイは目を覚まし、急いで炊飯器を点火し、準備を整えた。髪を梳かし、おにぎりを袋に包み、ムンの服を着替えさせ、地区の市場で買った布製の帽子を丁寧に被せた。「孫をどこへ連れていくの?」母は薬草の葉を乾燥させる盆を取り出し、振り返って尋ねた。「私たち二人で町へ行って、彼女のお母さんのことを尋ねてきたの。トムをいつまでも放っておくわけにはいかないし、ムンをお母さんと離れさせるわけにもいかないわ。」外では、早朝の穏やかな風が木の葉を優しく揺らし、昨夜残った水滴が庭に落ちていた。丘の麓では、葦原が波のようにざわめき、雲の層のように白く輝いていた。突然、ソイが「ひとりで行って、ひとりで帰る」「ひとりで刺繍糸を紡ぐ」という歌を口ずさんだ。
霧の立ち込める朝の町への道。少女は軽快に自転車を漕ぎ、クー・ムンはハンドルにぶら下がった籐の椅子にきちんと座り、小さな頭を時折後ろに傾けて叔母に微笑みかけていた。数台の水牛車が風を切って通り過ぎ、埃と煙が立ち上る。正午過ぎ、叔母と甥は町の中心にある小さな喫茶店に立ち寄った。叔母は店主に、通りの向かいにある薄暗い喫茶店で働くトムについて尋ねた。「トム?金髪なの?あの店で働いてたんだけど、数ヶ月前に辞めたって聞いたんだけど、どこへ行ったのかしら」
彼女は店主に別れを告げ、ムンを拾い、バイクで走り続けた。トムは彼女が遠くまで行かないだろうという予感がしたので、しばらくぶらぶら歩き回り、尋ね回った後、市場の端に古着を売っている屋台を見つけた。一人の少女が、山積みになった服を掛けるのに忙しそうにしていた。長い黒髪をきちんとまとめ、その横顔は物憂げで物静かな様子だった。もしかして…「トム!」トムは、彼女の息が詰まり震える声に、そっと呼びかけた。
少女は振り返った。子供の頃と同じようにキラキラと輝く瞳は、今はどこか寂しげで、どこか迷い気味だった。クー・ムンがソイの腕の中にいることに気づき、彼女は驚いた。トムは立ち止まり、シャツを脱ぎ捨て、息子の元へ駆け寄った。「ママ!」―その呼びかけは小さかったが、トムを驚かせるには十分だった。クー・ムンは母親を恋しがる子供のように、母の腕の中に飛び込んだ。一瞬の衝撃の後、トムはしゃがみ込み、息子を抱きしめ、涙で濡れた顔をソイの髪に埋め込んだ。ソイは目をそらし、目尻の涙を拭った…
葦原からの風がそっと吹き、新土の香りを運んできた。隣のベッドでは、クー・ムンが祖母と母の間に横たわり、人生のあれこれと喋っていた。その日の午後、ソイがトムを家に連れて帰った時、幾多の心配と別れの後、母はもはやトムを責めることはなく、静かに毛布と枕を探しに行き、トムが二人の間に横たわれる暖かい場所を用意した。
夜。ソイはまた夢を見た。白い葦の茂みの真ん中に立っている自分の姿だった。ソイの手には、白い葦の花輪が月明かりにきらめいていた。ソイはトムを呼び、白い花輪を妹の頭に置いた。すると二人はおしゃべりを返した。下の畑は収穫の季節で、乾燥場は黄金色に輝いていた…
一人で行き、一人で帰る。一人で刺繍糸を紡ぐ……ソイは、幼い頃、母が妹と二人で寝かしつけるときによく歌っていた、馴染みのある歌を口ずさんだ。今夜も子守唄が響いた。二人で行き、二人で帰る。二人で刺繍糸を紡ぐ……夢か現実か分からず、ソイはトムのささやきを聞いた。「今から僕は母のところ、ムンのところへ帰る。君は結婚しなさい!結婚式の日に君の頭にかぶる白い葦の冠を編んであげるよ。」
短編小説:ヴー・ンゴック・ジャオ
出典: https://baocantho.com.vn/vong-lau-trang-a188425.html


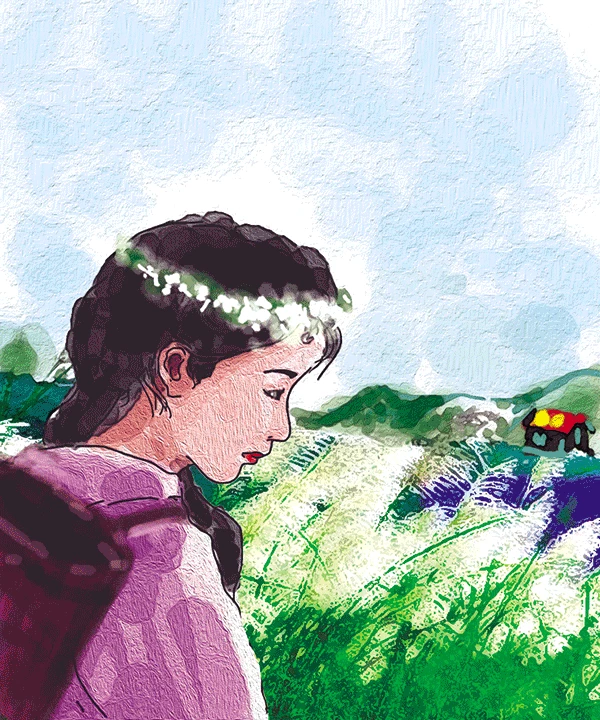



































































































コメント (0)