ホーチミン市医科薬科大学病院第3分院の専門医、グエン・トラン・ニュー・トゥイ医師は、多くの人が科学的な指示に従って食事制限、脂肪の減少、でんぷん質の摂取制限、そして様々な断食療法を行っているにもかかわらず、依然として体重が減らず、減少が遅く、さらには太りすぎや肥満になっていると述べています。なぜ、ほとんど食べない人やダイエットをしているのに体重が減らない人がいるのでしょうか?伝統医学の観点から見ると、太りすぎは食事だけでなく、脾臓、消化器、血液など、体内の深部にある要因にも関係しています。
脾臓が弱いと太りすぎの原因になる
伝統医学では、脾臓は体内の食物や水分の消化、輸送、代謝を司る主要な臓器とされています。脾臓が弱ると、食物の消化・代謝能力が低下します。そうなると、たとえ食事量を減らしても、体内の輸送・吸収がうまくいかなくなり、「痰湿」や余分な脂肪が蓄積してしまいます。
例えば、人は少量の食物しか食べないかもしれませんが、脾臓虚弱のため、食物からのエネルギーは十分に代謝されず、蓄積につながり、過体重や肥満を引き起こします。
痰湿症候群
痰湿は、気血の代謝に異常があり、余分なものが体外に排出されずに体内に滞留することで起こります。脾虚により気血が滞ると、体は脂肪、水分、余分な痰などの老廃物を代謝できず、これらの物質が体内に蓄積し、特に腹部、太もも、腕などに蓄積し、あまり食べていないにもかかわらず、余分な脂肪を形成します。
「例えば、痰湿のある人は体が重く感じやすく、あまり食べなくても余分な脂肪が蓄積しやすくなります。血と気の流れが滞るため、余分な物質を運び、排出するプロセスが遅くなり、たとえ食事量を減らしても、体重がなかなか減らないか、ほとんど減らないのです」とトゥイ医師は述べています。

血液循環が阻害されると、余分な物質の運搬と排出のプロセスが減少するため、食べる量を減らしても体重を減らすのは困難、またはほとんど減りません。
血液の停滞
伝統医学では、気血は精気を運び、身体を養い、機能を維持する役割を担っています。気血の循環が滞ると、代謝や排泄機能が低下し、余分な物質、特に脂肪が蓄積しやすくなります。体の各部位の活動が鈍くなり、少量の食物を摂取してもカロリーや余分な脂肪を燃焼できなくなります。
例えば、運動不足、ストレス、不健康な生活習慣などにより血と気の滞りがある人は、食事量が少ないにもかかわらず肥満になりやすいです。食事を多く摂っていないにもかかわらず、体は食べ物を効率的にエネルギーに変換できず、余分な脂肪が蓄積されてしまいます。
心理的および感情的な要因
伝統医学によれば、感情的、心理的、そして精神的な健康要因は、過体重や肥満の原因として非常に重要な役割を果たします。ストレス、不安、あるいは長期にわたるストレスは、内臓の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、過度の心配は脾臓に、過度の思考は肺に、過度のイライラは肝臓に、過度の恐怖は腎臓に悪影響を及ぼします。
「これらの障害はすべて、体内の栄養素の輸送プロセスに影響を与え、食物の代謝能力を低下させ、血液とエネルギーの停滞を引き起こします。この状態になると、あまり食べなくても体に余分な脂肪が蓄積される可能性があります」とトゥイ医師は述べています。
一般的に、ストレスを感じている人や長期にわたるストレスにさらされている人は、食欲が減退したり、食べる量が減っても内分泌系の障害や体内のバランスの乱れにより過体重や肥満になりやすく、余分な脂肪が蓄積し、減量が困難になります。つまり、食べる量が減っても過体重や肥満のままであるという事実は、単に食事だけが原因ではなく、体内の様々な要因から生じている可能性があります。
伝統医学では、内臓のバランスの乱れ、血行不良、体温不足、心理的要因などにより、体に余分な脂肪が蓄積されると説明されています。したがって、過体重や肥満の問題を解決するには、根本的な原因を理解し、食事、運動、精神管理を適切に調整する必要があります。
「食事量を減らしても体重が減らない場合は、健康全般についてさらに詳しく相談する必要があるかもしれません。伝統的な医療によるサポートは、体調の改善に効果的に役立ちます」とトゥイ医師は語りました。
[広告2]
出典: https://thanhnien.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-an-it-van-thhua-can-185250205151840216.htm


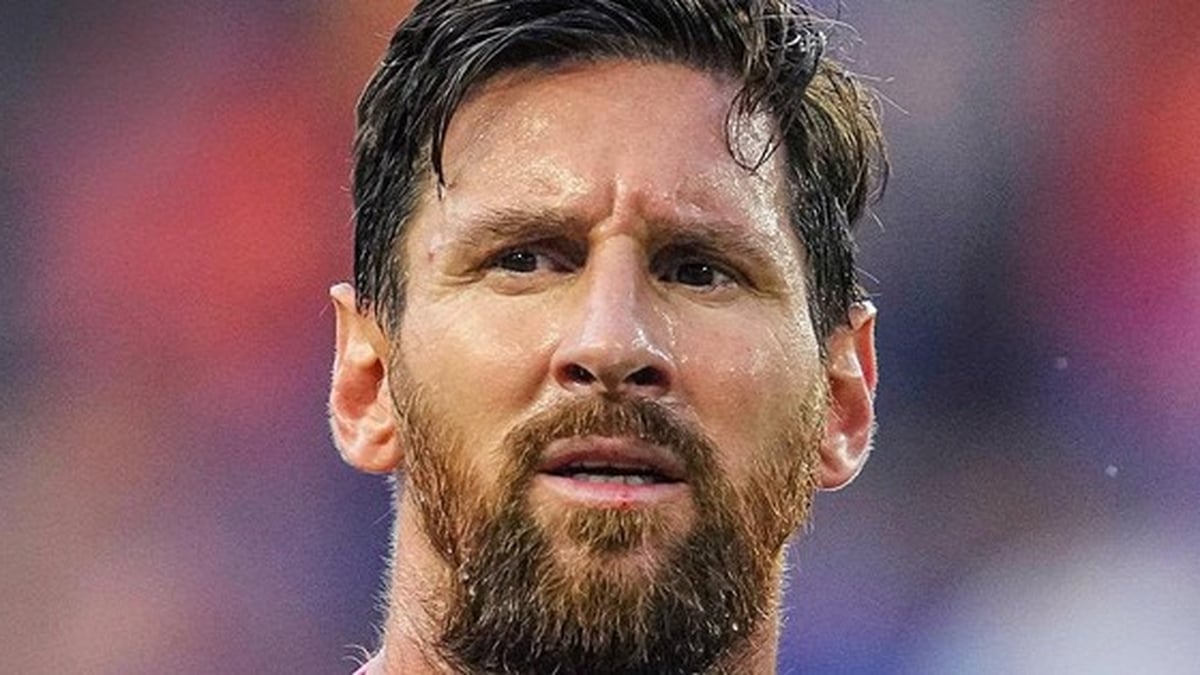


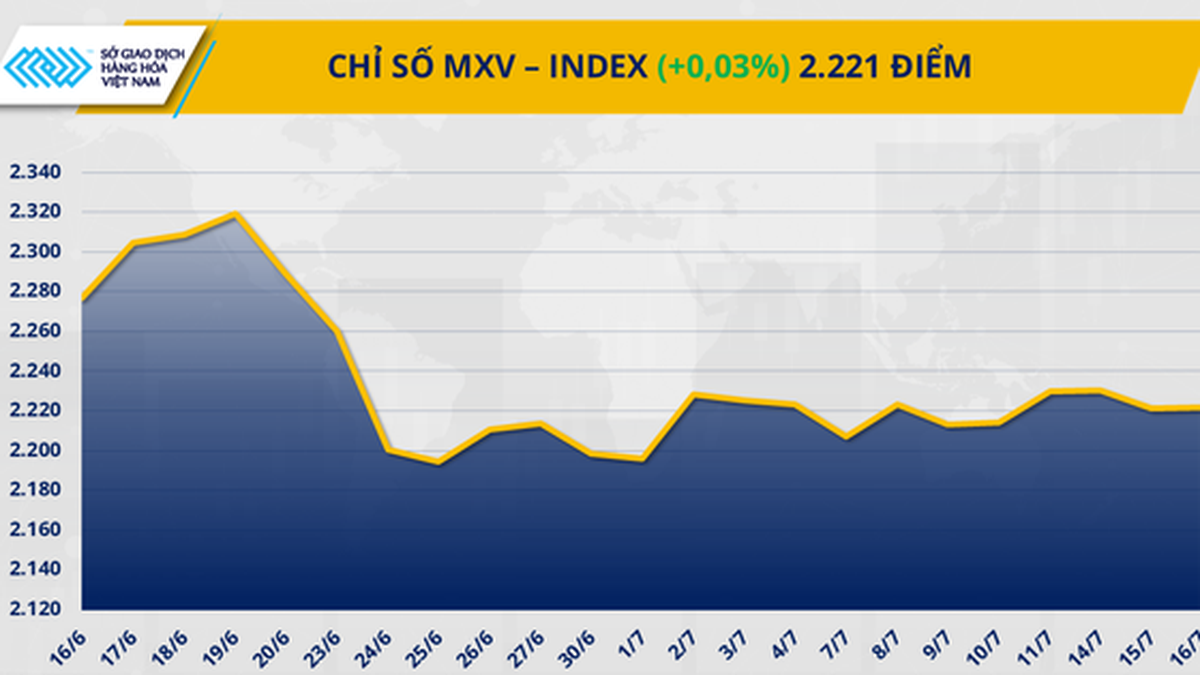




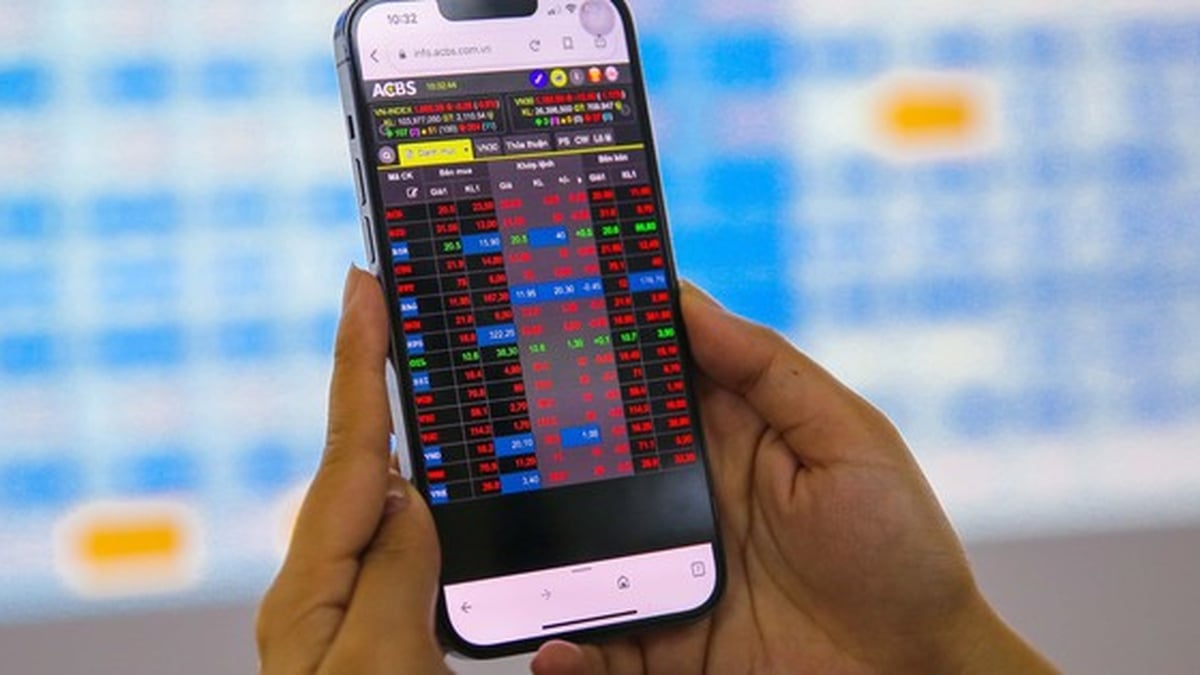









































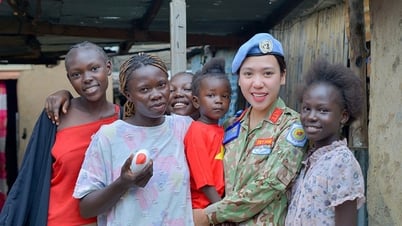
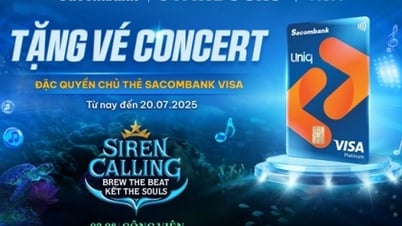







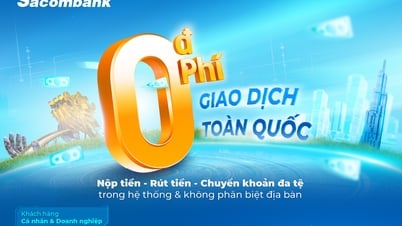









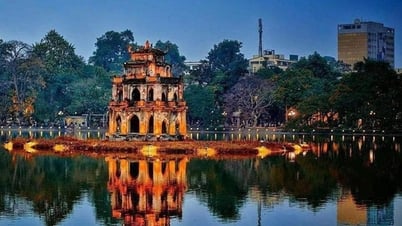










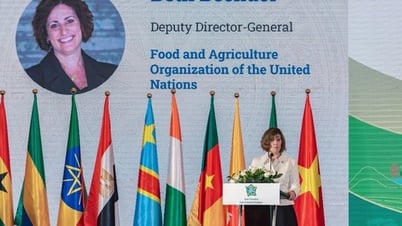















コメント (0)