世界の食料市場は再び混乱に陥っている。ロシアが黒海穀物取引から撤退を決定しただけでなく、インドが多くの種類の米の輸出を禁止すると発表したことも原因だ。
世界最大の米貿易業者であるインドが、輸出の約40%を占める米の部分的な輸出禁止措置を発動したことで、食料インフレが制御不能に陥るのではないかという懸念が生じている。特に、既に高い債務水準と食料・燃料費の高騰に苦しむ南半球諸国においては、懸念が高まっている。たとえ早期に解除されたとしても、この輸出禁止措置はインドにとって経済的にも 地政学的にも重大な決断となる。インドは発展途上国における自然体で責任あるリーダーであるという、インド指導者たちの最近の主張は、この措置によって著しく損なわれることになる。
 |
インド政府の決定の根拠は、来年に迫った総選挙を前に、国内の食料価格が高騰していることである。インドでは伝統的に、食料インフレ率の低さが選挙の勝敗を左右する重要な要素であり、国内の米価格は過去1年間で10%以上上昇している。
インドの経済学者のほとんどが理解していないのは、政府が、貧しいインド国民に簡単に分配したり、価格を下げるために市場に放出したりできる大量の米を備蓄しているのに、なぜ輸出禁止が国内消費者にとって最善の答えなのかということだ。
実際、インド政府当局者にとって、輸出禁止は国内価格の上昇に対する最後の対応ではなく、最初の対応となった。例えば、昨年ロシアがウクライナの小麦市場を掌握してからわずか数ヶ月後、インドは再び小麦輸出を停止し、新興国が最も脆弱な時期に、その食料不安を悪化させた。
インドは、世界貿易機関(WTO)においてさえ、自国の制限的な貿易政策は何百万人もの自給農家を保護するためだとしばしば主張している。しかし実際には、農業所得が政府の最優先事項であるならば、価格が上昇し農家が稀に見る利益を上げている時に輸出を停止することはなかっただろう。インドが世界でリーダーシップを発揮したいのであれば、自国の決定が世界的な影響を及ぼすことを理解しなければならない。米国のようなより豊かな国でさえ、消費者――多くはインド系移民――がスーパーマーケットに殺到し、インド産米を買いだめしている。
インドの政策立案者たちは、こうした批判に対して即座に弁明する。彼らは、この禁止措置はインドで最も人気のある米であるバスマティ米には適用されないと主張するだろう。しかし、これは海外在住のインド人、特に短粒種の米を好む南インド出身者にとって、ほとんど慰めにはならないだろう。
政府は、昨年発表された輸出禁止措置にもかかわらず、インドは2022年夏の小麦輸出量が前年比でほぼ2倍になったと指摘している。これはシステムの不備によるものではなく、禁止措置前に締結された契約が履行されたことが一因である。しかし、他国政府がインドに対し、特定の小麦輸出について例外を認めるよう働きかけることができたことも一因である。米についても同様の制度が導入される予定である。
インドの決定は報復を招く可能性が高い。実際、世界の米価格が10年ぶりの高値に達した場合、反発は急速にエスカレートする可能性がある。そして世界は、米不足の原因を主にインドの禁輸措置に求めている。
[広告2]
ソースリンク

















































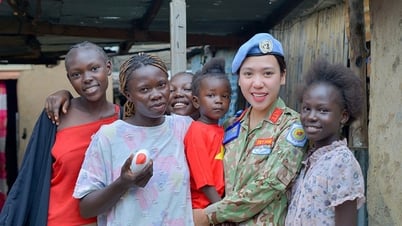









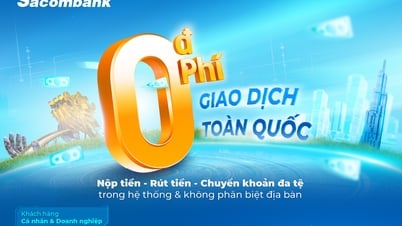
























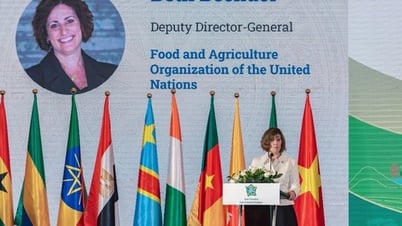















コメント (0)