 |
| ベトナム企業はFTA関税優遇措置の恩恵を受けている。(出典:Vietnamnet) |
税制優遇措置の恩恵を受ける
商工省の統計によると、2022年に自由貿易協定(FTA)を締結した市場に輸出された約800億米ドル相当の商品が関税優遇措置を受けており、これは前年より13%増加した数字だ。
ベトナムとFTAを締結している市場は60カ国以上あり、これらはベトナムの主要な輸出先であり、同国の輸出額の約3分の2を占めています。2022年には、ベトナムの輸出総額は3,715億米ドルを超え、そのうちFTA市場への輸出額は2,330億米ドルに達しました。
FTAに参加することの大きな意義は、有利な貿易条件を備えた大規模な輸出市場圏が創出されるだけでなく、ベトナムの産業も関税優遇措置の恩恵を受けられることです。
FTAに基づく特恵原産地証明書(C/O)を利用した総輸出額は783億米ドルに達し、FTA市場へのベトナムの総輸出額約2,330億米ドルの33.61%を占めた。
ベトナムは15のFTAを実施しており、輸出企業が関税優遇措置を享受できる多くの機会が開かれている。
これらのうち、中国、韓国、ASEAN市場は、FTAインセンティブの利用率が高く、ベトナムからの商品輸入において継続的にトップの市場となっています。
中国向けベトナム製品への特恵関税受領証(C/O)発行額が170億米ドルを超え、第1位となった。次いで、ASEAN諸国向け製品へのD型C/O発行額が133億4000万米ドルとなった。
3位と4位はそれぞれ124億ドルの韓国と121億ドルの欧州連合(EU)です。
韓国へのFTA特恵利用率が最も高い輸出品目は水産物(93.99%)で、農産物(野菜、コーヒー、胡椒)もC/O特恵利用率がそれぞれ92.26%、97.98%、ほぼ100%と非常に高い。木材および木材製品(76.15%)、履物(100%)、繊維(97.99%)も特恵利用率が最も高い。
ビジネスには依然として障害がある
先日開催されたワークショップ「FTA実施におけるベトナムの特恵輸出税および特別特恵輸入税の約束の効果的な実施」において、 ベトナム商工連合会(VCCI)WTO統合センター所長のグエン・ティ・トゥ・トラン氏は、輸入品の特恵関税利用率が輸出品よりはるかに低く、非常に残念であると述べた。
実践的な観点から、2022年にWTO統合センターはベトナム・EU FTA(EVFTA)のインセンティブの活用に関する調査を実施しました。
トラン氏は、「EVFTAの実施から2年が経ち、企業が得た最大のメリットについて尋ねたところ、関税優遇措置が最大のメリットであると回答しました。輸出優遇措置は輸入優遇措置よりも大きなメリットをもたらします。多くの企業は、FTAが生産活動や事業活動にプラスの影響を与え、交渉における困難を軽減し、ベトナムにとって有利に働くと評価しています。」と述べました。
関税優遇措置を活用していない企業があることについて、WTO統合センター長は、EVFTAに規定されている関税優遇措置について知らない企業もあると述べた。
トラン氏によると、FTAにおける関税優遇措置を利用するには、市場の変動、不利なビジネス環境、利益を享受するために原産地規則を満たすことの難しさ、約束に関する具体的な情報の不足、一部のFTA約束が企業に不利であること、企業の競争力が限られていることなど、多くの障害がある。
グエン・ティ・トゥ・トラン氏は、「内部からの抵抗があれば、企業は自ら変わらなければならない。また、抵抗は約束の実施と実行のプロセスから生じるため、企業は声を上げて実施機関が調整できるようにする必要がある」と強調した。
今後、FTAの特恵関税コミットメントを活用するためには、企業はFTAのコミットメントを注意深く研究する必要があるとトラン氏は述べた。企業がどの市場に製品を輸出する場合でも、ベトナムがその市場と締結した協定を研究し、これらの協定の特恵関税コミットメントについて理解する必要がある。
例えば、日本市場の場合、ベトナムは現在日本と4つのFTAを締結しており、企業は一般関税率表(MFN)だけでなく4つの異なる関税率表についても学び、どの関税率表がより有利かを見極める必要があります。
同時に、各協定の優遇措置は原産地規則と関連しているため、企業は原産地規則を満たすことで当該協定の優遇措置を享受するためには、どの協定の原産地規則を満たすことができるかを検討する必要があります。また、FTAの規定に従って他の優遇措置を享受するためには、他の条件を遵守することも必要です。
国際協力局( 財務省)多国間金融統合部長のグエン・フオン・リン氏によると、企業は、かなり長期にわたるスケジュールで発令される税制令の状況において、コミットメントとその影響について積極的に学び、適切な行動を準備する必要があるという。
また、競争力の向上、企業がFTA統合の機会を活用できる基盤づくり、同時に企業間の協力・連携の強化も必要である。
[広告2]
ソース

























![[写真] ザーライ省の指導者らが中央高地の少数民族とともにホーおじさんの記念碑に花を捧げる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)






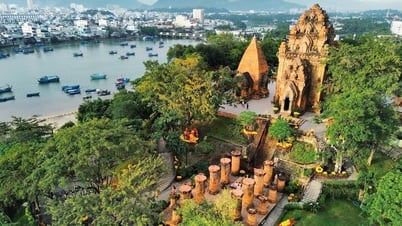







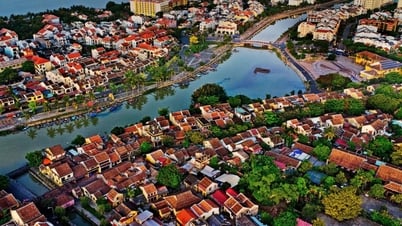




























































コメント (0)