感染面積は昨年の冬春作物より何倍も広い。
2023~2024年冬春作では、省全体で3万9000ヘクタール以上の稲作が行われる予定です。現在、早春作は開花~緑肥期、晩春作は穂分化~穂抱合期にあります。省全体では、稲の生育は概ね順調です。しかし、圃場における害虫発生状況の調査結果から、一部の害虫が発生しており、水田に広範囲にわたる被害をもたらす可能性があることが示されています。被害の規模とレベルは、2022~2023年冬春作よりも高くなっています。
具体的には、4月16日時点での害虫被害面積は6,700ヘクタールを超え(2022~2023年冬春作物の約7倍)、そのうち重度の被害面積は664.5ヘクタール(2022~2023年冬春作物の何倍にも相当)、防除済み面積は3,800.5ヘクタールです。主な害虫は、コブトエビ、ウンカ、ネズミ、イネいもち病です。
同省農作物生産・植物保護局技術部長のグエン・ティ・ニュン技師は次のように付け加えた。「今年の冬春作物では、圃場におけるツチグモの密度が劇的に増加し、キムソン、イエンモ、イエンカンなどの一部地域では、密度が1平方メートルあたり数百匹に達しました。現在までに、省全体でツチグモに感染した総面積は6千ヘクタールを超え、重度の感染地域は650ヘクタールに達しています(2023年の同時期には感染地域はありませんでした)。これまで多くの地域で農薬散布が行われてきましたが、現地調査によると、ツチグモの感染面積は依然として増加しています。」
「今後、第二世代のコガネムシが出現し、キムソン県、イエンモー県、イエンカン県、ホアルー県、タムディエップ市の穂分化期から穂包化期にかけての晩春の田んぼに広範囲にわたる被害をもたらすでしょう。コガネムシの密度は通常50~70匹/平方メートルですが、高地では100~150匹/平方メートルに達し、場合によっては300匹/平方メートルを超えることもあります。早期発見と駆除が行われなければ、深刻な被害を受けた地域では穂の葉が白くなり、稲の収穫量に甚大な影響を与えるでしょう」と、グエン・ティ・ニュン技師は警告しました。
専門分野の調査によると、今後、コブウンカに加え、第二世代のイネウンカも大量発生し、特に穂分化期から穂抱合期にある晩春の田んぼに広範囲にわたる被害をもたらすと予測されています。発生密度は平地で400~500頭/m²ですが、高地では1,000~2,000頭/m²、巣は3,000頭/m²を超えます(キムソン、イエンモ、イエンカン、ホアルー地区など)。被害規模とレベルは、2022~2023年冬春作の同作よりも高くなっています。早期発見・駆除が遅れると、晩春の田んぼでは田んぼが赤く染まり、緑肥期から実り期にある早春の田んぼでは巣が焼けてしまいます。さらに、ウンカは田んぼで黒条萎縮病を媒介するウイルスも運びます。
さらに、葉いもち病が散発的に発生し、窒素肥料過剰の緑稲地帯で局地的な被害を引き起こしています。感受性品種には、TBR 225、BC 15、Nep、LT2、Bac Thom No. 7、Dai Thom 8などがあります。頸いもち病は、乳熟期から緑葉期の早春茶に局地的な被害を引き起こしており、主にNho Quan地区で、花の20~30%に高い罹病率を示しています。褐色斑点病の感染面積も、2023年の同時期の1.7倍に増加しています。また、一部の地域では、ナミハダニ、銀葉枯病、条斑細菌病、雑草イネ、黒穂病、ハダニなどの被害も発生しています。
4月30日から5月1日までの休暇シーズンに予防のための散布ピークに重点を置く
4月下旬、私たちはイエンモー県イエンラムコミューンのナムイエン協同組合を訪問しました。稲の害虫や病気の複雑な状況に直面し、協同組合のサービスチームのメンバーと省作物生産・植物保護局の職員は、圃場の点検、田んぼの明確な分類、密度の評価、害虫の年齢判定に注力し、閾値に達した際に迅速かつ適切な防除措置を講じています。

ナムイエン協同組合のヴー・ヴァン・ハン理事長は、「4月初旬、第一世代のツトガが出現した際、協同組合は散布を指示しました。しかし、現在までの現地調査で、第二世代のツトガが依然として高い密度で発生していることがわかりました。さらに、一部の圃場ではイネいもち病やウンカも発生しています。第二世代のツトガとその幼虫は4月28日から5月2日にかけて発生すると予想されており、この時期が散布に最も効果的な時期です。そのため、すべての農家が適切な散布方法を把握し、積極的に効果的な散布を行うよう、町内の拡声器によるアナウンスを強化しています。また、協同組合は、住民への供給とサービス提供に必要な量の植物保護薬剤も準備しています。」と述べました。
同省作物生産・植物保護局技術部長のグエン・ティ・ニュン氏は次のように強調した。「稲の生殖期、つまり穂立ちと穂形成期の今のような時期に、農家は絶対に油断したり、油断したりしてはならない。分げつ期と異なり、害虫の密度は10~30匹にもなるが、稲はまだそれを補う能力を持っている。しかし、穂形成期に入ると、稲はこの能力を失ってしまう。農家は、穂の葉が穀物収量に重要な役割を果たすことを覚えておく必要がある。なぜなら、穀粒に蓄えられている物質の約60%は、開花後の稲の葉による直接的な光合成産物だからである。したがって、穂の葉を適切に管理し、保護する必要がある。」
農作物生産・植物保護局は、散布時期について、「コガネムシの幼虫は4月28日から5月11日に開花すると予想されるため、最適な防除時期は4月30日と5月1日の連休と重なる」と発表しました。専門家はまた、農家は田んぼを明確に区別し、適時に防除するために天候と害虫の動向を注意深く監視し、天敵を保護し環境を保護するために無差別に農薬を散布しない必要があると指摘しました。さらに、コストと散布作業を節約するために、コガネムシ、イネいもち病、ウンカ類の同時散布を組み合わせることが可能です。ただし、適切な種類の農薬を選択し、指示に従って適切な濃度で混合することが重要です。昆虫密度が200匹/平方メートルを超える高密度の田んぼには、1回目の5~7日後に2回散布する必要があります。
省農作物生産・植物保護局による冬春稲の害虫防除に関する指示 *ヒメツチハンミョウの場合:2齢幼虫が孵化した時点で、20匹/m²以上の密度で圃場に散布してください。散布時期は5月1日から5月12日までで、以下の専用殺虫剤のいずれかを使用してください:Clever 150SC、300WG、Incipio® 200 SC、Director 70EC、Virtako 40WG、Voliam Targo 063SC、Silsau super 3.5 EC、Dylan 10WG… 200匹/m²以上の密度で圃場に散布する場合は、2回散布してください。2回目は1回目の5~7日後に行ってください。 * トビイロウンカおよびセジロウンカの場合:散布時期は4月27日から5月8日までです。具体的には: - 穂分化段階 - 穂包囲:2 齢幼虫の数が多いときに、密度 2,000 匹/m2 以上の圃場で、浸透性殺虫剤のいずれかを散布します(例:Penalty 40WP、Chess 50WG、Titan 600WG、Applaud-Bas 27 WP、Palano 600WP、Sutin 5 EC、50WP...)。 - 緑赤尾期:2齢幼虫が満開のときに、密度が1,000匹/m2以上の圃場に、Nibas 50EC、Bassa 50EC、Vibasa 50ECなどの接触型殺虫剤のいずれかを使用して散布します。接触型殺虫剤を使用する場合は、散布した殺虫剤が幼虫に直接接触するように列を分離する必要があり、収穫前に検疫期間を確保できる殺虫剤を選択する必要があります。 * 穂いもち病対策:葉いもち病に感染した圃場、新圃場、病原体近傍、感受性品種において、イネの開花率に応じて散布します。予防時期は、イネが開花開始から3~5%早い時期に、以下の薬剤のいずれかを使用します:カソト200SC、バンプ650WP、カタナ20SC、カビム30WP、フィリア®525SE、ビーム®75WP、バミー75WPなど。 * 2点イネノメイガの場合:卵密度が0.3巣/m2以上の圃場に、ニョークアン郡およびジアビエン郡では5月15日以降、イエンモ郡、イエンカイン郡、キムソン郡、ホアルー郡、タムディエップ市、 ニンビン市では5月25日以降に、以下のいずれかの特定殺虫剤を散布します:Prevathon® 5SC、Virtako® 40WG、Voliam Targo® 063SC、… * 有害なネズミに対しては、掘る、捕獲する、燻製にする、罠を仕掛けるなどの手作業による対策に重点を置き、ネズミの駆除を継続します。これらは、畑でのネズミによる被害を抑えるのに非常に効果的な対策です。 さらに、褐斑病や籾腐病の予防には散布を併用し、雑草が生えた稲は根こそぎ除去します。(注:具体的な状況に応じて、地域はどの害虫が主な害虫であるかを特定し、タイムリーかつ効果的な防除措置を講じる必要があります。上記の害虫を予防するために散布を併用することも可能ですが、十分な薬剤量を確保する必要があります。混合薬剤の量は1升あたり25~30リットルです。) |
文と写真:グエン・ルー
ソース




































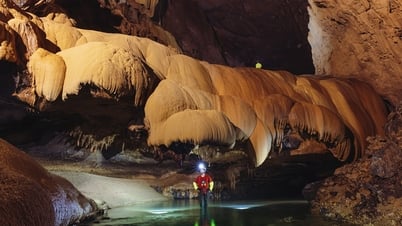

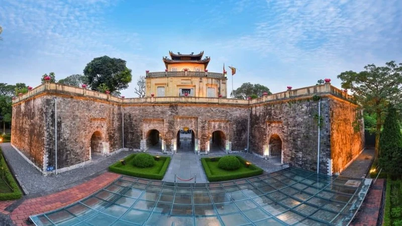




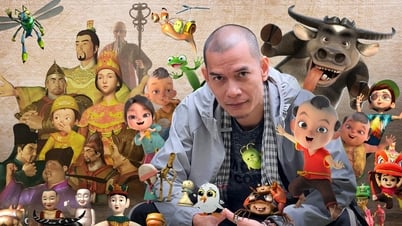










































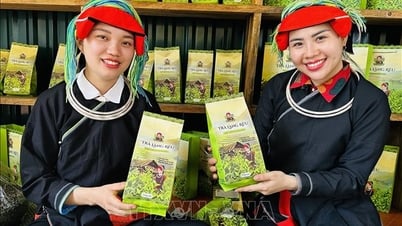












コメント (0)