大阪大学の谷内進一教授らは、特殊な胃カメラを使って膵臓がんを早期に発見する検査を開発した。
膵臓分泌物中の DNA を分析して、ほとんどの膵臓がんに見られる遺伝子変異の有無を確認します。
この検査を胃がん検診と同時に行えば、膵臓がんの早期発見が容易になります。
東京のVNA記者によると、上記の研究で研究者らは、膵臓がんのほとんどが膵液が通る膵管の一部から発生することを発見したという。
その事実に基づいて、彼らは膵液を分析する検査方法を開発しました。
まず、膵液を刺激する薬剤を投与し、がん細胞のDNAが膵液中に放出されやすくします。次に、特殊な胃カメラを用いて十二指腸の膵液出口付近から膵液を採取します。
検体中のDNAを検査し、KRAS遺伝子の変異レベルを調べます。変異数が多い検体は膵臓がんと診断されます。
試験は日本で健康な人75人と早期膵臓がん患者89人を対象に実施された。
結果によると、膵臓がん患者は約81%の精度で診断されました。また、健康な症例でも、がんは検出されませんでした。
地域の医療機関で定期的に行われる胃がん検診では、専門医がカメラを使って胃だけでなく十二指腸も観察することが多い。
この新しい検査は、従来の内視鏡に別の医療機器を取り付けることで実施でき、所要時間はわずか1~2分程度です。
研究チームは、胃がん検査に加えて膵臓がんリスクの早期検査を加えることで、医療負担と患者の健康への影響を軽減できると考えている。
しかし、この検査は膵臓がんの家族歴がある人など、膵臓がんのリスクが高い人にのみ実施すべきだとも推奨している。
日本では、毎年約4万4千人が膵臓がんと診断され、そのうち約4万人がこの病気で亡くなっています。
これは治療が最も難しい癌の一つであり、診断後5年生存率はわずか10%程度です。そのため、早期発見・早期手術には高度な技術が不可欠です。
膵臓がんの約94%には、がんの存在を示すマーカーとして機能するKRAS遺伝子の変異が見られます。
体液中の遺伝子変異を検出する方法は研究されているが、血液などの検査サンプルでの早期検出は依然として難しい。
新たな研究結果は、膵臓がんによる死亡を予防したり減らしたりするための新たな前向きな方向性を開いた。
この大阪大学、鳥取大学、香川大学などの共同研究が、アメリカの医学雑誌「Annals of Surgery」に掲載されました。









































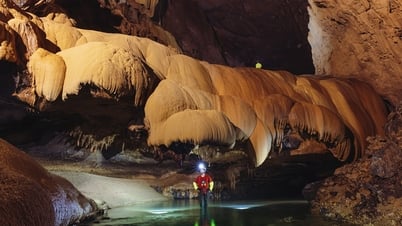





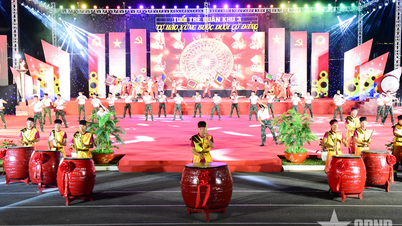



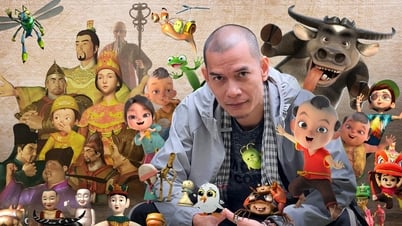
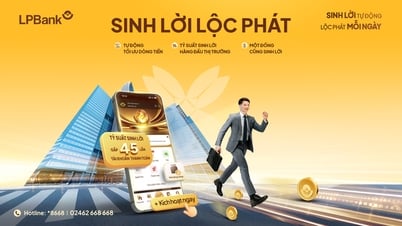


















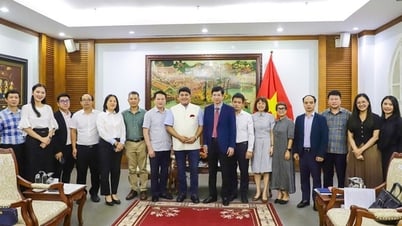



















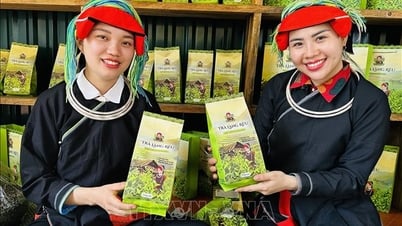










コメント (0)