仏手実は祭壇用だけではなく、健康にも多くの効能があります。
仏手果の概要
グエン・ドゥック・クアン博士が健康・生活新聞に掲載した記事によると、仏手果は仏手果、仏手オレンジ、仏手スライスとも呼ばれています。学名:Citrus medica L. var. sarcodactylis (Noot.) Swingle.、ミカン科。[= C.medica L.var digitata Riss.]
仏手(ブッダ)の実は、プク・トー・カムとも呼ばれ、幸運の象徴として神聖な意味を持ちます。仏手は美しい形、鮮やかな色、そして長く続く香りを特徴とし、多くの家庭の祭壇に欠かせない果物です。テト(旧正月)には五果の中央に置かれることが多いです。崇拝の対象であるだけでなく、仏手には多くの薬効があります。
仏手毬の薬効成分は、乾燥した果実(そのまま、または蒸して3~4mmの厚さにスライスし、日陰で乾燥させたもの)です。根は秋に収穫され、葉は一年中収穫されます。仏手毬の果実には、精油とフラボノイド(ステロリン、リメチン、シトロテン、ダイムリメチンなど)が含まれています。仏手毬の精油には、抗菌作用、抗真菌作用、消化促進作用があります。

仏手の実は健康に良い。
東洋医学によると、仏手は辛味、酸味、苦味があり、温性で、肝臓、胃、肺に入り、気を調え、痰を消し、肝臓を弛緩させ、胃の調子を整え、痛みを和らげる作用があります。肋間部や心窩部の痛み、吐き気、嘔吐、咳、痰を伴う気管支喘息、呼吸困難などを治療します。
仏陀の手による咳止め薬
仏手果には多くの健康効果があり、中でも最も顕著なのは咳止め効果です。ベトナムネット紙は、伝統医学の施術師であるヴー・クオック・チュン氏( ハノイ東洋医学協会)の言葉を引用し、現代医学によると、仏手果にはビタミンC、配糖体、糖、有機酸が豊富に含まれており、鎮痛、解毒、胃の栄養補給、痰の溶出、咳や喘息の緩和に効果があると述べています。
咳止めや痰の排出に仏手を使う方法は様々です。シロップ状にしたり、スライスした仏手を氷砂糖に浸して蒸し、冷蔵庫で保存したりすることもできます。呼吸器感染症による咳で、呼吸困難や発熱がない場合は、仏手を使うのが効果的です。1日2~3回、小さじ1~2杯を目安に服用すると、咳の症状が軽減されます。
子供が肺炎や気管支炎で咳をしている場合は、仏様の助けを待たずに医者に連れて行く必要があります。
仏手果は、生の仏手果30g(乾燥仏手果10g)を水で煮て飲むことで、酔いを覚ます効果もあります。風邪による腹痛には、乾燥仏手果15gと炒り米30gを茶のように煮出して1日3回飲むか、お粥にして食べます。
咳止めとして、仏手果の健康効果について上記にまとめました。この情報がお役に立てば幸いです。
[広告2]
ソース




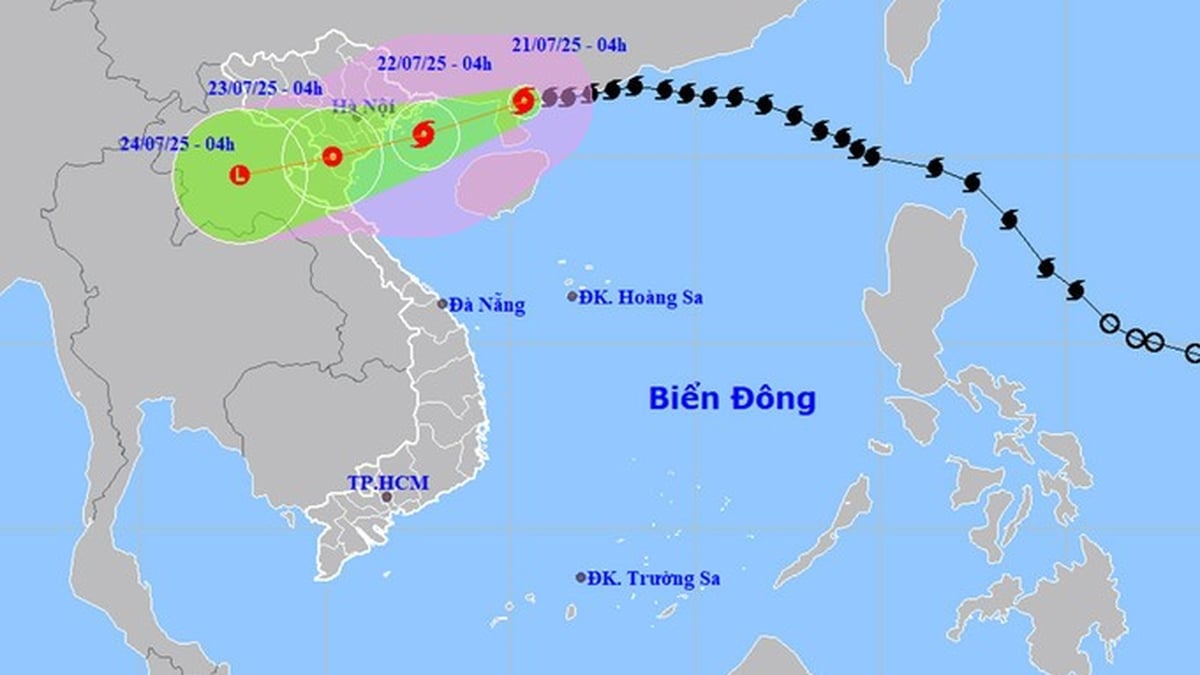



























































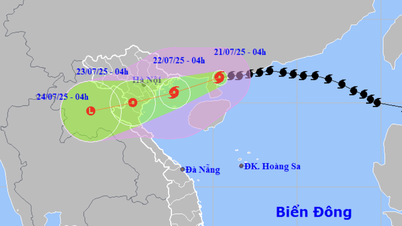































コメント (0)