財務省は提出書類の中で、現行の個人所得税法(PIT法)は2007年に公布され、国家予算収入の管理に多くの重要な貢献を果たしてきたと述べた。しかしながら、実際には同法には一定の限界があり、現在の社会経済発展の状況やベトナムが署名した国際公約に適合しなくなっている。そのため、財務省は個人所得税法(代替)の草案を作成することを提案した。
特に、財政省は、近年の社会経済発展の状況と発展の動向を踏まえ、個人納税者と扶養家族に対する家族控除に関する規定を検討・調整することを提案しました。同時に、納税者の税負担軽減に貢献し、所得再分配政策の実現における個人所得税政策の役割を引き続き推進していくことになります。

財務省は、個人所得税法(代替)の草案作成を提案している。(イラスト写真)
財務省は、個人所得税法(2009年1月1日発効)において、納税者控除額は月額400万ドン(年間4,800万ドン)と規定されており、扶養家族1人当たりの控除額は月額160万ドンとされていると述べた。個人所得税法の一部条項を改正・補足する法律(2013年7月1日発効)では、納税者控除額は月額900万ドン(年間1億800万ドン)と規定されており、扶養家族1人当たりの控除額は月額360万ドンとされている。
2020年6月2日、国会常任委員会は個人所得税の家族控除額の調整に関する決議を公布しました(2020年度から適用)。これにより、納税者の控除額は月額1,100万ドン(年間1億3,200万ドン)に引き上げられ、扶養家族1人あたりの控除額は月額440万ドンとなります。個人所得税の家族控除額の引き上げは納税者の負担軽減に寄与し、現在個人所得税を納税しているすべての納税者の納税額が減額されます。
現在、納税者本人に対する控除額は月額1,100万VND、扶養家族1人当たりの控除額は月額440万VNDであるため、社会保険料、健康保険、失業保険料などを差し引いた後の給与所得が月額1,700万VND(扶養家族が1人の場合)または月額2,200万VND(扶養家族が2人の場合)の人は、個人所得税を支払う必要がありません。
計画投資省統計総局の2023年人口生活水準調査報告書によると、2023年のベトナムの一人当たり平均月収(現行価格)は496万ドンで、最高所得層(人口の上位20%を占めるグループ5)の平均月収は1,086万ドンです。したがって、現在の納税者控除額(月額1,100万ドン)は、一人当たり平均所得(他国で一般的に適用されている水準をはるかに上回る)の2.21倍以上であり、これは人口の上位20%の平均所得に相当します。
財務省は、最近、家族控除の水準がまだ低いという意見があるが、現在の家族控除の水準は、現代の人々の一般的な生活水準や収入水準と比較すると低くないとの意見もあるとし、現在多くの勤労者はまだ税金を払わなければならない水準の収入には達していないとしている。
さらに、地域最低賃金水準に応じて家族控除額を規制する必要があるという意見もあるし、都市部や大都市の家族控除額はコストが高いため農村部や山間部よりも高く設定する必要があるという意見もある。また、大都市への移民や移住を制限するために、都市部や大都市の個人に対する税率を高く設定する必要があるという意見もある。
本質的には、税額控除に関する規定は、個人が食費、宿泊費、交通費、学費、医療費など、生活の基本的なニーズを満たすために一定の所得水準を有していなければならないという原則を保証するものです。したがって、この基準額を超える所得のみが課税対象となります。また、控除の適用は、低所得者を個人所得税の課税対象から除外することを目的としています。個人所得税法の規定に基づく納税者および納税者の扶養家族に対する家族控除の水準は、所得の高低や消費ニーズの差異にかかわらず、社会全体の水準に応じて定められた水準となります。
我が国では、現行の家族控除額は2020年から適用されているため、新たな状況に適した改正や補足策を提案するために、見直しと再評価を行う必要があります。具体的な家族控除額については、物価変動や近年の生活水準の向上、そして今後の予測と整合を図りつつ、税制における個人所得税政策の役割を縮小しないよう、慎重に検討・算定する必要があります。
控除額が「高すぎる」場合、個人所得税政策が持つ機能(社会的公平性の確保と所得調整)の遂行における役割が曖昧になり、個人所得税政策は前期のような「高所得者優遇税制」へと無意識のうちに逆戻りしてしまうことになる。同時に、各時期における国の社会経済発展の実態と要件に合わせて柔軟かつ積極的に調整できるよう、家族控除額の規制を政府に委ねる選択肢を検討することも可能である」と財務省は強調した。
財務省が提案したもう一つの注目すべき改革は、個人所得税の税率表における税率の数を減らすことです。個人所得税法第22条第2項は、給与所得に適用される累進税率を5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%の7段階に規定しています。
財政部は「実際の実施過程を通じて、現行の累進課税制度は、段階が多すぎる上に段階間の格差が狭すぎるため、年末の所得集計時に税額が急上昇し、納税額が増加したり、追加納税額は多くないのに税務処理の回数が不必要に増えたりしやすく、不合理だという見方が出ている」と発表した。
最近、一部の国では、税制の簡素化のため、税目表の税率区分の数を削減する傾向が見られます。ベトナムは、現行の税目表における税率区分の数を7段階から適切な段階に削減することを検討すべきです。同時に、税目間の所得格差を拡大し、高税率所得者層への規制を強化することも検討すべきです。この方向性で実施することで、税目の簡素化と税率区分数の削減が促進され、納税者の申告と納税の円滑化につながります。
[広告2]
出典: https://vtcnews.vn/de-xuat-sua-luat-thue-tncn-nang-muc-giam-tru-gia-canh-giam-so-bac-bieu-thue-ar909491.html














































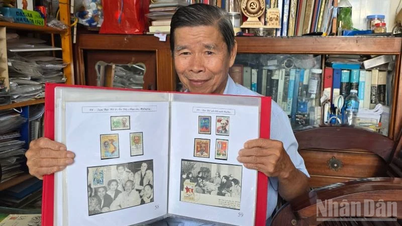






















































コメント (0)