多くの人が疑問に思うのは、なぜエビは調理すると色が変わるのかということです。簡単な説明は、エビの殻に含まれるタンパク質の複雑な相互作用によるものです。栄養情報サイト「The Daily Meal」 (米国)によると、高温によって殻に含まれる化合物が放出され、オレンジがかった黄色に変わるそうです。

調理するとエビの殻がオレンジ色に変わります。
生のエビは通常灰色です。種類によって異なりますが、ほとんどのエビは灰青色の殻をしています。この殻にはアスタキサンチンと呼ばれるタンパク質が含まれています。魚類の鱗にもこの物質が含まれていますが、エビやカニなどの甲殻類には特に多く含まれています。
アスタキサンチンはカロテノイドの一種で、ニンジンにも含まれる物質群です。青色光を吸収し、赤、オレンジ、黄色に見えます。しかし、エビの殻に含まれるアスタキサンチンは、クラスタシアニンと呼ばれるタンパク質と結合します。このクラスタシアニンが、アスタキサンチンの光吸収能力に影響を与えます。
しかし、エビを調理すると、高温によってクラスタシアニンタンパク質がアスタキサンチンから分離し、殻にオレンジがかった黄色が現れます。エビの身はオレンジがかった黄色ではありません。身がオレンジがかった黄色に見えるのは、殻の色から吸収されたためです。
この現象はエビだけでなく、カニなどの他の甲殻類にも見られます。カニの殻の変色も同様の理由で説明できます。
興味深いことに、この現象はフラミンゴにも見られます。フラミンゴは生まれつき白い羽毛を持っていますが、エビや藻類をよく食べます。これらの食物はどちらもカロテノイドが豊富です。
エビの殻や藻類は摂取されると吸収され、体内に取り込まれます。その結果、鳥の羽はピンク色に変わります。これは、ニンジンを食べ過ぎると人間の肌がわずかにオレンジ色になるのと似ています。しかし、 The Daily Mealによると、フラミンゴとは異なり、人間はエビをたくさん食べてもオレンジ色や黄色になることはありません。
[広告2]
ソースリンク




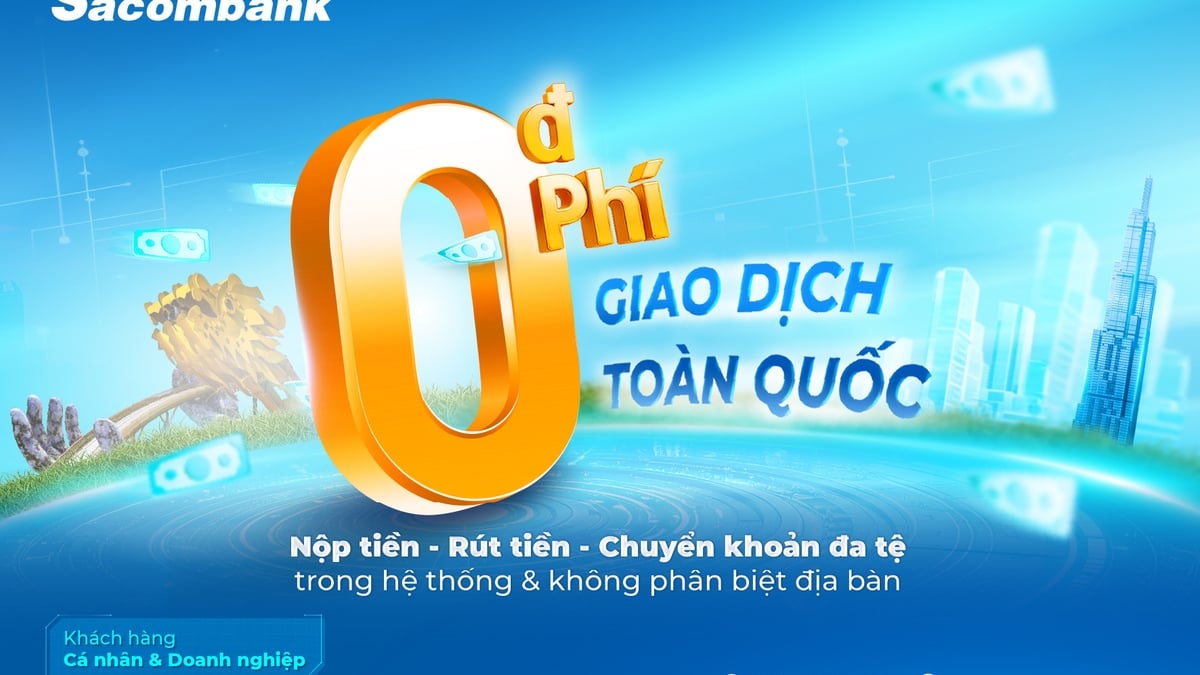













































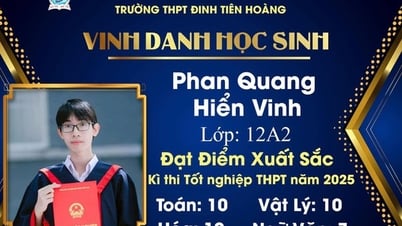


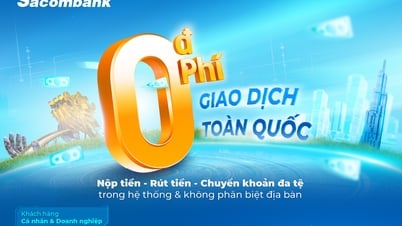












































コメント (0)