ハノイ工科大学は、TSA思考力評価試験を新たな方法で実施して2年目となります。2022年以前と比較して、試験構成が調整されました。特に、試験構成の調整に加え、ハノイ工科大学は、問題の質の評価と受験者の試験得点の算出に、質問応答理論(IRT)という新しい評価理論を適用しました。
このため、受験者は試験終了後に自己採点を行うことができず、受験者の試験データの分析による採点結果を待たなければなりません。そのため、結果発表後、多くの受験者が予想と異なる点数を受け、混乱を招いています。

ハノイ工科大学が主催するTSA思考力評価テストには多くの学生が非常に興味を持っています。
テストのスコアは、受験者の能力を推定する定量化されたモデルです。
受験者のこうした懸念を払拭するため、タンニエン新聞は、教育評価と測定の分野で長年研究と実践に携わってきた独立科学者で、過去2年間ハノイ工科大学にTSA思考評価テストの実施についてコンサルティングしてきた人物の1人であるダン・スアン・クオン博士にインタビューしました。
ダン・シュアン・クオン博士によると、質問応答理論は、受験者の能力とその能力を測定する問題との関係を説明する数理モデルに基づいています。この理論的アプローチでは、問題のパラメータ(難易度、識別、推測など)と受験者の能力が、試験に参加した受験者グループのテストデータに基づいて定量化されます。したがって、質問応答理論から推定される受験者の能力は、従来の採点方法とは異なります。

受験者は、TSA 思考力評価テストを受ける前にテストを受けます。
従来の採点方法では、テストの得点は、特定の採点ガイドに従って、テスト内の問題の得点を機械的に加算しただけのものです。専門家はこれを「素点」と呼びます。素点があれば、ほとんどの受験者は解答を頼りに自分のテストを採点することができ、たとえテストが客観形式の多肢選択式問題のみであったとしても、受験者はテストを受けた後に自己採点することができます。
質問応答理論のアプローチでは、テストスコアは受験者のテストデータを分析した上で、受験者に通知される結果です。これは専門知識を要する複雑なステップであり、専用のソフトウェアを用いて実行され、統計指標を用いて慎重に検討されます。本質的に、テストスコアは定量化された結果であり、受験者が自分の能力を把握するのに役立つだけでなく、他の受験者全員の結果と比較するための基準にもなります。
ダン・スアン・クオン博士は次のように説明した。「原則として、受験者がテストを終えた後、システムはテストの各質問のデータに基づいて受験者の能力を推定します。これには、対応する各質問に何人の受験者が答えられるか、その受験者がどの受験者か、各受験者が何問答えられるか、その受験者がどの質問であるかなどの情報が含まれます。」
受験者のテスト結果データは、システムが受験者の能力を推定するモデルを生成するのに役立ちます。この推定能力から、テストで使用される尺度(通常は0~100)に変換され、思考力評価スコアが算出されます。
たとえ 70 問正解したとしても、テストの点数は異なる場合があります。
ダン・スアン・クオン博士はまた、ハノイ工科大学の現在のTSA思考力評価試験は、1パラメータの質問応答モデル(問題の難易度のみを考慮)と2パラメータ(問題の難易度と識別力を考慮)の適用を組み合わせた試験であると述べました。上記の原則により、受験者グループは同じ素点を持ちますが、学生のTSAテストの点数は異なります。
ダン・シュアン・クオン博士は、次のような例を挙げました。「試験に100問あるとします。従来のアプローチでは、正解1問につき1点が与えられます。2人の受験者が70問正解した場合、それぞれ70点を獲得します。しかし、質問応答理論のアプローチでは、試験の各問題は難易度が異なり、受験者の能力は、どの問題に正解したかに基づいて推定されます。そして、この2人の受験者の場合、受験者Aが受験者Bよりも難しい問題を解くことができれば、受験者Aの能力は受験者Bよりも高くなります。さらに、問題の難易度も受験者の能力を推定する要素となります。その結果、学生Aの発表スコアは学生Bのスコアよりも高くなります。」
簡単に言えば、従来の生の点数に基づくアプローチでは、問題の点数は同じ「重み」で計算されるため、問題の難易度や易しさは考慮されません。一方、質問応答理論では、問題の点数は異なる「重み」を持ちますが、この重みはテスト作成者の主観的な意図によるものではなく、受験者のテストデータに基づく数学モデルに基づいて計算されます。
質問応答理論を適用する過程で、試験データの分析では比較の手法も用いられ、受験者の得点を共通の尺度に合わせます。思考力評価試験は毎年複数回実施され、受験者は試験後すぐに結果通知を受けます(年次試験の実施まで待つ必要はありません)。
異なるラウンドで受験する受験者間の入学手続きにおける公平性を確保するため、試験主催者は第1ラウンドのスコアを基準として採用します。第2ラウンド以降の試験結果の分析においては、均等化手法を適用し、第2ラウンドの受験者のスコアを基準スコアに戻した上で、正式な成績を発表します。これにより、ラウンド間の試験結果の比較が容易になります。
ダン・スアン・クオン博士によると、それぞれの理論には長所と短所がある。「ハノイ工科大学では、思考力評価試験に質問応答理論を適用する際に、毎年具体的なロードマップを策定し、非常に慎重に試験を進めています」とクオン氏は述べた。
ダン・スアン・クオン博士は、オーストラリアのフリンダース大学で教育測定と評価に関する論文を発表し、教育学の博士号を取得しました。この分野で18年以上の経験を有しています。
[広告2]
出典: https://thanhnien.vn/vi-sao-nhieu-thi-sinh-thay-diem-thi-danh-gia-tu-duy-tsa-khong-nhu-ky-vong-185240525095542657.htm


















































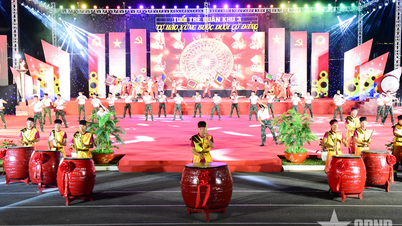



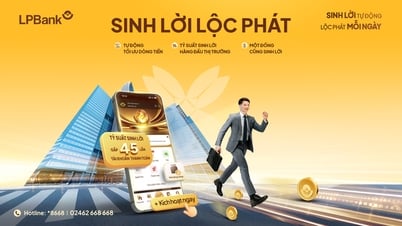
















































コメント (0)