
私は古代の塔の石壁に手を置いた。石は冷たかったが、それは物質の冷たさではなく、時の冷たさだった。幾世紀も経った時間が、レンガ一つ一つ、亀裂一つ、浸食された鉱脈一つ一つに、静かに凝縮していた。私の指は、物質化し、静寂の中に結晶化した記憶の層に触れているようだった。
地面と岩の肉にナイフが切り込んだような細い亀裂に、黒い筋が走っていた。それは静止していなかった。時の層の下に隠された、目に見えない流れのように、動いているのを感じた。
黒い筋はレンガの縁を、石の溝を這い、そして静かに壁に張り付く苔の中へと消えていった。古木の梢から差し込む斜めの光の下で、黒い筋は突然、眩しいほどではなく、痛ましいほどにきらめいた。まるで、今にも去ろうとする人の最後の視線のようだった。
私は滅亡した王朝、チャンパ、赤土に染まった城塞、塵の中に残された神々と愛の物語を思い浮かべます。
おそらく、ここにはかつて、冷たい石段を裸足で歩き、腕に石琴を抱え、森を眺めながら、二度と戻らない誰かを待つチャム族の少女が住んでいたのだろう。
軍馬が塔の麓まで撤退し、火が王朝全体を焼き尽くしたとき、その愛は依然として残っていた。それは塵のように小さく、しかしその黒い染みのように永続的で、決して消えることはなかった。
私は静まり返った廃墟の中に立ち、その黒い筋を、歴史を流れ、名付けられることのなかったものを書き続ける記憶の流れとして、生きた存在として見ていた。
黒い筋はレンガの穴の周りを曲がりくねり、木の根に溶け込み、岩に染み込んでいく。まるで涸れることのない地下水脈のようだった。実際に見た者は誰もいなかったが、誰もがその存在を感じていた。まるで心の奥底で囁かれるように。とても優しく、それでいて無視できない。

塔のドームの上空は重苦しく感じられた。塔から突然、神鳥が羽ばたいた。翼を飛ばす音ではなく、空と記憶が触れ合うかすかな音。その音は空間を揺らし、過去と現在、魂と肉体を繋ぐ目に見えない糸のような響きを残した。
壁の隅に、古代のレリーフの指が伸び、夕陽に照らされて動いていた。まるで溶けていく何かを掴もうとしているかのようだった。空っぽの地下室を風が吹き抜ける音が聞こえた。まるでシヴァ神が目覚めたかのようだった。
あなたは――どこから来たのかわからないが――私の傍らに立っていた。まるで幾多の人生を生きてきたかのように、遠くを見つめていた。私はあなたの手に触れた。香炉の香りが漂う、かすかな煙の層にだけ触れた。あなたは、かつて沈黙の中で愛し合い、霧の中で待ち続け、石へと溶けていった人々の化身だ。
まるで塔の奥深くから、古くてひび割れた心臓があり、そこから黒い筋がにじみ出ているように感じた。それは悲しみではなく、語られなかった物語、満たされなかった欲望の痕跡だった。
当時の私の愛には名前も、約束もなかった。だが、形があった。古びた石壁に静かにしがみつく黒い筋のように。誰がその愛を始めたのか、どこで終わるのかは知らなかった。だが、それは存在していた――目撃者も、儀式もなしに。
それは、大きな音で響き渡る音楽ではなく、かつて神聖であったものに触れるたびに胸の中で振動する音楽です。
石壁はもはや物体ではなく、まだ演奏されていない音楽だった。ひび割れ一つ一つ、黒い筋一つ一つが、深い音色を奏でていた。苔を通して光が薄れていくにつれ、私は見た。時の傷跡だけでなく、そこに漂う魂も。そして、きらめく苔の上に、突然青い花が咲いているのが見えた。
私は再び石に手を押し当てた。学ぶためではなく、静まるためだった。そしてその静寂の中で、私は息を呑んだ。寺院からではなく、私の内側から。
私が失った心の奥底にある何かが、今、古代の背景に黒い筋を輝かせながら、あなたとともに戻ってきています。
私たちとその愛は、広大な世界と融合しました。
出典: https://baovanhoa.vn/van-hoa/nhung-vet-den-biet-tho-151502.html



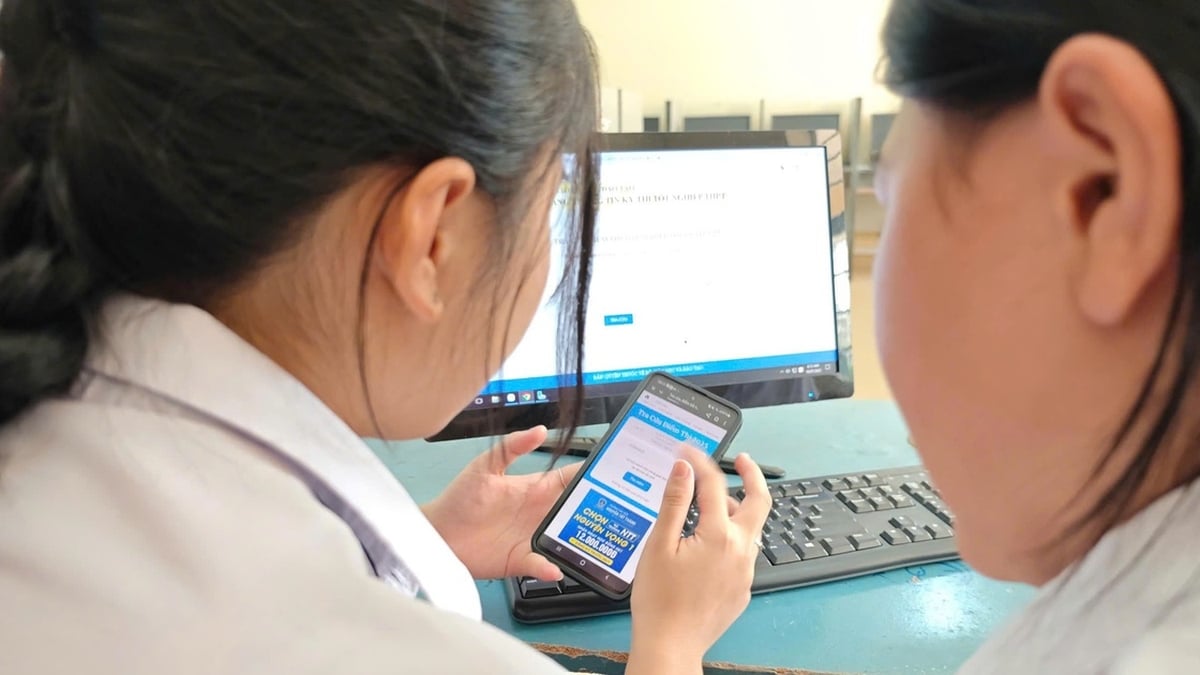







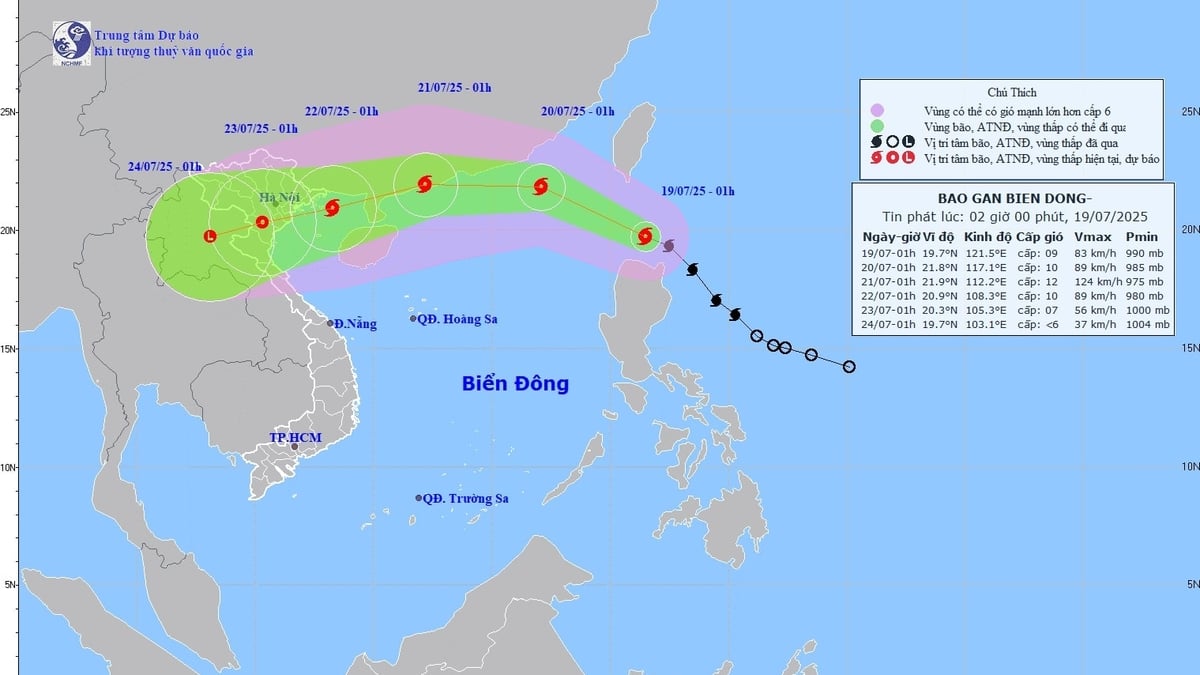






















































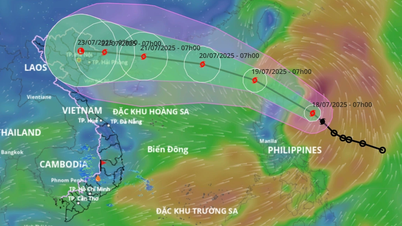



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)