スケジュールに合わせてあちこちを駆け巡るのではなく、ゆったりと旅を楽しみ、リラックスしながら思い出に残る体験をすること。それが今人気の「スロートラベル」です。
夏だけでなく、観光は疲れた人々や多忙な人々を癒す「薬」のような存在となっています。グエン・ハイ・ナムさん(ハロン市ホアンボー区)は、家族旅行の申し込みを検討していました。あちこちを巡るツアーではなく、ナムさんはMiMiQトラベル(ハロン市バイチャイ)のツアーに家族で申し込むことにしました。「家族で休暇を過ごし、クアンランビーチで静かなひとときを過ごせます。ホームステイを体験し、海辺の人々の暮らしに溶け込み、朝は丘を自転車で登って日の出を眺め、午後は釣りをしたり、網を引いたり、貝を掻き集めたり…最高です」とナムさんは嬉しそうに語りました。

体験と適度な休息を両立させるというトレンドが、徐々に観光客の心を掴みつつあるようです。「観光だけでなく、多くの場所や賑やかなスポットに行くことではなく、『ゆっくり』暮らし、休息を取り、自然、生活、そして地元の文化に浸ることを重視しています…」とMiMiQ Travelの担当者は語りました。
実際、コロナ後の時代において、世界はペースを落として一瞬一瞬を楽しむ必要性とともに、観光業に大きな変化を目撃しました。 この傾向は近年、アジアやヨーロッパの多くの先進国で人気を集めています。京都(日本)、ヴェネツィア(イタリア)といった、歴史と文化に彩られた多くの観光地でさえ、観光客数を制限しており、これは有名な「スローツーリズム」の典型的な例です。
「スロートラベル」とは、ゆったりとした体験や観光旅行のことで、リラックスした雰囲気の中で、目的地を深く探求し、一瞬一瞬を楽しむことに重点を置いています。多くの場所を急ぎ足で訪れ、あらゆる体験を試すのではなく、「スロートラベル」では、一つ一つの体験を、訪れた場所の文化、人々、料理などについて学び、より深く感じる機会と捉え、選択的に旅をします。

ベトナムでは近年、「スロートラベル」が注目を集め、主流となっています。これは、多くの場所を巡る「ランニング」旅行に取って代わり、多くの場所を訪れて同じ日に出発する傾向にあり、目的地と観光客の両方にプレッシャーをかけています。ハロツアートラベル(ハロン市)のディレクター、トラン・ダン・アン氏は次のように述べています。「観光客はますますゆっくりとしたペースで旅をし、最もユニークで興味深く魅力的な目的地を選び、楽しむ傾向にあります。私たちは、量ではなく、質と感動をツアーのハイライトとして重視する「スロートラベル」を推奨しています。」
アン氏によると、現在多くの旅行会社が「スロートラベル」の優位性を個人で訴求するだけでなく、旅程や旅行形態に柔軟に適用しているという。代表的なものとしては、自然の美しさや未知の土地を探索するトレッキング観光、冒険と自己発見を目的とした「バックパック」観光、地元の食や文化を楽しむグルメ観光などが挙げられる。さらに、仕事やプロジェクトを通じたボランティア観光、自転車でのツアーや旅行といった新たな形態も生まれている。これらの観光形態に共通するのは、いずれも時間を投資し、アクティビティを重視し、斬新でユニーク、そして非常に楽しくリラックスできる点だ。
実際、クアンニン省の「スローツーリズム」の形態は、旅行会社によって採用されたり、過去には有名なツアーの一部になったりしています。たとえば、イエンドゥック村体験ツアー、イエントゥの自然に浸る瞑想ツアー、クアンラン島とミンチャウ島の漁師の生活を体験するツアーなどです...

この魅力に、多くの旅行会社や地域団体が真剣に取り組み、魅力的な「スロー」ツアーを企画・実施・統合してきました。例えば、観光客の少ない秋冬にコト島でヒーリングツアーを企画するなどです。観光客はパゴダを訪れたり、ビーチで早朝から瞑想やヨガをしたり、ダイビングで海を探検したりすることができます。また、稲が実る時期に村を訪れ、ビンリュウ高原で新米の季節を体験することもできます。さらに最近では、この地域では森の中をトレッキングしたり、タケノコ狩りをしたり、宿泊して村人たちと一緒に版築住宅を建てる体験をしたりといったツアーも企画されています。
さらに、かなり人気のある形態は、旅、リラックスした休暇、ゆっくりとした生活、騒がしくなく自然に浸ること、田舎暮らしを楽しむこと、釣り、果物狩り、郊外、高地、ハロン、ビンリュウ、ヴァンドン、ティエンイエンなどの少数民族でのホームステイ、ファームステイなどです。
人気はあるものの、専門的でユニークな「スロートラベル」ツアーの数は少なく、普及には至っていません。「スロートラベル」は、観光客の心身のリラックスやバランスの回復に役立つだけでなく、様々な体験を生み出し、地域における新たな地域や観光活動の発展にも貢献するため、積極的に推進していく必要があります。
ソース




















































































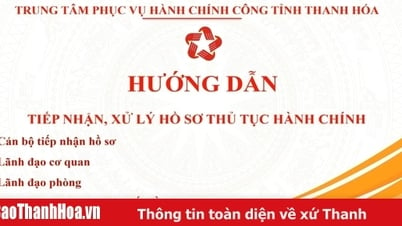




















コメント (0)