その結果、妊娠検査の結果、妊娠21週目に妊婦NPPAさん(27歳、ホーチミン市3区在住)の胎児心臓に異常が見つかり、進行性大動脈弁狭窄症と診断されました。妊婦は羊水穿刺と遺伝子アレイ検査を受けましたが、異常は見つかりませんでした。
1月11日時点で、胎児は29週で、重度の大動脈弁狭窄症を呈していました。胎児および小児心臓学の専門家による協議の結果、本症例において緊急胎児介入、あるいは妊娠30週以降の大動脈弁拡張のための遅延介入が行われなかった場合、胎児は子宮内で失われ、死産率が50%を超えるか、胎児が左室低形成症候群および単心室心壁へと進行する可能性が高いと結論付けられました(出生後、一時的に単心室循環に戻すための複数回の手術、または心臓移植による完全な治療が必要となる)。
心臓専門医は、この時期の胎児心臓介入が適切であることに同意しています。しかし、羊水過多のため胎児の位置が心臓介入に適さないことが予測され、胎児は絶えず体位を変え、体位の変化も激しいため、処置の実施が困難になり、処置が成功しない可能性もあり、介入中に胎児心停止のリスクがあることを説明する必要があります。

保健局長のタン・チ・トゥオン医師は、 2つの病院の指導者および胎児介入チームとともに、妊婦と胎児への介入を行う前に協議した。
この特別な手術の進行は、小児心臓専門医の予測通りでした。胎児の位置が絶えず変化し、針を左心室から大動脈弁まで挿入するのが非常に困難でした。
土度病院の介入チームは20分かけて針を正しい位置に挿入し、その後、小児第一病院の心臓弁チームに引き継ぎ、大動脈弁の拡張という最後の重要なステップを完了しました。その後、母親は手術室でさらに15分間モニタリングされ、胎児心嚢液の状態は安定していました。
手術は同日午前11時に終了し、大成功を収めました。妊婦は術後、厳重な経過観察を受けました。午後1時までに心嚢液貯留は良好にコントロールされ、胎児心拍数は正常、母体の容態も安定しました。
1月4日には、前述のトゥドゥ病院と第一小児病院のチームがベトナムで初となる胎児インターベンション心臓手術を実施しました。これは、 ダナンで経過観察されていたLさん(1996年生まれ)の症例です。胎児に重度の心臓異常、先天性肺弁欠損症、右心室低形成が認められたため、Lさんはトゥドゥ病院に転院しました。
土圃病院でのモニタリング中に、胎児の心臓異常が悪化の兆候を示し始め、子宮内または出生直後の死亡リスクが高まりました。しかし、胎児心臓弁の浄化のための介入後、超音波検査で胎児肺弁の血流は良好で、心嚢液貯留は見られないことが確認されました。
両病院の外科チームは、手術中に事故が発生することなく、絶対的な精度を確保しました。これは、この地域の先進国と同等の高度な技術における新たな一歩を示す成功でもあります。
[広告2]
ソース





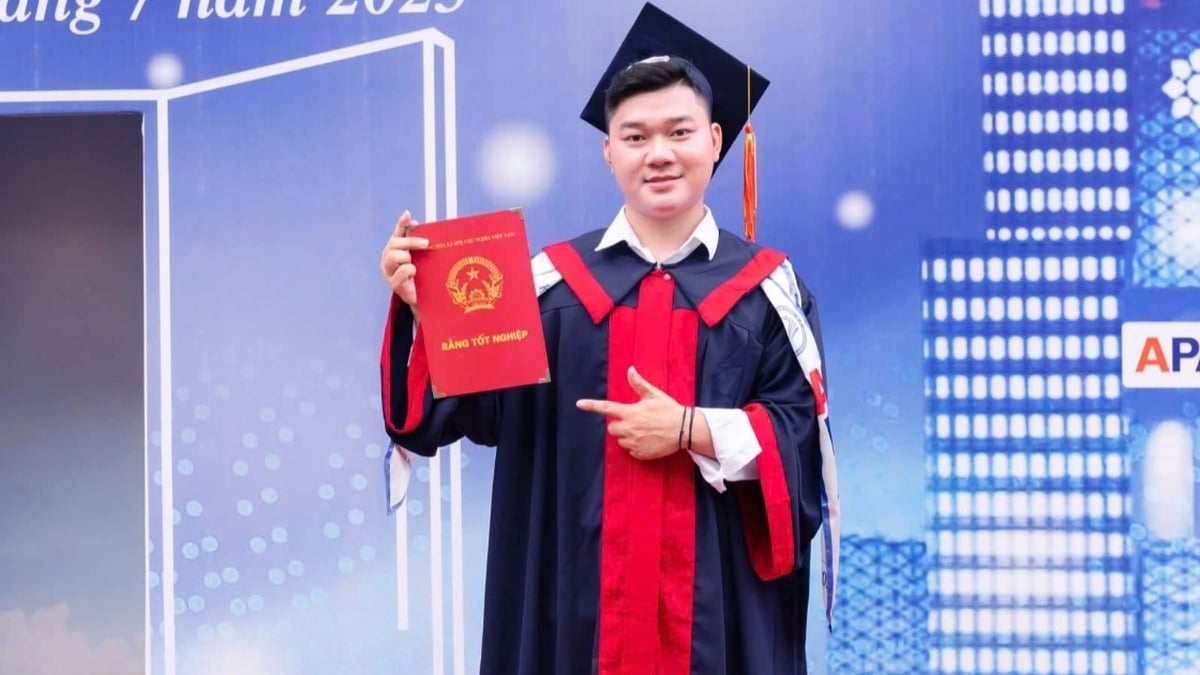


































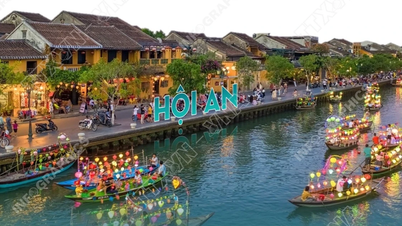























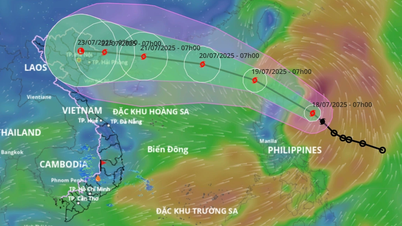



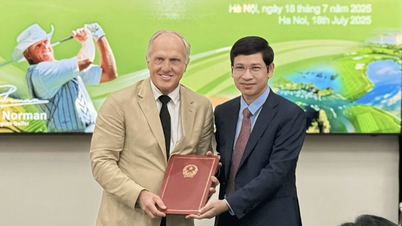



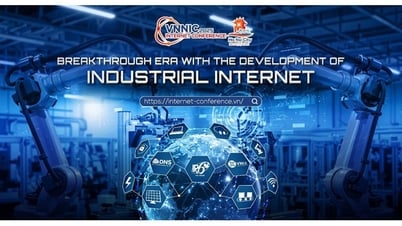






















![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)







コメント (0)