17 歳の Hanh Ngan さんは、文章スタイルが改善され、より本物らしく論理的になったおかげで、IELTS スコアが 7.5 から 8.5 に上がりました。
グエン・ティ・ハン・ガンさんは現在、 ハノイのイエンホア高校に通う11年生です。昨年8月、ガンさんは2回目のIELTS受験で、2か月前の7.5から8.5にスコアを伸ばすことができました。各項目のスコアは、リーディング9.0、リスニング8.5、ライティング8、スピーキング7.5で、最も大きな変化はライティングが1ポイント、その他のスキルが0.5ポイント向上したことです。
IELTSホームページの統計によると、2022年にベトナムでIELTSを受験した人のうち、8.5以上のスコアを達成したのはわずか約1%でした。
Ngan氏は、7.5点台では、リスニングとリーディングでは8点以上を取る受験者が多いものの、ライティングとスピーキングのスキルは6.5~7点程度にとどまっていると指摘しています。7.5点台からさらに高いスコアに伸ばすのは、それ以下のスコアとは異なり、困難です。
「スコアが5.5から6.5に上がれば、生徒はリスニングとリーディングのスキルにもっと重点を置くことができます。しかし、8を超えるスコアでは、すべてのスキルが均衡していなければなりません」とンガン氏は語った。

グエン・ティ・ハン・ガンさん。写真:キャラクター提供
女子生徒によると、ライティングスキルに対する考え方を変えることが、スコアを上げる鍵となるそうです。
「点数が低かった時は、頭に浮かんだことを何でもかんでも書いていました。それでもエッセイは完成していたものの、論理に抜けがあり、コヒーレンス(一貫性)の点数が下がってしまいました」とンガンさんは語った。
最初の試験から2ヶ月後、ガンさんは65本のエッセイを書く練習をしました。彼女はエッセイの小技的な書き方をやめ、論理的思考力を鍛え、本質を捉えて書きました。
例えば、IELTSライティングのパート1(タスク1)では、グラフの記述が求められます。これまでは折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ、表グラフといった形式で問題を解いてきましたが、今回はグラフの性質、つまり静的グラフと動的グラフに基づいてアプローチします。
「チャートが時間の経過とともに変化しない場合は静的チャート、変化する場合は動的チャートです。静的チャートではデータの比較に重点を置く必要があるのに対し、動的チャートでは時間の経過に伴うデータの傾向についてより詳しく述べる必要があるという点が異なります」とNgan氏は説明します。
さらに、女子学生はエッセイの構成にもいくつか変更を加えました。通常、Nganさんはエッセイを4つの段落で書きます。導入、概要、そして2つの展開段落です。概要では、データや図表の全体的な傾向を述べるだけでなく、最も重要なデータについても説明します。
ンガン氏は、前回の試験における最大のミスは、データを単に列挙しただけだったことに気づいた。2回目の試験では、似たような特徴を持つデータを一つの段落にまとめ、大きいものから小さいものの順に並べ、比較・評価した。ンガン氏によると、この方法により、受験者はデータ間の変動や相関関係を明確に把握できるという。ンガン氏は、ある国の人口グラフを例に挙げた。単にデータを列挙するだけでは、高齢者と若年層の割合しか把握できない。しかし、データを評価・比較することで、人口の高齢化や若年化の傾向を一般化できるとンガン氏は語った。
「審査員が求めているのは論理的思考力であり、論理的思考力を発揮できれば得点につながる」とンガン氏は述べ、データを説明する際に使用する特定の語彙を暗記することも非常に重要だと付け加えた。
パート 2 (タスク 2) では、書き始める前に、Ngan 氏は約 5 分間かけて、経済、教育、文化の観点から水平にアイデアを見つけ、次に個人、集団、社会レベルから垂直に考え、アイデアを整理しました。
ガンさんは試験のテーマの例を挙げました。「陸生動物と水生動物は人間の活動によって危険にさらされています。その理由と解決策は何でしょうか?」
その理由について、ンガン氏は経済的・文化的な観点からアプローチし、陸生動物の個体数と生息地の減少を引き起こす密猟者や伐採者、そして環境に悪影響を与える家庭ごみや事業系廃棄物の排出を挙げた。さらに、密猟者や伐採者に雇用を創出することで廃棄物の削減を促進することや、企業や社会に汚染税を課すグリーン税制を提案するなど、小規模から大規模まで様々な対策を提案した。
「これは私が多様な視点を持っていることを示しています。これらは単なる思いつきのアイデアではありません」とンガン氏は語った。
女子学生は、IELTS受験者には様々なライティングスタイルがあるが、重要なのは試験官に間違いを見つけられないよう論理的に論証することだとコメントした。Ngan氏はまた、難しい単語を使うよりも適切なトピックに関する語彙を使うことが重要であり、高得点のエッセイには書き手独自のライティングスタイルが見られることが多いと評価した。Ngan氏はライティングスキルの復習過程で、IELTSの専門家が作成したサンプルエッセイをよく参考にし、論証の仕方を学んだ。
スピーキング力に関しては、ンガンさんは試験対策は日常的に英語でコミュニケーションを取るのと同じだと考え、高度な語彙やイディオムを使うことには重点を置きませんでした。シャドーイング法(物まね)を使った発音練習、映画の登場人物のように自然なトーンで話す練習、そしてお気に入りの英語の歌を歌う練習を行いました。
「受験者の心理としては、豊富な語彙を好む傾向がありますが、実際には、普通に話しているときにそのような単語を思いつくのは不可能です。あるいは、予想だけで勉強しても、試験問題によっては、点数は伸び悩むことになります」とンガン氏は述べた。
Nganさんは、リスニングとリーディングのスキルにおいて、ほとんど苦労したり、過度に復習する必要がなかったそうです。Nganさんによると、幼い頃から英語の本を読んだり映画を見たりしていたため、早い段階で英語の基礎が身についていたそうです。Nganさんの好きな映画はマーベルで、様々な英語のアクセントに慣れるのに役立っています。また、Nganさんは中学校時代から『ぐうたら日記』を全巻読み、世界の話題を扱った『Hot Topics』を豊富な語彙力で読みました。
Nganさんは、この年齢でIELTSを受験するのは人生経験が浅いため不利だと考えています。そのため、マクロなテーマに遭遇した際には、身の回りの最も身近な物事と関連付けて理解し、試験に臨むようにしています。
「例えば、平等主義というのは非常に漠然としたテーマです。しかし、私は学生が平等に教育を受けられるということに限って話します。重要なのは、私がどのような意見を持ち、それをどのように擁護するかです」とンガン氏は述べた。
ドアン・フン(g hi )
[広告2]
ソースリンク
































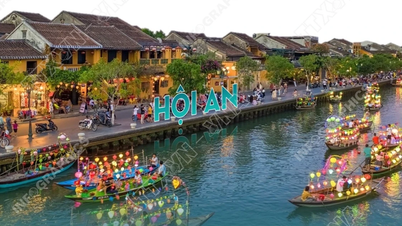


















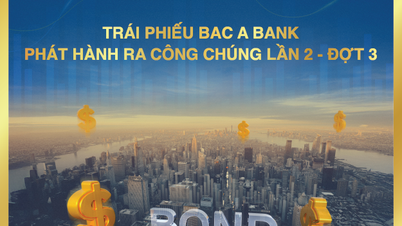








































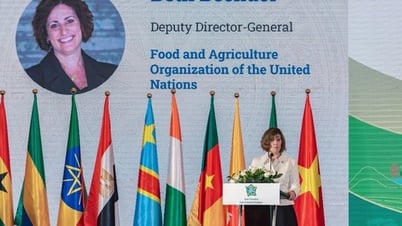








コメント (0)