杜叔父が警備員としてこの会社に入社してから20年が経ちました。妻と家で大晦日を過ごしたのも20年ぶりです。春になると、妻と数人の人に会いに行くためだけに家に帰り、その後は急いで会社に戻って勤務に就きます。

イラスト:THANH SONG
屠叔父は退役軍人で、過去の戦闘について滅多に人に話さなかった。彼にとって戦争は恐怖であり、勝利は決して完全なものではないようだった。解放の日、彼は左足を引きずりながら故郷に戻ったが、それは多くの戦友に比べればまだ幸運だった。村は荒廃し、血縁者も残っていなかった。彼は友人の家に身を寄せていた。そんな時、誰かが彼に裁縫師を紹介し、二人の幸せは再び訪れた。二人はすぐに夫婦になった。数年間一緒に暮らしたが、二人の間には子供ができなかった。人々の議論を聞き、頭を痛めた二人は都市に移ることを決意した。当時の都市はまだ簡素な場所で、二人は簡素な部屋を借り、それを購入するためにお金を貯めた。
都会に移り住んで以来、妻は下宿屋で裁縫をし、彼はその代理店の警備員として雇われていた。20年経った今でも、街は賑やかだったが、彼の家族は相変わらず貧しく、ひとり親家庭だった。稼いだお金は日々の食費に消え、足が悪化しては病院に通うなど、決して余裕はなかった。杜叔父は妻を慰め、「まあ、子供もいないのに、家なんて持つ意味がない。客はそんなにお金を持っていないのに、豪華な家なんて持つ意味がない」と言った。妻は夫を気の毒に思い、冗談を飛ばして「町で一番大きな三階建ての家があって、全部の部屋を開けられるのよ」と言った。それから夫婦は抱き合って、楽しそうに笑い合った。50歳近い夫婦は、今でも優しく兄弟姉妹と呼び合っていた。おそらく子供がいないから、まだ新婚だと思っていたのだろう。
事務所では、毎年何十もの会議、記念日、祝賀会が開かれます。事務所で行われる式典は実際には少なく、他の部署がホールを借りて開催しています。杜おじさんは部屋の装飾と展示を担当し、数十人に報酬を支払っています。手紙の切り抜きから生け花まで、杜おじさんの熱意と多彩な才能は、皆から称賛されています。彼は微笑みながら、「兵士である以上、何事も素早く覚えなければならない」と言います。ジャングルでの困難な時期にも、私たちは盛大な式典を数多く開催することができました。
作業が終わるたびに、ホールには必ず花かごがいくつか残っていました。個人的な贈り物用の花束は持ち帰りましたが、歓迎の花かごはそのまま残されていました。杜叔父さんはホールの掃除を終えると、花かごの前でどうしたらいいのか分からず立ち尽くしていました。捨てるのはもったいない。生花は高価なのに、ゴミ箱に捨てるのはもったいない。
市場の花売りが立ち寄り、トゥおじさんに花籠を持ち帰らせてほしいと頼みました。トゥおじさんはなぜかと尋ねました。彼女は少し手入れをして、赤い布を外して新しい花籠にして売るように言いました。トゥおじさんは呆れて目を回し、それは市場で誰かに捧げたバナナを売るようなものだと言いました。花売りは弁解しました。バナナは花とは違うのです、おじさん。人々が先祖に捧げたバナナは魂が喜ぶものなので、それを返すのは失礼です。しかし、この生花はただ見るためのもので、会議に来た人々が花を見るかどうかは分かりません。彼らはただ聞いているだけです。つまり、この花籠はテーブルと椅子のように、持ち運ばれるものでした。トゥおじさんは、もし彼女に渡さなければ、捨ててしまうのは神様からの贈り物の無駄遣いではないかと考え、彼女に持って帰るように言いました。
ある日、一日違いで二つの会議が開かれました。翌日の花籠は前の日と全く同じで、布の帯と言葉だけが違っていました。杜叔父はすぐに気づきましたが、何も言いませんでした。「まあ、卸売業を営んでいるんだから、儲かるのはいいことだ」と心の中で思いました。それに、この花はたった二時間しか飾らないので、せっかく綺麗に飾っておいて捨ててしまうよりは、少しは新鮮なうちに飾っておいた方がいい、と。
伝統的な新年は太陽暦の始まりでもあるため、儀式の数も増えます。この部署は前年の総括と新年の指針をまとめ、この委員会は典型的な例を称える会議を開催します。我が国では一年中祭りがあり、伝統的な祭りだけでは物足りず、テトには突然様々な祭りが催されます。さて、テトには人々が互いに喜び合うことを止めることはできません。花が一つずつホールに運び込まれました。トゥおじさんは立って見守りながら、黙々と「シー」5つ、「チャイ」1つ…と数えていました。お金、お金。普段は花の値段は1つですが、テトには3~4倍も高くなります。警備員としての彼の月給は、2時間持つ花かごの値段にしか相当しません。トゥおじさんは突然、自分が無価値だと感じるようになり、テトに人々があちこち出かけるのに、彼が隅っこに座っているのも無理はありません。
20 回目のテトが過ぎた時、彼はあることに気づいた。テトの儀式は毎年頻繁に行われ、各儀式に使われる花の数も増えていたのだ。当時花を頼んでいた女性は今では子供が成長しており、テトはさらに 2 人の子供を連れて、花を飾り付ける屋台に花を持ってきていた。新鮮な黄色と赤の花かごを見て、彼は突然、家を借りている自分の境遇がかわいそうに思えた。テトが来るたびに、妻は市場でダラット産の菊を数本買ってきて、家の小さな祭壇の花瓶に飾っていた。しかし、テーブルの真ん中には花がなかった。キャンディの皿とティーポットが置かれた小さなテーブルはいっぱいだった。しかも、テトには路地裏から訪ねてくる人は 5 人ほどしかいないのだから、花を飾る気にはなれないだろう。
* * *
今年、トゥおじさんは最後の儀式の後、花籠を家に持ち帰り、飾り付けて楽しみ、そして妻を喜ばせるつもりだった。妻を深く愛していたトゥおじさんは、テトの間、戦争と爆撃の時のように、ほんの短い間しか会えなかった。しかし、その花籠を妻にどう説明すればいいのだろうか?もし誰かが使っていたから持ち帰ったと言えば、妻は他人の余剰品を使っていると思われて悲しむかもしれない。もし窓口で買ったと言えば、妻はため息をつき、テト休暇中のお金が惜しまれるだろう。妻に「誰かからもらった」と嘘をつくこともできる。しかし、警備員に花をあげる人がいるだろうか?もしかしたら代理店からもらったのかもしれない。信じられないかもしれないが、代理店は砂糖1キロ、ジャム1袋、色付きワイン1本をくれるだろう。その方が現実的だろう。トゥおじさんは長い間考えたが、妻がそれでも幸せで安心できるような、花を持って帰るいい理由が思いつかなかった。その間に、花売りは最後の花かごを玄関まで運んでいた。
- これ!
- トゥおじさんはまるで彼女を引き止めるかのように優しく呼びかけました。
彼女は驚いて振り返った。
- どうしたんですか、トゥおじさん?
「任せてくれ…」トゥおじさんは言葉を切りながら少し間を置いた。今さら彼女に頼むのは、あまりにも恥ずかしい。こんな風に物乞いをしたことはなかった。あらまあ、人生で誰かに何かを頼んだことは一度もなかったのに、今、自分のものであるはずの花束を頼まなければならず、それが難しく感じられた。その時、彼は正直者でいるのは決して容易なことではないと悟ったのだ。
すると彼は思わずこう言った。
- ...ああ、気にしないでください、それは何でもありません。
花売りの男は、何を言っているのか分からず、しばらくそこに立ち尽くし、それから軽く頷いてトゥおじさんに挨拶し、花を門まで運びました。
その日は年内最後の勤務日で、午後の儀式はオフィスの年越しパーティーだった。つまり、トゥおじさんに花を持って帰りたいと思っても、花屋に行って買わない限り、花をもらうことはできないということだ。花を買って、彼は1本買ったことを後悔したが、妻は10本買ったことを後悔した。もう騒ぎ立てるのはやめよう。
午後から夕方まで、彼は花のことを考え続けた。今年は例年と変わらず、旧正月の飾り付けもない、いつもの借家だった。もしそう知っていたら、今日の午後、少しばかりの「屈辱」を味わいながら、思い切って花かごを持ち帰っただろう。
通りからは線香の香りが漂っていた。年の瀬も残りわずか、彼はオフィスに一人残っていた。自分のことよりも、家にいる妻のことの方が気の毒だった。もうすぐ大晦日だろう?そう自問し、時計を見た。11時45分。まだ間に合うだろう。大晦日に誰かがオフィスに押し入るなんてありえない。だから、あんなに厳重に警備しなければならないのだ。
そこで彼は門を飛び出して家路についた。まるで誰かに追われているかのように走った。通りには夜遅く帰宅する人が数人いて、彼が走る姿を見て不審に思ったようだが、春が近づいているこの空気の中では、誰も気に留めなかった。
大晦日に間に合うように歩き、走りながら、彼の心は花のことを考え続けた。今日の午後、思い切って花籠を買って家に持ち帰れば、妻はきっと喜んでくれただろうと思うと、胸が締め付けられ、後悔の念に苛まれた。そして、花がないせいで、借りている部屋がこれから、そして新年の間ずっとどれほど寒いだろうと想像した。花のない部屋にも、また春が来るのだ。彼の目は潤んでいた。大晦日の露のせいでも、走り回った汗のせいでもない。後悔と自己憐憫に安堵し、彼は涙を流した。
ちょうど12時、隣の家のテレビから花火の音が鳴り始めた。大晦日に間に合うように帰宅したと分かっていたが、それでも驚きは隠せなかった。借りていた部屋の前に立つと、妻がフルーツの盛り合わせを終え、椅子に腕を預けて眠そうな顔をしていた。
夫の姿を見て、妻は言葉を失い、声を詰まらせながら「帰ってきたばかりなのに…」と言った。トゥおじさんは微笑んで頷いた。テーブルに目をやると、ふと、大きくて美しく、生花が飾られた花瓶が目に入った。まだ平らで柔らかい花びらを見て、トゥおじさんは、この花がビニール袋から取り出されたばかりだと分かった。彼が何か尋ねる前に、妻が口を開いた。
「部屋に花瓶に花が飾ってあるでしょ?今日の午後、彼女が持ってきてくれた時は、すごくびっくりしたわ。住所を間違えたのかなと思ったの。実は彼女は市場の花売りの娘だと言っていて、トゥおじさんが花を買って、私に持って帰るように頼んだのよ」
トゥおじさんは驚いた。誰にも華美な頼み事をしなかったのだ。おじさんが落ち着く前に、妻が続けた。
― 旧正月の雰囲気を演出するために、お花も買って家に飾りたかったんです。でも…無駄遣いしてるって責められそうで諦めたんです。ところが、まさかあなたが買ってくれたなんて。
トゥおじさんも奥さんに同じことを言おうと思っていた。でも、気にしないで。春は愛と花で満ち溢れているのに、どうしてそんなことを言うんだろう。
ホアン・コン・ダン
ソース




























































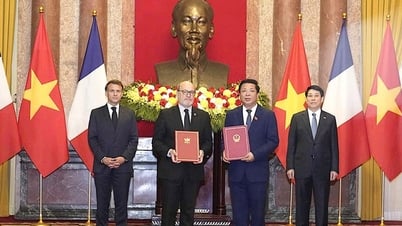
































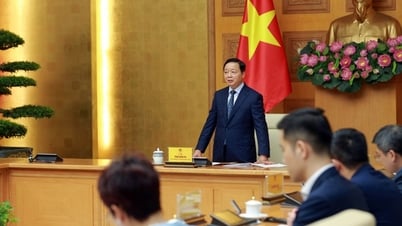






コメント (0)