大学における科学研究(NCKH)は、課題、卒業要件、あるいは活動といった形で実施されます。形態に関わらず、多くの学生は研究を実施するための時間、資料、方法が不足していると考え、研究を始める際に躊躇してしまうことがよくあります。
時間、データベースなど多くの障壁があります...
ホーチミン市人文社会科学大学の学生であるTHさんは、多忙なスケジュールと多くの課外活動を抱えながら、卒業研究を行う上で最も大きな「コスト」は時間だと述べています。研究プロセスの各段階は、それぞれに多くの時間を費やします。例えば、Hさんのグループのメンバーは、英語の科学論文(A4用紙20ページ)の内容を数時間かけて読み、要約するだけでなく、膨大な数の科学論文から情報を統合するのにも数時間を費やしています。
グループ研究のプロセスでは、予期せぬ問題も発生します。TH氏によると、メンバーごとに読解力やプレゼンテーション能力にばらつきがあるため、研究の各部分の品質にばらつきが生じます。そのため、編集を担当するメンバーは、全体の内容の確認と編集に時間を費やすことになります。
さらに、講師は一般的な知識しか提供せず、学校のデータベースも限られているため、THのような科学研究を行う学生はオンラインで文献を探す必要があります。高価な文献の中には、学生にとってアクセスの「障壁」となっているものもあります。

学生には時間、材料、方法が不足しており、科学研究を行うことに不安を感じています。
さらに、多くの学生は研究のアイデアはあるものの、それを実践に移すのに苦労しています。例えば、ブイ・ティ・フォン・アンさん(ベトナム国家大学ハノイ校外国語大学日本語文化学部の学生)は、長年科学研究のテーマに興味を持っていましたが、どこから始めればよいか分からず、これまで研究を先延ばしにしてきました。また、ファン・ゴック・リンさん(ホーチミン市経済大学経営学専攻の学生)は、学校での科学研究に関する知識が散漫で、講師による実施指示が複雑で、実践に応用するのが難しいと感じていました。
実施プロセスにおいては、いくつかのステップが客観的な要因の影響を受けやすく、これも学生が科学研究を恐れる理由の一つです。「調査を『広める』段階で、多くの人が『とにかく終わらせたい』と答えたため、研究モデルは…『奇妙な』結果をもたらしました!」と、ホーチミン市経済大学経営学部のチン・ティ・トゥー・タオさんは語りました。
科学研究は学生にとって負担になりますか?
科学研究のメリットについて尋ねられたブイ・ティ・フォン・アンさんは、まだメリットを感じておらず、むしろ負担が増えていると述べました。一方、ホーチミン市人文社会科学大学の学生であるTHさんは、多くの学生が義務として参加しており、「無味乾燥な」科学研究活動には興味がないと述べました。
しかし、この活動には紛れもないメリットが存在します。例えば、ホーチミン市教育大学で化学と化学教育を専攻するグエン・ホアン・フイさんは、科学研究を通して情報処理能力と英語力を向上させると同時に、専攻分野の応用可能性についてより深く理解することができました。また、ホーチミン市経済大学で経営学を専攻するチン・ティ・トゥー・タオさんは、科学研究への参加を通じて人脈を広げ、自分の立場を守る方法を学ぶことができました。
学生が科学研究を行うのに役立つ2つの要素
そこから、ホーチミン市人文社会科学大学社会学部の学生科学研究管理の講師であるグエン・ヒュー・ビン氏は、科学研究には研究のインスピレーションと必要なリソース(知識、人材、時間)という 2 つの要素が必要であると結論付けました。

学生には科学的研究を行う意欲を刺激し、それを実行するための追加リソースを提供する必要があります。
ビン先生は、学生が独自の研究を始める前に、学部・学科が主催する科学研究関連の様々な活動に参加し、科学研究への興味と好奇心を刺激するイベントの運営に参加することを勧めています。その後、ビン先生は、学生が「大きくて重い」テーマを選んで圧倒され、落胆してしまうのではなく、より実践的なテーマを考えるよう促しています。
実践過程において、学生は学んだ知識を研究課題と結びつけ、既存の知識領域との関連性を見いだしながら、テーマを発展させなければなりません。講師としての役割に加え、学生は多くの文献を読み、問題が生じた場合は講師と定期的に議論する必要があります。ビン氏はまた、「甘い果実」を得るためには、研究テーマを最後まで追求するという強い意志を持ち続け、徹底的に取り組む必要があると強調しました。
[広告2]
ソースリンク





















































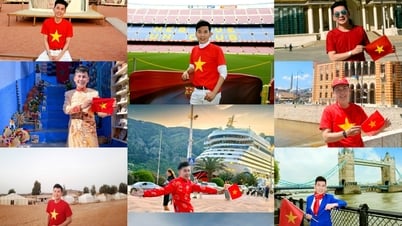
























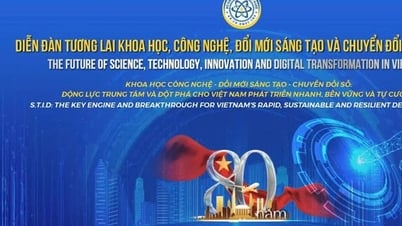




























コメント (0)