2008年8月6日、第10期党中央委員会の決議第27-NQ/TW号は、国の工業化と現代化を推進する時期に知識人チームを構築することについて次のように確認した。強力な知識人チームを構築することは、直接的に国の知性と国力を高めることである。知識人チームの構築に投資することは、持続可能な開発への投資である。
決議第27号の実施から15年を経て、省庁、部局、地方による評価を通じて、ベトナムの知識人コミュニティは量的にも質的にも発展してきました。
しかし、産業化と近代化を推進する時期に知識人チームを構築することは、文化分野を含めて依然として限界がある。
応用民俗文化研究所所長のトラン・フー・ソン博士は、Giao Thong新聞の取材に対し、文化分野の知識人を雇用し、報奨し、尊敬するための画期的な政策を実施する時が来たと語った。
トラン・ヒュー・ソン博士。
文化部門の知識人は不足しており、また弱い。
文化産業の現状と人材の質をどのように評価しますか?
文化分野の人材には、経営人材、制作・ビジネス人材、クリエイティブ人材などが含まれます。
文化分野の統計によると、文化、芸術、 体育、スポーツの国家管理機関、公共サービス部門、文化分野全般で活動する企業で働く直接労働力は 72,000 人以上であり、文化、芸術、体育、スポーツ関連の分野で働く間接労働力は約 150,000 人です。
現実には、多くの中央政府機関および地方政府機関には、文化マネジメント業務を遂行できる有資格者が不足しています。一方で、クリエイティブチームや専門家チームは依然として不足しており、脆弱です。
経済は大きく発展したにもかかわらず、映画、舞台演出、批評理論といった分野における第一線の専門家、そして文化芸術のあらゆる分野における優れた才能、世界クラスの若き才能が依然として不足しています。
全体的に、文化的な人的資源は依然として弱点があり、専門知識の量と質の両方を満たしていません。外国語の能力は依然として限られており、国際交流と統合に影響を与えています。創造力は地域と世界の先進国のイノベーションに追いついていません。
文化部門の知識人チームの量と質の両方が不足している原因は何だとお考えですか?
私の考えでは、主な理由は3つあります。1つ目は、文化産業に対する社会の認識です。文化は、娯楽産業、旗振り業、誰でもできるもの、といったイメージで捉えられ、正しく認識されてきませんでした。
この考え方は、多くの時期、多くの場所で、幹部の恣意的な計画と任命につながり、職務遂行能力に欠け、能力と権威が低く、深い専門知識を欠く幹部を文化分野に配属することさえあります。文化局や文化事務所の幹部の多くは、文化や文化管理の訓練を受けておらず、他の部門から異動してきた人々です。
文化は特殊な産業であり、この分野の経営陣にも特別な専門知識が求められます。文化経営のリーダーが芸術的な才能に秀でていても、マネジメントの方法を知らないとしたら、舵取りはできません。逆に、マネジメントの方法は知っていても文化を理解していない人は、さらに危険です。彼らは人材を発掘し、評価し、業界全体の持続可能な発展政策を提案する方法を知らないからです。
つまり、文化担当者は、文化の問題や価値観に共感し、説明し、明確に分析し、それによって文化の発展に対する明確な視点、方向性、解決策を持つことができるように、文化への献身と深い理解の両方を必要とします。
二つ目は、人材育成の不足です。近年、文化体育観光部は人材育成事業や、海外との協力による研修プログラムを実施してきました。しかし、毎年、目標達成の難しさを「訴え」ています。この不足は、これまで長期的な人材育成政策がなかったことに起因しています。今から人材育成を始めるのは遅すぎます。成果が出るまでには20年以上かかるでしょう。
第三に、人材育成・活用に関する政策の不十分さです。人材に特別な配慮が払われず、適切な政策が実施されていない場合、人材育成・活用は非常に困難です。
高級芸術や伝統芸術には才能ある後継者が不足している。(写真:ト・クオック)
才能には大胆に投資しなければなりません。
第10期党中央委員会決議第27-NQ/TW号の内容から現状まで、あなたがおっしゃったような現状をどのように変えていくことができるとお考えですか。
現在および今後数年間において、第四次産業革命は依然として力強く発展しており、多くの分野で飛躍的な進歩を促進し、あらゆる国に新たな機会と課題の両方を生み出しています。
文化芸術分野の人材への投資は決して安くはないということを、最初から明確に認識しておく必要があります。人材には大胆に投資しなければなりません。しかし、人材チームへの投資戦略には、優秀な人材の発掘、誘致、そして雇用という方針において、明確な目標とメカニズムがなければなりません。
まず、人材選抜の段階においては、小学校、つまり初等文化施設から着手する必要があります。育成対象者を選抜する際には、これらの人材に対する具体的な政策メカニズムが必要です。例えば、奨学金の支給、質の向上、生活費の支給などです。さらに、人材育成に加えて、特に外国語をはじめとする文化教育も提供する必要があります。
彼らが成長した時、社会に貢献しながらも生計を立てられるような、十分なキャリアを選ばなければなりません。そうした才能の中から、特に優れた人材を数名選び、世界トップクラスの研修センターに留学させるのも一つの方法です。
次に、各管理レベルにおいて、文化人材の専門性と資質に見合った、合理的で適切な活用政策を策定する必要がある。同時に、知識人、芸術家、職人に対する研修制度、給与、難解・希少・ハイレベル・伝統芸術の研修支援など、制度・優遇政策を充実させる必要がある。
日本の経験は非常に素晴らしいと思います。政府は、創作活動に専念し、芸術に身を捧げる能楽師を支援するために、あらゆる資源を投入しています。彼らの公演は、他の公演よりも高額なチケットを販売しています。つまり、伝統文化と観光を結び付け、「特産品」へと昇華させているのです。
言うまでもなく、アーティストが職業として生計を立てるためには、国が補助金を出し、製品を市場、特に観光業に結び付ける必要があります。今、文化への投資は「お金を使う」だけでなく「お金を稼ぐ」ことも意味します。
併せて、国家は社会化活動を促進し、文化発展のための投資源、資金、寄付を動員するためのインセンティブメカニズムと政策(税、手数料、信用、土地使用権など)を継続的に改善する必要がある。また、国家は、研修、教育振興、人材育成、文学芸術振興、映画振興、出版支援などのための基金の設立を奨励する。非営利サービスを提供し、社会的インパクトを生み出す社会的企業の設立を奨励するためのインセンティブメカニズム(税の免除・減税など)を整備する。
しかし、現状では、国からの補助金だけでは不十分です。国庫からの投資は、企業や社会からの更なる投資源を引き付ける原動力にもなります。
それどころか、経営陣や文化創造チーム自身も積極的に資質を高め、新しいものを更新し、国の工業化と近代化の潮流に追いつく必要があります。
ありがとう!
2015年から現在に至るまでの複数の省における調査や統計年鑑を見ると、文化分野への投資は依然として低いという現状が見て取れます。地方予算全体の文化支出の1.8%という投資水準に達している省は一つもありません。
文化部門への支出レベルが低いことが、この部門の発展を遅らせる原因であり、多くの地方では文化産業を築く利点を促進できていない...
国費で賄われる芸術作品は、依然として、主要な祝日や重要な政治行事への貢献が主であるが、長期投資プログラムはそれと同期して実施されていない。
トラン・フー・ソン博士
[広告2]
ソース






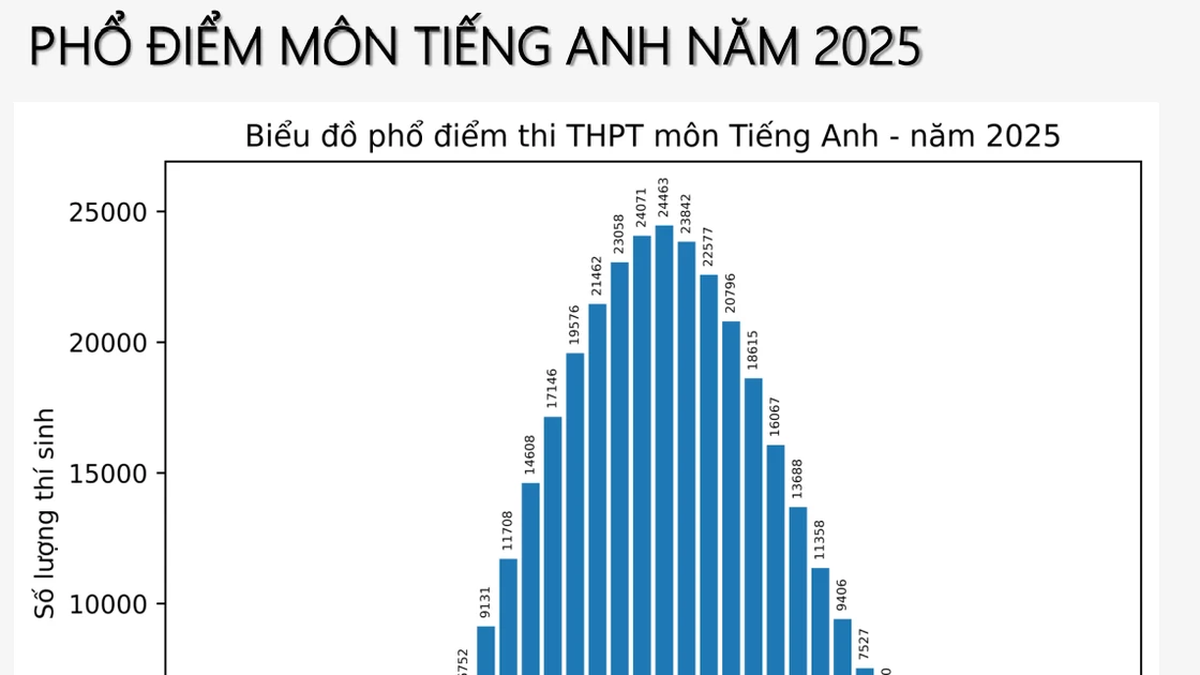

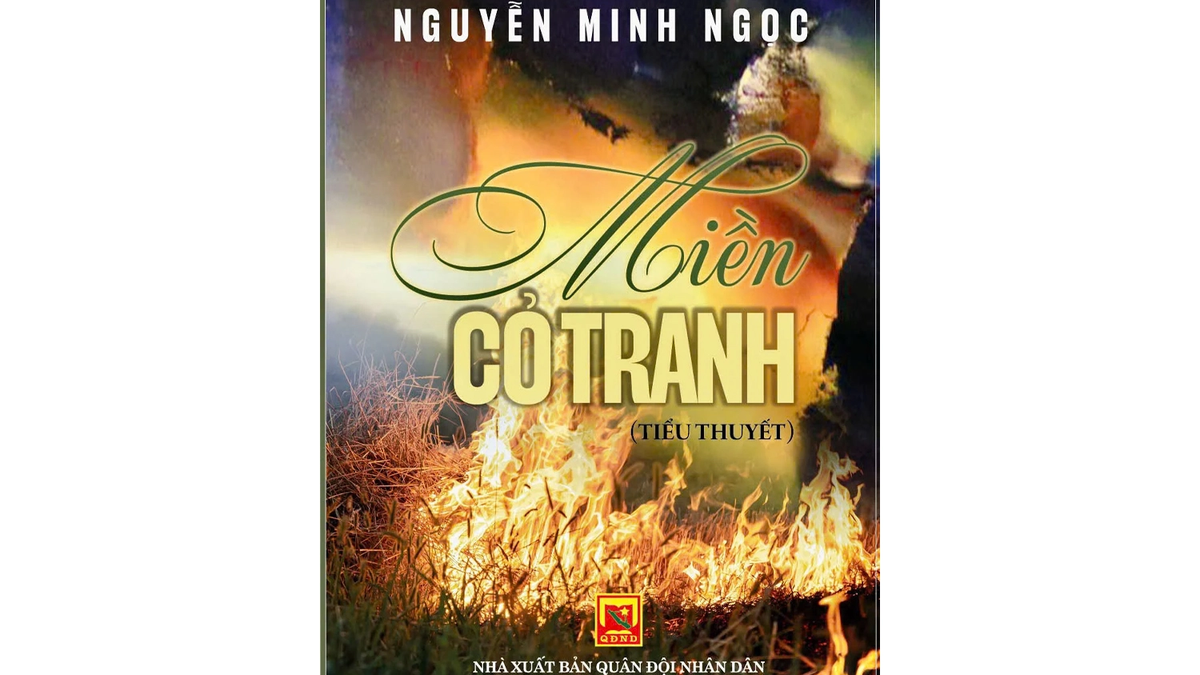








































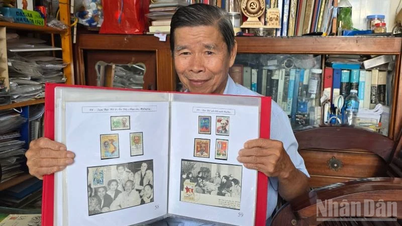




















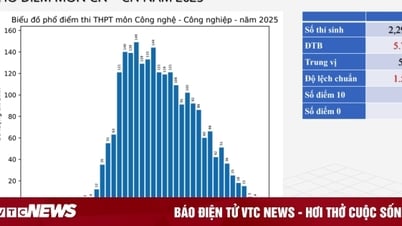

































コメント (0)