
2%の金利支援策についてですが、現在、融資対象となる多くの企業が、受注がなく生産が困難なため融資を受けられない一方で、融資を希望しながらも融資資格を満たさない企業も存在するという矛盾が生じています。この問題について、どのようにお考えでしょうか。
- 実は、企業は2%の金利支援策を慎重に検討すべきです。過去から現在に至るまで、政府の事業支援策を見てみると、中小企業は多大な支援を受けてきました。しかし、その見返りは少なく、支援の条件も非常に厳しいものとなっています。
企業を支援し、企業がより多くの支援を受けて復興し発展できるように支援するという目標を定めているのに、なぜこのような厳しい規制を設け、条件を満たす企業、特に従業員100人未満の中小企業の割合を非常に低くしなければならないのでしょうか。
さらに、回復力のあるプロジェクトを規定するプログラム設計により、貸し手と借り手の双方が、回復力のあるビジネスとは何かを理解することに非常に関心を持つことになります。
11月1日午後の社会経済討論会に出席したグエン・チー・ズン計画投資大臣は、現在支出されているのは8,730億ドンで、計画の約2%に過ぎないと述べた。政府は国会に、このプログラムを2023年末まで継続実施する許可を提出した。もし達成されなければ、予算は廃止される。この問題について、大臣はどのような見解をお持ちですか?
- 私の意見では、企業のアクセスを容易にするための直接的な規定は数多くあり、もちろん、それに伴って非常に煩雑な書類作成や手続きも伴いますが、それでも支援パッケージへのアクセスを希望する企業は数多くあります。
したがって、政府は、2%の金利支援策の期限が切れるまでの間、申請を提出し、期限後も支給されなければならない企業に対し、経過措置を策定する必要があります。支給額は、支給時点ではなく、申請受付時点に基づいて計算されます。
経営者は常に、より明るい未来を目指して、どんな犠牲を払ってでも事業を育て、維持したいと願っています。だからこそ、資源が枯渇した時に政府やその他の機関から支援を受けられることは、私たちにとってかけがえのない財産です。
さらに、可能であれば、政府は2%金利支援策に続き、特に「死の扉」を抜け出し、困難から立ち直ったばかりだが依然として「疲弊」している企業群、特に中小企業を対象とした新たな支援策を検討すべきだと私は考えています。比喩的に言えば、2%金利支援策は貧困層を支援するものであり、新たな支援策を策定することで、貧困に近い層をターゲットとし、貧困からの完全な脱却を目指すべきです。
このサポート パッケージでは、どのグループに優先アクセスが与えられますか?
- ベトナム企業の90%以上が中小企業であるため、繊維、履物、中小企業といった労働集約型グループが対象となります。この支援策には、債務の延長、減額、凍結など、様々な支援方法が含まれますが、具体的には、さらに検討が必要です。
この支援策を策定するにあたり、一部の国会議員は、この問題について決定を下すための臨時国会の開催を検討する必要があると述べ、かろうじて破滅の危機を脱したものの依然として極めて脆弱な企業に活力と息吹を与える必要があると訴えました。これにより、企業は復興と発展の過程においてより安心感を抱くことができるでしょう。
共有していただきありがとうございます!
[広告2]
ソース






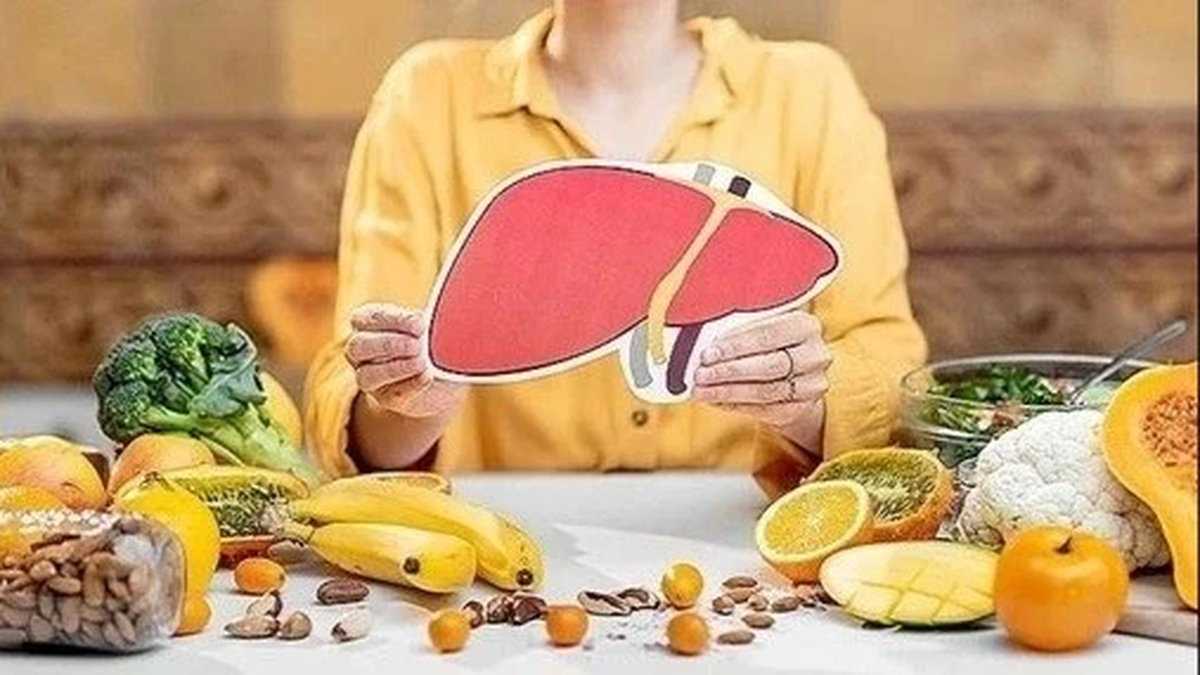











































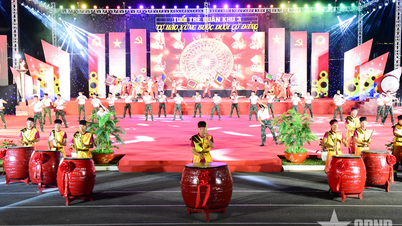



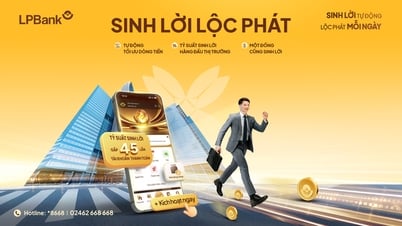









































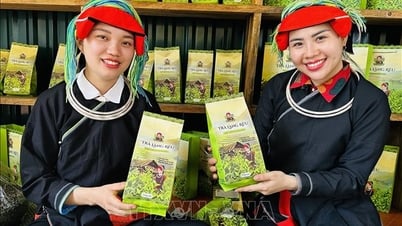






コメント (0)