地質鉱物法の最近の起草において、立法者や当局、専門家や管理者は皆、鉱物採掘権のオークションの内容について、より具体的かつ厳格な規制が必要であるという点で一致しました。立法者や国家鉱物管理機関が目指すのは、厳格な法的枠組みを構築し、鉱物管理の透明性を高め、鉱物と鉱物活動が国の開発目標に効果的に貢献し、透明な情報管理を通じて国家、地方、そして企業の利益に公平に利益をもたらすことです。オークションは、このための強力な解決策と考えられています。
しかし、一部の専門家が指摘するように、いかなる法律も絶対的に完璧であると確信できる人はいない。法律の原則と現実の動向との乖離は、多かれ少なかれ抜け穴を生み出すものであり、鉱物資源の採掘における競売規制も例外ではない。競売違反や競売回避は典型的な例である。

最近、首相自らが、 ハノイの3つの砂鉱山のオークションで、当初の開始価格より数百倍も高い価格が提示された件に関する問題の検討を直接指示しなければならなかった。
ハノイにある3つの砂鉱山が、開始価格の数百倍もの価格で競売にかけられたことについては、様々な仮説が立てられており、いずれも社会的な懸念を引き起こしています。第一の仮説は、これらの鉱山の埋蔵量が現実的に評価されていないというものです。河床下に位置するという特性上、砂の埋蔵量の測定、評価、推定は容易ではありません。主観的であろうと客観的であろうと、わずかな影響で数値が急激に変化する可能性があります。この仮説が現実のものとなった場合、国家は鉱物資源を失うことになります。
次の仮説は、仮想オークションが行われ、その後預託金が没収されるというものです。結論が出るには今後の展開を待つ必要がありますが、ハノイおよび周辺地域で建設資材として使用される砂の価格は、建設現場への輸送費を含めても1立方メートルあたり約10万ドン(約10万ドン)であることを考えると、懐疑的になるのも無理はありません。一方、今回オークションに成功した3つの鉱山に残っている砂の1立方メートルあたりの平均価格は、採掘費と輸送費を含めずとも最大80万ドン(約8万ドン)に達しています。
この価格高騰は人々に「蚕が桑を食べる」という策略を思い起こさせます。つまり、砂の開発許可を得た後、企業は合法的に許可された地域を徐々に開発し、毎日少しずつ侵食していくのです。1年後、振り返ってみると、開発面積は合法的な「核心面積」の何倍も広がっています。
これは多くの地域で起こっており、限られた砂の埋蔵量を補うために、ほぼ当然のこととして暗黙のうちに理解されています。これはまた、企業が砂の採掘権の価格を当初の価格の数十倍、数百倍にまで引き上げようと競い合う多くの理由の一つでもあります。
当局は長年にわたり、各省市で許可範囲外での砂採掘の事例を多数発見してきました…一部の企業は、鉱山の位置や境界線の外で、規定の期間を超えて機器を使用して砂をすくい上げたり、許可された能力を超えて採掘したり、計量所やカメラ監視システムの運用を維持できなかったり、帳簿や請求書、売買書類が不完全だったり、許可された生産量に従わずに鉱物の採掘や取引に対する税金を申告・支払ったりしていました…こうした状況は、以前に発生した競売違反の手口と無関係ではありません。

策定中の地質鉱物法案は、鉱物採掘権の競売に関する規定を補足・明確化しました。2015年刑法(2017年に改正・補足)も、「資源の調査、探査、採掘に関する規定違反」の刑事訴追要件を明確に規定しています。法案草案と関連法の構想により、競売妨害のような、鉱物資源を不正に搾取する行為を抑制・制限するための法的根拠が確立されることを期待します。しかし、法律はあくまでも手段に過ぎません。最も重要なのは、法執行官が自らの職業倫理基準を「破る」ことなく、脱法行為者や法の基準に違反する者を幇助・無視しないことです。
[広告2]
ソース




































































































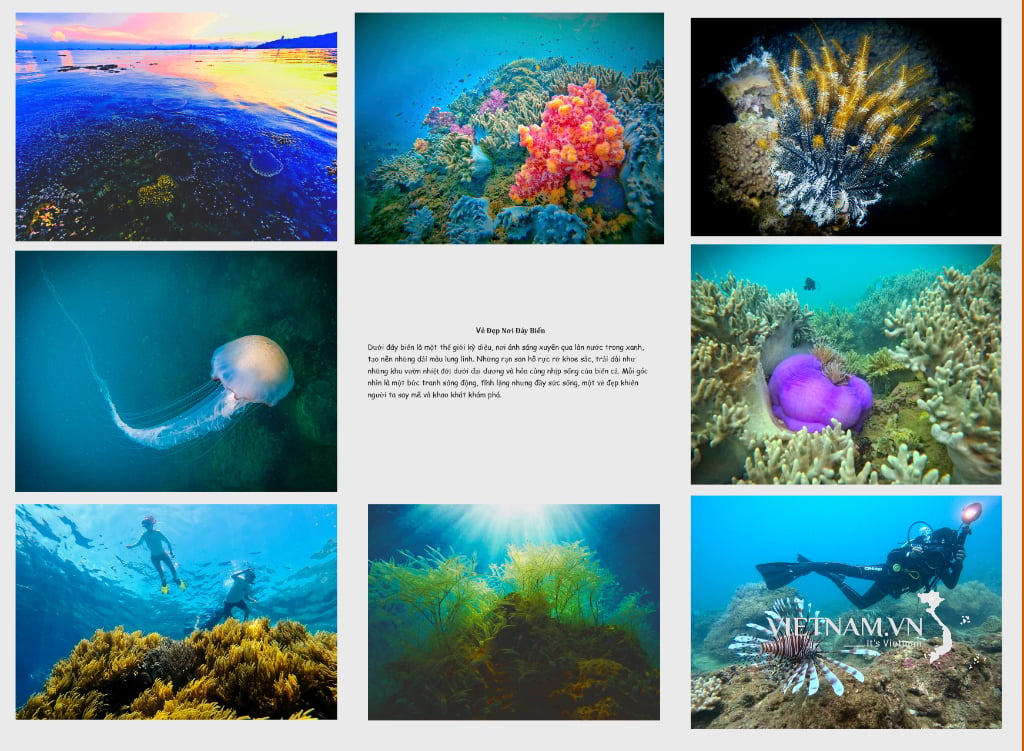
コメント (0)