ドイツ、フィンランド、日本は、持続可能な生活習慣の変革を幼児に教育することを選択した先駆者です。
持続可能性は人生のスキルです
グリーンリビング、あるいはサステナブルリビングは、現代生活と地球上の自然資源、生息地、そして生物多様性の保全と保護とのバランスを目指しています。欧州教育プラットフォームによると、サステナブルリビング教育は、社会意識の向上、モデルの変革、そしてグリーンライフスタイルの促進において重要な役割を果たしています。
フィンランドでは、持続可能な開発のための教育(ESD)は、幼稚園から大学まで、カリキュラムの付加的な要素ではなく、中心的な柱となっています。就学前の子どもたちは、ゲーム、課外活動、教室での実践を通して、リサイクル、省エネ、環境保護の概念を学びます。
典型的な例として、「Palloässät(スマートボール)」プロジェクトが挙げられます。このプロジェクトは、物語の語り、インタラクティブな動画、教室での小規模な気候委員会といった創造的な活動を通して、子どもたちが17の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に取り組むことを支援し、子どもたちの学習意欲を高めています。小学校では、生徒たちはリサイクルプロジェクト、廃棄物を使った絵画、家庭での水使用量のモニタリングなどに参加することで、日常生活における環境に対する責任感を育んでいます。
フィンランドでは、野外教育が人気の教育方法です。子どもたちは森や小川、新鮮な空気に囲まれた自然の中で学び、開放的な教室のような空間で過ごします。この空間は、子どもたちの身体的な発達を促し、自然と感情的に繋がり、人間と環境の関係性をより深く理解するのに役立ちます。
フィンランドの専門学校や大学では、持続可能な教育を積極的に研修プログラムに取り入れています。多くの学生が再生可能エネルギー、廃棄物リサイクル、グリーン都市設計などに関連した実践的なプロジェクトに参加しています。こうした知識は環境教育における意義だけでなく、学生が現代の働き方モデルを理解する上でも役立ちます。

森林から環境意識へ
ドイツは「ヴァルトキンダーガルテン」発祥の地です。 国際的には「森の幼稚園」としても知られ、子どもたちは自然環境の中で学びます。黒板やプラスチックの椅子の代わりに、教室は森です。子どもたちは枝をペン、葉っぱをおもちゃ、石を教材として使うことを学びます。
この方法は、子どもたちの運動能力と自立心を育むだけでなく、自然への深く自然な愛情を育むことにも役立ちます。このドイツのモデルは、自然環境が縮小し、活気に満ちた都市システムに取って代わられた状況において実用的であるため、世界中で広く普及しています。
次の教育レベルでは、ドゥックは数学、科学、言語などの科目にグリーンリビングの内容を統合することに重点を置いています。MINTプログラム(STEMに相当)を通じて、生徒たちは科学的かつ実践的な視点から環境問題に触れます。
ドイツテレコム財団などのドイツの教育機関も、小学生を対象に環境保護に関する読書や物語のプログラムを後援しており、内容をより身近に、より理解しやすいものにしています。
さらに、ドイツ政府は、大学と職業訓練機関間の持続可能な教育ネットワークを構築するHOCH-Nプロジェクトの実施に資金を提供しています。このプロジェクトは、教育機関が教育、研究、運営管理に環境要因を組み込むことを奨励しています。これは、教育を社会全体の消費文化を変革する原動力へと変えるという長期的なコミットメントを示す一歩です。

すべての学生はグリーンエージェントです
日本では1990年代以降、「自然学校」が盛んになりました。子どもたちは農場、森林、生態系の中で体験学習を行います。
しかし、森の中で学ぶドイツとは異なり、日本では生徒たちは「自然を学校に持ち込む」のです。学校で木を植えたり、菜園の手入れをしたりすることで、自然との密接なつながりを築き、労働と環境の価値を理解します。
日本では、単に体験するだけでなく、国のカリキュラムにグリーンリビング教育も組み込まれています。多くの高校では、生徒たちが地域の環境プロジェクトに取り組んでいます。例えば、プラスチック削減キャンペーン、学校の節電、ゴミの分別の推進などです。一人ひとりが、街全体、特に近隣地域を清潔に保つための担い手となっているのです。
日本の持続可能性教育プログラムにおける大きな節目は、世界的な持続可能性教育の取り組みを表彰するユネスコ-日本持続可能な開発のための教育賞へのスポンサーシップです。
これは、教育を単なる知識を伝える手段としてではなく、地球の未来に責任を持つ国民を育成する手段として捉えるという日本政府のビジョンを反映しています。
ドイツ、フィンランド、そして日本に共通するのは、子どもたちを変化の中心に据えていることです。これらの国々は、子どもたちが大人になるまで環境保護の原則を教えるのを待つことはありません。子どもたちがまだ遊び、無垢な目で世界を探検しているうちに、習慣を身につけさせているのです。
フィンランド
- 持続可能な開発に関する教育(ESD)を国家一般教育カリキュラムに統合:2014 年。
- UNESCO ASPlanet ネットワーク (持続可能な開発を含むユネスコの目標の推進に取り組む世界的ネットワーク) に加盟する学校: 120 校。
美徳
- 2016年から2020年にかけての「HOCH-N」プロジェクトには125の大学が参加しました。
- 持続可能な開発に関する教育(ESD)を国家一般教育カリキュラムに統合:2015 年。
- UNESCO ASPlanet ネットワーク (ユネスコの持続可能な開発目標の推進に取り組む世界的ネットワーク) に加盟する学校: 260 校。
日本
- 持続可能な開発に関する教育(ESD)を国家一般教育カリキュラムに統合:2016 年。
- UNESCO ASPlanet ネットワーク (ユネスコの持続可能な開発目標の推進に取り組む世界的ネットワーク) に加盟している学校: 約 1,100 校で、世界最多。
出典: https://giaoducthoidai.vn/geo-mam-tu-tuoi-tho-post741296.html










































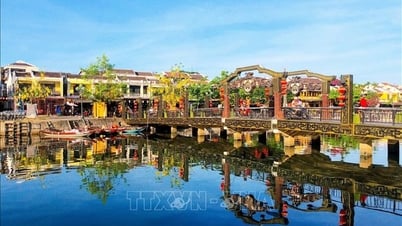



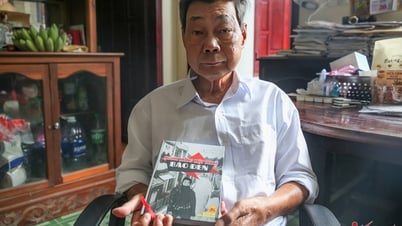





























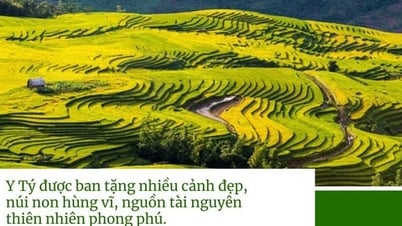
























コメント (0)