これは、 ハノイ市タイホー区の高校教師の心境です。この感情は、ハノイ市内務省とハノイ市教育訓練局が2023年に発表した教員昇進に関する文書に端を発しています。この文書では、資格を有するすべての教員ではなく、「校長、副校長、グループリーダー、主要教員」と「大学9年間教育」のケースのみを考慮するよう指示されているため、多くの教員が、実績や賞状は豊富でありながら役職に就いておらず、選考から除外されてしまいました。
数百人の教師が教育訓練大臣に書面による嘆願書を提出した。ある教師はこう訴えた。「なぜ地方ではすべての教師の昇進を公平かつ透明に検討しているのに、首都の教育制度では役職のある教師の昇進しか検討しないのでしょうか。一体どこに公平性があるのでしょうか?役職のない教師が長年献身的に働いてきたにもかかわらず、それでも自分の職業に情熱を燃やし続けることができるのでしょうか?」
政府法令第115/ND-CP第31条には、「専門職の昇進のための試験または検討は、平等、公開、透明性、客観性、法令遵守の原則に従って行われる」と明記されており、これは政府の方針に沿っているのだろうか?
さらに、内務省と教育訓練省は、試験を実施したり昇進を検討したりする際に、地方自治体も「チームにとって有利な条件を整え、平等、公開、透明性、客観性、合法性の原則に基づいて、専門職への昇進に真に値する教師を確実に特定する」必要があると常に強調している。
ハノイの学校では、最近では役職のある教員しか昇進の検討対象にできなかったり、教育法が施行されてまだ3年しか経っていないにもかかわらず、教員に9年間の大学教育を義務付けたりしている事実は、教育環境そのものに不平等を生み出している。
教師の給与は既に低く、仕事のプレッシャーは高まっているにもかかわらず、多くの教師は依然として教育への貢献と実績を通して自らの能力を証明しようと懸命に努力しています。しかし今、ハノイ市独自の規制によって、わずかな給与を改善するための昇進の機会さえも奪われています。
あまりに多くの不満を受けたハノイ市教育訓練局は、最近、緊急の指導文書を発行せざるを得なくなり、その中で次のように付け加えた。「(名称に「教師」でない)教師が、教師という専門職の名称への昇進の基準と条件を満たしている場合、その構造とニーズが確保されなければならず、教師は教育機関において専門知識を指導する役割を果たさなければならない。」
しかし、教育訓練省の新たな文書は、すべての教師ではなく一部の教師に希望を与えている。教師には職位が与えられておらず、「専門職としての指導的役割」を担う必要があるためだ。そのため、教師たちは依然として、教育機関が昇進の検討対象と認めるまで待たなければならない。さらに、これは教育訓練省から高校に送られた文書に過ぎず、中学校以下の教師グループには依然として他の指示がない。教育訓練省は、小中学校教師に9年間の大学教育を義務付けることは不要であり、規則にも合致していないと断言している。長年の実績を持つ教師でさえ、各地域、特に最近ではハノイにおける政策上の障壁によって「取り残される」可能性がある。
結果がどうであれ、教師たちがその崇高な職業における一見明白で正当な権利を要求するために手紙を送ったり集団請願書を書いたりしなければならないという事実自体が、教師たちだけでなく世論にも負担を感じさせるものである。
[広告2]
ソースリンク











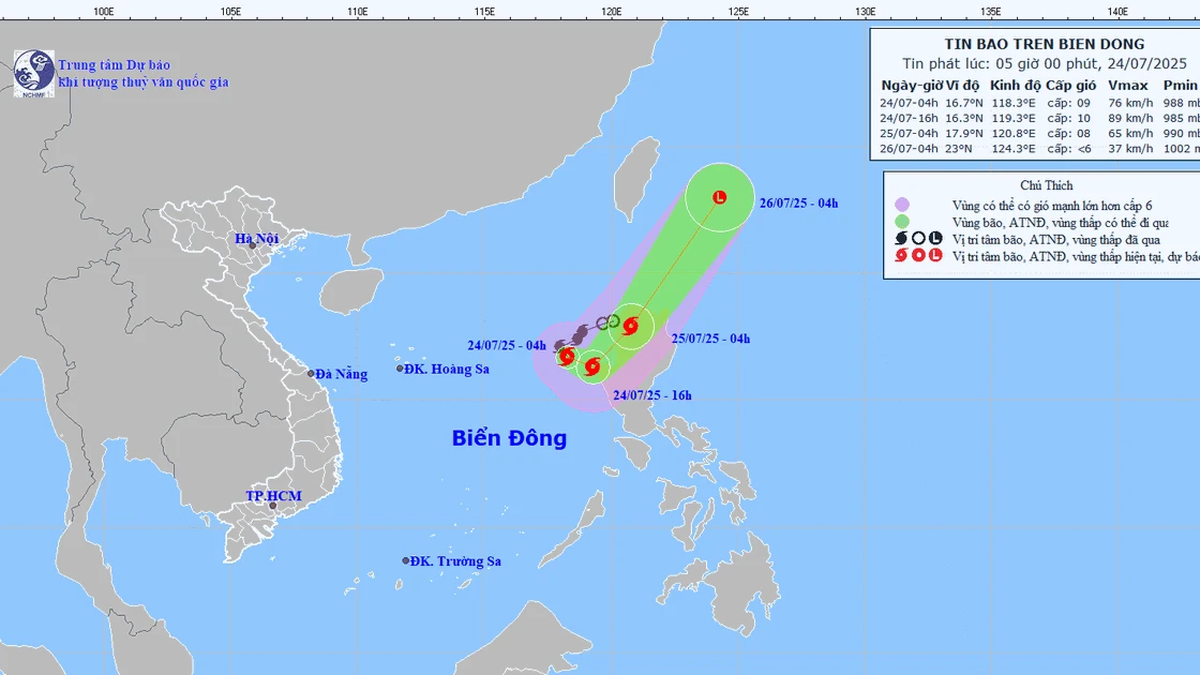




































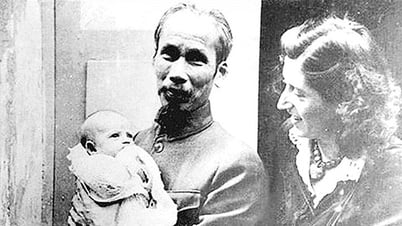

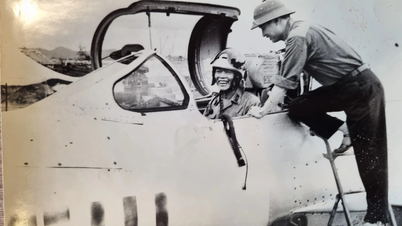













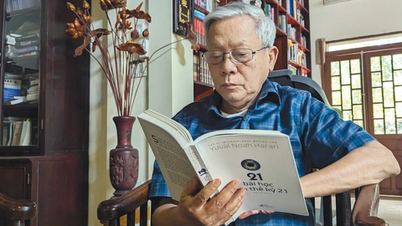


































コメント (0)