後ろでは、巨大な段ボール箱が傾いていて、擦り切れた輪ゴムで縛られており、倒れそうになっていた。

レストランに到着すると、彼はすり減ったサンダルで、とっくに動かなくなっていたブレーキを交換した。店内は客でごった返しており、太ったティン夫人が客を誘うようにあちこち走り回っていた。彼を見ると、彼女はよちよちと店から出て、匂いのするビニール袋をハンドルに掛けた。「ねえ、魚醤のフライドチキンウィングがあるの」
彼は笑った。自転車に乗り、ペダルを漕ぎ始めた。彼女が後ろから「今日の午後は早めに荷物を届けてね!」と叫ぶ声がまだ聞こえた。気にしなかった。太ったティン夫人は彼にそう言うのに慣れていたし、彼は彼女を長く待たせることはなかった。
彼は角を曲がって公園の前の芝生に立ち止まり、新聞紙の上に座り込んで食事の準備をしました。
チリンチリン…遠くから聞き慣れた鐘の音が聞こえてきました。
顔を上げなくても、プードルだと分かりました。散歩の時間です。街灯が点灯する時間になると、犬は散歩に出かけます。そのたびに、こっそりと近づき、しばらく手を嗅いでから去っていきます。飼い主がいつも後ろをついてくるにもかかわらず、プードルと彼が急に仲良くなったのはいつからでしょうか。
彼は滅多にその女性に目を向けようとしなかった。しかし今日は、どういうわけか視線が彼女へと向けられ、止まった。青いスポーツウェアと白い靴を履いた彼女は、とても健康的で優雅に見えた。彼は一目見ただけで、すぐに背を向け、ぼんやりと人混みの通りを眺めた。
「行こうよ、ミット!」彼女は優しく呼びかけた。
従順な犬は後ろ足をひっきりなしに蹴りながら、前を走り続けた。男は長くきちんと結ばれた髪が揺れるのを見ながら、ため息のような笑い声を漏らした。
彼にとって、その光景は毎日の午後にすっかり馴染み深いものだったが、今日はなぜか若返ったような気分になった。高校生の頃、目の前に座っている女の子が、同じように長い髪を高く結んで、あんな風に揺れていることに、彼は密かに気づいていた。
3年間、彼はその髪を静かに抱きしめて眠りについた。ある日、クラスの親友とアイスクリームショップに入った時、その長い髪が揺れているのが見えた。それ以来、彼は長い髪を見るたびに、小さくため息をつきながら顔を背けるようになった。
彼はプードルの飼い主の名前を知らなかったし、知る気もなかった。紫色のサルスベリの茂みの向こうに姿が消えるたびに、彼はただぼんやりと彼女に声をかけた。「スオン!ミットが今日の午後出かけるにはちょっと遅いぞ!」と彼は彼女の後ろでささやいた。
翌日、彼は思いついた別の名前で彼女を呼んだ。「マイ・リー、まだ8時なのに、どうしてミットをこんなに早く帰らせたんだ?」。その翌日、彼は再び「マイ・デュエン…」と呼んだ。彼は自分のこと、彼女が帰ればいい、彼女のこと、とささやいた。一見無関係に思えたが、ある日…
その夜、突然雨が降り始めた。空を雷鳴が駆け抜け、彼は目を覚ました。街灯の淡い光が屋根裏部屋に差し込んでいた。彼は起き上がり、タバコに火をつけ、窓の外を眺めた。
土砂降りの雨の中、黄色い傘を差した女の子が泣きながら行ったり来たり走り回っていました。「ミット!ミット!どこにいるの?」彼は目をこすって外を見ました。
彼女だ!なんてことだ!彼は自分の目が信じられなかった。嵐の真夜中に、彼女はどこへ逃げ出したんだ?何も考えずにドアを開け、通りに飛び出し、「スオン!スオン!」と叫んだ。
彼女は分岐点へ駆け寄り、そして突然立ち止まって辺りを見回した。しばらくして、その呼び声が黒い葉のないガジュマルの木から聞こえてきたことに気づいた。彼女は震えながら歩き出した。服はびしょ濡れで、傘はもう役に立たなかった。
「電話したの?」彼女は彼の前で立ち止まった。長い髪は額に張り付いて水滴が滴り、頬は寒さで青白く、目には心配と不安が浮かんでいた。
「あ…あの…雨の中走ってるのを見たんだけど、夜ですごく暗かったよね!」
「ミットを探しているの。誘拐されちゃったの!助けて!」彼女は絶望して叫んだ。
雨はまだ降り続き、すぐに通りは水浸しになった。通り過ぎる人々は、黄色い傘を差して道端で泣いている少女を不思議そうに振り返っていた。ふと、彼の脳裏に、この通りの端にあるペット用品の看板が浮かんだ。通り過ぎるたびに、鉄の檻の中に数匹の犬が困惑した顔をして立っているのを時折見かける。もしかしたら!彼は家の中に駆け込み、レインコートを着せると、少女を引っ張って人影のない通りを急いで走った。
通りの突き当たりで、雨はちょうど止んだ。店主は荷物をまとめ、閉店の準備を始めていた。店主の許可も待たずに、一番奥の犬小屋へと駆け込んだ。そこには、毛むくじゃらの犬が震えながら、哀れにも困惑した表情で立っていた。
「ミット!ミット!パパだよ!」と彼はケージのドアをそっと揺すった。すると父親の声がはっきりと聞こえてきて、彼自身も驚いた。
犬は彼を一目見るなり、尻尾を丸めてドアを引っ掻き、出てこいと要求した。彼女はすでに彼の後ろにいて、しゃがみ込み、「ミット…ママ!」と叫んでいた。
店主は感動の再会を目の当たりにし、立ち止まった。彼女はかがんでケージの扉を開け、犬を取り出し、彼女に渡した。
「はい…おばさん、ありがとう。今朝は出かけなくて、ドアを閉めるのを忘れてしまって…」彼女は犬を抱きしめ、言葉を失いながら泣きました。しばらくして、彼女は優しく言いました。「おばさん…身代金を返させてください」
店主はかがみ込んで犬の頭を撫でながら言った。「いいですよ、家に連れて帰ってください!身代金はいただきませんから!今日の午後、私が家の中に座っていると、若い男性がこの犬を連れてきました。遠くで仕事をしていて、この犬を飼うことができないから売りたいと言っていました。この美しい犬を見て、私はすぐに同意しました。」
彼女は飼い主にお礼を言い、犬を抱いて戻ってきました。犬は静かに後ろについていきました。
早朝、自転車を玄関から出すとすぐに空を見上げ、午後は雨が降らないようにと密かに願った。いつからこんな待ちぼうけがついたのだろう。愛犬の鈴の音を待ち、影を待ち……
荷物を運んで疲れた一日を終え、彼は公園に行き、芝生に腰を下ろした。午後は焼きソーセージと缶詰の赤梅の二食を食べた。彼は、自分にとって甘美に思えるその瞬間を待ち望んでいた。
その時、聞き覚えのあるチリンチリンという音が鳴り響いた。遠くからミットがそれを見つけると、矢のように駆け寄り、まるで久しぶりに親友に会ったかのように頭を胸に擦り付けた。涙を流しながら犬を抱きしめ、撫でていると、彼女が現れた。
彼女は彼の隣に座り、ぼんやりと通りや交通を眺めながら、まるで何か面白いものを発見したかのように時折微笑んでいた。
「食べろ、坊や!」と男はソーセージを取り出し、犬の前に差し出した。犬は二度目の差し出しを待たずに、かがんで美味しそうにソーセージを食べた。食べながら尻尾を振り、時折男と女を見上げながら「なあ、どうして二人は何も言わずにずっとこっちを見てるんだ?」と問いかけているようだった。
「これ、スオンからだよ…」彼はつま先立ちで歩き、熟した赤いプラムの箱を彼女に渡した。
彼女は少し驚いて混乱し、プラムの箱を持って優しく言いました。「ありがとう!ミットを探すのを手伝ってくれてありがとう、お礼にプレゼントを用意しなきゃ…」。
彼はぼんやりと空を見上げた。頭上では、つがいのスズメが乾いた草を運び、高い枝に飛び移り、さえずっていた。彼女もつがいの鳥を追いかけ、時折そっと彼をちらりと見ては、笑みを隠すように顔を背けた。
「えっと…どうして私の名前を知っているんですか?」と彼女は突然振り返って尋ねました。
「私も…分かりません…ただ推測しているだけです。」
"推測?"
彼はうなずいた。「君の名前はいくつも推測したけど、あの日、なぜスオンと呼んだのかは覚えていない。君が振り返った時は驚いたよ。」
彼女は目を大きく見開いて彼を見つめた。彼が彼女を驚かせたのは、ミットを一瞬で見つけて以来、二度目だった。その夜、彼女は彼が自分の名前を正しく呼ぶのを聞いたが、どうして分かったのかと不思議に思う気にはなれなかった。ソーセージを食べ終えると、犬はそっと近づき、愛情を込めて彼の手を舐めた。
「もう行くわ。暗くなる前にミットを案内しなくちゃ」と彼女は立ち上がり、熟した赤いプラムの箱を持って優雅に首を傾げた。「あなたが私をあなたの家に招待してくれたら、ミットを探すのを手伝ってくれたことと、このプラムの箱をくれたことへのお礼に、塩卵のスポンジケーキを作るわ。」
彼は慌ただしい群衆の後ろに彼女の姿が消えていくのを黙って見ていた。
街は雨期に入り、雨は突然降り、そしてすぐに止み、通りには枯葉を運んで流れる小川が残っていた。彼はまだ馴染みの芝生に座り、思いついたばかりのメロディーを口ずさんでいた。いつの間にか、彼の心は、道の割れ目から芽吹く葉のように、温かく優しい陽光の中に溶け込んでいた。
VU NGOC GIAO (baodanang.vn) によると
出典: https://baogialai.com.vn/vet-nang-post561329.html


























![[インフォグラフィック] ベトナムとセネガルの伝統的な友好関係](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/4c96a604979345adb452af1d439d457b)







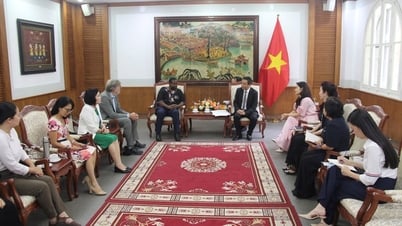




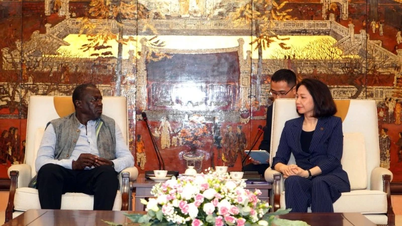


































































コメント (0)