「祖先の家」はスパイスは豊富だが、調和が欠けている。ヒュン・ラップ監督はセリフを巧みに利用して物語と観客の感情を誘導しているが、対立の解決方法は依然としてぎこちない。
先祖代々の家 5年ぶりにフイン・ラップの名がスクリーンに戻ってくる。 盲目の魔術師:死んだ人は手を挙げてください (2019年)。今回も、これまでのウェブドラマ作品で追求してきたスピリチュアル性とコメディ性を踏襲しつつ、テーマを軸に据えている。 先祖代々の家 依然として家族愛
物語は、バインセオを売る伝統を持つ、何世代にもわたる伝統を持つヒュイン家から始まります。映画の主人公は、家族との対立により故郷を離れ、何年も前に都会へ移住したZ世代のコンテンツクリエイター、ミ・ティエン(フォン・ミ・チー)です。
視聴者を引き付けるコンテンツについて「全くアイデアがない」ため、ティエンさんと親友はアイデアを見つけるために故郷に戻った。
この物語は問題に満ちているが、解決策がない。
ティエンが、何年も前に事故で亡くなった兄ジア・ミン(フイン・ラップ)の幽霊が見えることに気づいたことで、事態は急転する。兄の魂を解放するため、彼女は生前果たせなかった願いを叶えなければならない。その願いの一つは、家族が争っている家を守ることだった。
二つの世界をつなぐという考えは 先祖代々の家 新しいものではなく、懐かしい 私と悪魔が一つになる物語 トリン・ヴィ・ハオ著。財産紛争や兄弟間の争いもベトナム映画ではお馴染みのテーマだが、最近では 義理の姉妹 クオン・ゴックの遺跡が部分的に再現されています。
フイン・ラップ監督の映画は、家族間の対立、偏見が個人に及ぼす悪影響、悲劇につながる男性優位主義、文化や伝統的慣習の保存など、多くの問題を提起しています...
ヒュイン家が何世代にもわたって暮らしてきたこの先祖代々の家は、表面上は平和そうに見えたが、実際にはくすぶる争いを抱えていた。最大の問題は、何世代にもわたって彼らを苦しめてきた家父長制的なイデオロギーに起因していた。幼い頃から不当な扱いと中傷に苦しんできたミ・ティエンは、家族と不和になり、家を出ることを選んだ。少女である彼女は尊敬されず、あらゆる不運の源とみなされ、間接的に父と兄の死を招いた。

そのため、ミ・ティエンが故郷に戻るという決断は、彼女が長年抱えてきた葛藤や問題を解決し、長年の精神的トラウマを癒す旅へと繋がっていく。この設定は一見スムーズに思えるが、ここからストーリーは大きく崩れていく。
感情の葛藤は、ミー・ティエンと母と兄との葛藤の解決から、長年愛情と理解を得られなかった少女の心の変化まで、非常に表面的に、そして非常に描写的に再現されている。ティエンは、遊びに夢中になって問題を起こしたことを叱られた母親に腹を立て、殴られた兄に腹を立て、自分について悪い噂を広めた親戚に腹を立てている…
物語全体はフラッシュバックで簡潔に描かれ、登場人物の動機や性格について大きな疑問を提起する。多くの問題を提起するが、最終的には関係者に真実を語らせることで解決に向かう。同時に、フイン・ラップ監督は、ミー・ティエンと観客の双方に「多次元的な視点」をもたらすことを意図してセリフを用いている。しかし実際には、映画のセリフは途切れることなく、冗長で、アクション中心となっている。
素朴な教訓は涙を誘う一方で、物語は次第に誇張され長々とした状況に巻き込まれていく。登場人物たちのフラストレーションや、家族への怒りの瞬間は、突如として無意味なものにさえなってしまう。兄がもっと早く弟と分かち合うことを決意していたら、これらの出来事は存在しなかったかもしれないからだ。
一方で、 先祖代々の家 しかし、ジア・ミンがなぜ長年それらを心に抱え続け、問題が山積みになっていったのかは、いまだに説明されていない。映画の冒頭で提示された男性優位主義、あるいは多くの偏見の問題も、徐々に行き詰まりを見せた。
フイン・ラップがウェブドラマを映画化
フイン・ラップは精神的なテーマを借りて、家族関係の隠れた部分を探求するというアイデアを思いつきました。しかし、脚本の展開方法は限られており、形式も 先祖代々の家 映画的なクオリティが欠けているので、ウェブドラマのようには思えません。

この映画に登場する人物には、女性主人公の強引な設定から、邪悪で不格好な脇役の設定まで、多くの問題を抱えている。彼らの行動は論理性を欠き、フイン一家に降りかかる出来事も明らかに演出されている。
編集スタイルはホラー、コメディ、悲劇を巧みに切り替えており、観客の感情を突然中断させてしまう。監督が用いたシチュエーションコメディやセリフもまたお馴染みで、ミ・ティエンが失礼な親戚に反応するシーンは、まるで「言葉の戦い」から引用したかのようだ。 クックおじさんの息子。
フイン・ラップ監督は、映像で物語を語らせるのではなく、セリフを使って観客の感情を誘導し、影響を与えるという誤りを犯した。特筆すべきは、この映画のセリフが依然として「教科書通り」で、時にナイーブなところがあることだ。例えば、母親が緊急治療のために入院するシーンでは、ミ・ティエンが医師に手術費用について熱心に尋ね、「かなりの費用がかかります」という返答を受ける。あるいは、家族全員を招いてバインセオを作るためにキッチンに向かうシーンでは、登場人物のセリフはまるで教訓を暗唱しているかのようだ。文化的な要素を作品に挿入するというアイデアは称賛に値するが、フイン・ラップ監督はそれをより自然で繊細に表現する必要があるだろう。
映画初出演となったフォン・ミー・チーは、その素朴な風貌で好印象を残した。幼いミー・ティエンという少女は、頑固で傷つきやすい一面も持ち合わせているが、一方で感情豊かで、頑固ながらも優しく、涙もろい一面も持ち合わせている。
しかし、フォン・ミー・チーはキャラクターの感情表現において未熟であり、一方で、役柄の心理描写を習得するのに苦戦している。このキャラクターのトラウマは、「ママ、私が帰るのを待っているの? 私を愛しているの?」といったセリフで語られる必要など全くない。多くのシーンで、彼女は冷徹な瞳に限界を露わにし、特に恐怖、叫び、絶望といった場面では、時に本能的な行動に抑制を欠いている。
早すぎる死に悲しみに暮れる兄役を演じるフイン・ラップは、非常に芝居がかった演技を見せている。一方、ハン・トゥイとフイン・ドンの演技は実にバランスが取れているものの、彼らのキャラクターには演技の余地が欠けている。

予算の問題でビジュアル部分は 先祖代々の家 あまり印象に残らず、特殊効果にも欠点が見られた。しかし、シーンは比較的よく再現されていた。フォン・ミー・チーが歌ったいくつかの曲は、もしもっと自然に挿入されていれば、より感動的な効果があったかもしれない。
残念なのは、フイン・ラップ監督が「どんでん返し」を渇望したあまり、映画の結末を無理やり詰め込み、めちゃくちゃにしてしまったことだ。 先祖代々の家 ちょっとした癒しのメッセージできれいに終わるはずだったものが、騒音と混乱で観客を疲れさせるドラマの舞台と化した。
ソース




![[写真] A80ミッションを終えたパレード隊が人々に別れを告げる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/36d202d43ecc4ca8aede59a0e99f32ed)


![[写真] 建国記念日のバーディン広場の賑やかな雰囲気](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/c441c931800d4ff8a4a5b2ed4d4c496b)
![[写真] 警察がレ・ズアン通りのパレードを阻止](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/8f607af025d5437d828366c5e911bbda)


















































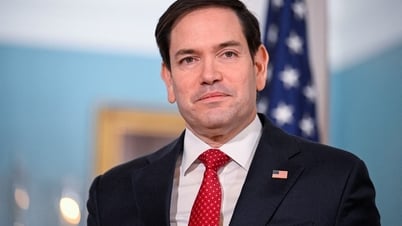








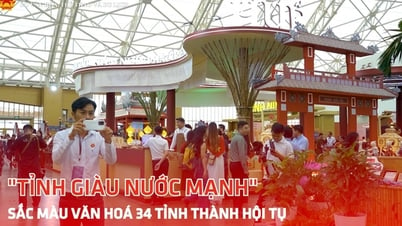


![[ライブ] 8月革命80周年と9月2日の建国記念日を祝うパレードと行進](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/ab9a5faafecf4bd4893de1594680b043)






















コメント (0)