7月18日、ハノイにおいて、真実国家政治出版社が古田元夫教授の著書『ベトナム ― 日本からの視点』の出版記念式典を開催した。
多くの歴史書とは異なり、本書は学術研究と個人的な経験、歴史分析、そして社会観察を融合させたものです。古田元夫教授は、アメリカに対する抗日戦争が激化していた1960年代後半にベトナム研究を始めました。1945年の八月革命に関する卒業論文をきっかけに、半世紀近くにわたる研究の歩みが始まり、ベトナム近代史に深い理解を持つ稀有な日本人となりました。
 |
| 古田元夫教授(左から2人目)とベトナムの研究者が、出版記念式典で読者と交流した。(写真:人民警察新聞) |
日常生活からマクロな問題までの視点
トゥルース・ナショナル・ポリティカル・パブリッシング・ハウスによると、本書は10章から構成され、国家建設の歴史、抵抗戦争、政治制度、 社会経済発展、対外関係、そしてベトナム人の習慣、信仰、生活など、多岐にわたる側面を網羅している。著者は多くのページを費やし、メコンデルタ、北西部、南東部、そしてハノイ、フエ、ホーチミン市などの都市部を実体験を通して描写している。
本書の特徴は「ボトムアップ」アプローチにある。古田元夫教授は、主要な政治的出来事だけに焦点を絞るのではなく、生活の細部を取り上げ、ベトナム社会の特徴を解説する。自転車に乗る際の「通行権の要求」や、警備員が現れた際に慌てて鏡を抱えて逃げ出す路上理髪師の姿などを描写する。そして、こう結論づける。「ベトナムは『無秩序』な社会ではなく、『統治しにくい』社会だ。 学会で使った『無秩序』という言葉は、決して否定的な意味ではなく、コミュニティの強い内的活力と自己統制力を指している」。
彼はまた、ベトナムと中国の試験制度の違いなど、多くの歴史的問題を分析し、ベトナムの中央集権体制は、国内のニーズから発展したというよりも、主に北からの圧力に対抗することを目的としたものだったと結論付けました。また、共産党指導下にあるベトナムの現在の政治体制は、「柔軟な中央集権化」という非常に独特な伝統を受け継いでいると彼は考えています。
信仰に関するセクションでは、越日大学の本部移転の際の「新築祝い」の儀式や、ヴォ・チ・コン通りの真ん中にあるチュンニャ村のガジュマルの木と門を精神的な理由からそのまま残した話を振り返りました。ベトナムにおける宗教と信仰は柔軟かつ実践的であり、社会行動と密接に結びついていると彼は言います。
特筆すべきは、ベトナム語の表記に関する研究が、漢字の影響、ノム文字の出現と衰退、そしてベトナム語のラテン語化の過程に至るまで、体系的に提示されている点である。著者はベトナム語を「静かな革命」と捉え、人々の知識の向上に貢献すると同時に、中国語研究の遺産の受容に「断絶」をもたらしたとしている。この点は今日でも議論の的となっている。
永続的な友情の象徴
出版記念式典で、国立政治出版社の理事長兼編集長であるヴー・チョン・ラム准教授は次のようにコメントしました。「400ページ以上に及ぶ本書では、古田元夫教授が客観的かつ献身的な視点から、ベトナムの歴史、文化、社会、国民、政治を生き生きと描き出しています。研究者としてだけでなく、親友として、また戦時中と平時の両方でこの国に住み、働き、経験してきた内部者としての立場からも、そのことが伺えます。」
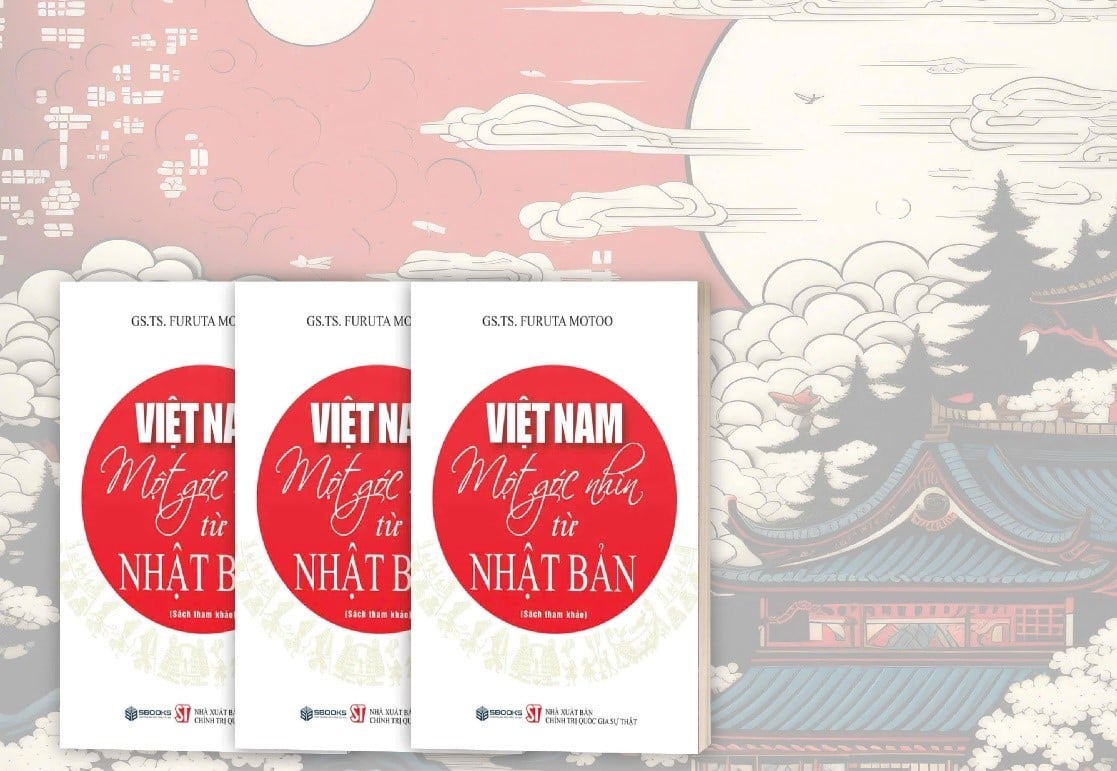 |
| 書籍『ベトナム ― 日本からの視点』。(写真:ナショナル・ポリティカル・パブリッシング・ハウス・トゥルース) |
伊藤直樹駐ベトナム日本大使は、本書はベトナムをより多角的に理解するための手がかりを提供し、多くの日本の読者にベトナムについてより深く知る機会を提供すると述べました。ベトナム語版の刊行は、ベトナムの人々が、思いやりのある外国人学者の視点を通して自分自身を振り返る機会となるでしょう。
刊行記念式典では、ベトナムと日本の代表団と古田元夫教授が読者と交流し、両国間の永続的な友好関係と、教育、文化、政治協力の促進に向けたコミットメントを強調しました。本書『ベトナム ― 日本からの視点』は、洗練された学術書であるだけでなく、両国民間の理解と友情を育む架け橋でもあります。
| 古田元夫教授著『ベトナム ― 日本からの視点』は、Truth National Political Publishing HouseとSbooksより出版され、価格は188,000ベトナムドンです。出版社の出版システム、またはTiki、Shopeeなどのeコマースプラットフォームでご購入いただけます。 |
出典: https://thoidai.com.vn/kham-pha-viet-nam-qua-goc-nhin-hoc-gia-nhat-ban-furuta-motoo-214923.html














































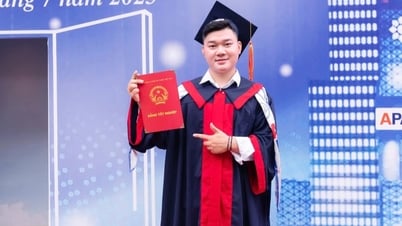




















































コメント (0)